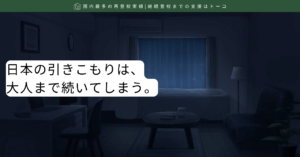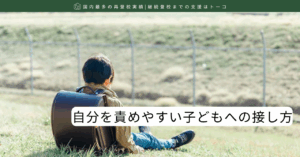夏休み明けの安定登校に向けたアプローチ
こんにちは。カウンセラーの竹宮と申します。
夏休みに入るこの時期、保護者の方からよくご相談を受けます。
「この夏でリズムを整えたいんですが、何から始めたらいいでしょうか」
「登校を再開させたいけど、無理をさせるのも怖いです」
「勉強も進んでいないので、遅れが心配で……」
どのご相談にも共通しているのは、「焦り」と「不安」ですが、これらは決して悪い感情ではありません。むしろ、お子さんのことを真剣に考えているからこそ生まれる感情です。
今日は、「夏休み明けに向けて、どう子どもと向き合えばいいのか」というテーマで書いてみたいと思います。
一般的によく言われるアドバイスも含めながら、実践的な視点でお伝えできればと思います。
夏休みは「リセット」ではなく「整理」の時期
「夏は立て直しのチャンス」という言葉の裏側
夏休みは、登校が難しくなっていたお子さんにとって、一つの「区切り」となるタイミングです。
周囲のクラスメイトも休んでいますし、学校行事も止まっている。
そのため、登校していないことへの「置いていかれる感じ」が、少しだけ和らぎます。
「この夏でリセットしましょう」という言葉がよく聞かれますが、この言い方には少しだけ違和感があります。
なぜなら、人の感情や悩みはスイッチのように「オフ」にできるものではないからです。
むしろ、「リセットしなきゃ」と考えること自体が、プレッシャーになってしまうこともあります。
この時期に大切なのは、「リセット」ではなく「整理」だと考えています。
整理とは、感情に名前をつけること
たとえば、子どもが「学校に行きたくない」と言ったとします。
その時、親としてはどうにか前向きにさせたくて、「何が嫌なの?」と聞くかもしれません。
でも、子どもにとっては、それをうまく言葉にするのが難しい。
むしろ、「うまく説明できない自分」に対して、もどかしさを感じてしまうことさえあります。
そこでおすすめしたいのが、「気持ちを書き出す」ことです。
これは心理学的にも有効なアプローチです。
感情に名前をつけて言語化することで、脳の中でその感情が整理され、コントロールしやすくなることがわかっています。
親がコントロールしようとすると、うまくいかない
この時期、保護者の方がよくされるアプローチの一つが、「生活リズムを整えよう」とすることです。
たとえば、
・朝は〇時に起きよう
・一日1ページは問題集をやろう
・夜はスマホを控えよう
といったことを決めて、スケジュールを作ろうとされます。
これらは、うまくいかないケースも多いのが実情です。
その理由は、「誰が主導しているか」にあります。
親が良かれと思って組んだスケジュールでも、子ども自身に「やろう」という気持ちがなければ、ほとんどの場合、定着しません。
むしろ、「決められたことを守れなかった」という自己否定感を生んでしまうことすらあります。
「やる気がない」のではなく「未来が見えない」
「うちの子はやる気がなくて……」
この言葉も、よく聞きます。
ですが、子どもたちを見ていると、本当に「やる気がない」子はほとんどいません。
正確に言うなら、「動き出すきっかけが持てない」状態です。
それはなぜでしょうか。
一つは、「未来が見えない」からです。
たとえば、登校できていない日々が続くと、「このままどうなるんだろう」「高校に行けるのか」「就職できるのか」といった不安ばかりが先行します。
そして、「どうせ無理だ」という気持ちが強くなっていく。
このような状態では、そもそも「頑張る理由」が見つかりません。
書き出すことで、諦めていた希望を探すこと
何を書き出せばいいのか
まずは大きな紙を用意して、「今の気持ち」をできるだけ自由に書いてもらうのが大切です。
形式は問いません。
・学校のことで不安に思っていること
・友達とのことで気になること
・勉強の遅れへの心配
・将来への不透明さ
・親への思い(言いにくくても、書いてもらって大丈夫です)
こうしたことを繋げながら言葉にしていくと、自分でも気づいていなかった気持ちに触れることがあります。
「本当は、戻りたいのかもしれない」
「勉強、追いつけるならやってみたい」
「進学、諦めたくない」
この「望みのかけら」が出てくることが、すべてのスタートになります。
望む未来像を話す時のコツ
ここでポイントなのが、「できる/できない」の判断を持ち込まないことです。
現時点の成績や出席日数に引っ張られず、「理想像」を一度しっかり共有する。
たとえば、子どもが「〇〇高校に行ってみたい」と言ったとします。
その時、「今のままだと難しいよ」と返してしまうと、せっかく出てきた気持ちがしぼんでしまいます。
そうではなく、「行きたい理由を聞かせて」「どういうところが良さそうに感じる?」と広げていく。
それだけでも、子どもは「考えていいんだ」と思えるようになります。
子ども主導で「夏休みの過ごし方」を設計する
「やること」ではなく「やりたいこと」を軸にする
ここまで、気持ちを書き出し、未来像を話すことで、少しずつ「自分のために動く」準備が整ってきました。
このタイミングでようやく、「夏休みの過ごし方」について話し合っていきます。
ただし、ここで意識してほしいのは、「子ども主導で考える」ということです。
つい親は、「これをやってほしい」「このくらいはやるべき」と、内容を決めてしまいがちです。
しかし、それでは結局、受け身の姿勢のままです。
あくまで、「どう過ごしたい?」と尋ねることから始めてください。
たとえばこんな会話です。
「この夏、どんなふうに過ごせたら、2学期に向けてちょっと気持ちが楽になると思う?」
「時間があるからこそ、試してみたいことってある?」
「学校のことも含めて、気になることって今どんな感じ?」
こうした問いかけは、「考える力」と「自分で決める感覚」を育ててくれます。
それが、後々の行動の持続にもつながっていきます。
スケジュールは「守ること」が目的ではない
スケジュールを立てたあと、多くの家庭で出てくる悩みがこちらです。
「最初はやる気を見せてたんですけど、3日で崩れました」
「また守れなかった……と本人が落ち込んでいて」
こういう時、親としても「せっかく一緒に考えたのに」とがっかりします。
でも、ここで必要なのは注意や叱責ではなく、「リカバリーの視点」です。
そもそも、子どもが立てたスケジュールは「試しにやってみた」段階。
守れないことも、想定の範囲内です。
大事なのは、「なぜ崩れたのか」「どうすればもう一度やってみようと思えるか」を一緒に振り返ることです。
たとえば、
・そもそも予定が多すぎた
・朝起きられなかったのは寝る時間が遅かったから
・やる気が出ない日は何が重く感じたのか
こうした振り返りは、自分自身を知るヒントになります。
「守れなかった」ではなく、「どうすれば次はやりやすいか」と考えることで、実行力が育っていきます。
気持ちの浮き沈みは「波」として受け止める
夏休み中、お子さんの様子に一喜一憂してしまうこともあるでしょう。
昨日は前向きだったのに、今日はまたふさぎ込んでいる……そんな日もあるかもしれません。
ですが、それは決して「戻ってしまった」ということではありません。
人の感情には波があります。
とくに不登校の背景には、自己肯定感の低下や、過去の出来事に対する未整理の感情が関わっていることが多いため、安定するにはある程度の時間が必要です。
心理学では、こうした状態を「揺らぎ期」と呼びます。
少しずつ前を向けるようになっても、時折ネガティブな気持ちが顔を出す。
それ自体は自然なことなのです。
ここで保護者としてできることは、波が来た時に「戻った」と判断せず、「今は下がってる時期なんだな」と受け止めること。
それが、子どもにとっての安心感になります。
この夏を「回復のきっかけ」にするために
今回は、「夏休み明けの安定登校に向けたアプローチ」と題して、お子さんとどのように向き合えばいいのかを、専門的な視点から整理してみました。
もう一度、要点をまとめておきます。
- 夏休みは「焦ってリセットする」時期ではなく、「感情を整理する」時期として捉えること
- 親がスケジュールをコントロールするのではなく、子ども自身が「望む姿」を言葉にすることを手助けすること
- 未来のイメージを語る際は、「できる/できない」ではなく、「何を望んでいるか」に注目すること
- スケジュールは完璧に守らせるのではなく、崩れた時にどう振り返るかが大切であること
- 気持ちの浮き沈みを「波」として受け入れ、変化を長い目で見守ること
大切なのは、「どうすれば登校させられるか」ではありません。
「どのようにすれば、子どもが自分の気持ちを取り戻していけるか」
「どうすれば、自分の未来をもう一度描こうと思えるようになるか」
そのための“きっかけ”を一つでも多くつくっていくことが、夏休みの本当の意義だと、私は考えています。
それが、お子さんにとっても、保護者の方にとっても、意味のある夏になります。
どうか無理のない範囲で、少しずつ取り組んでみてください。
当社では再登校支援プログラムを提供しておりますが、派生版として「安定登校に向けた夏休みの過ごし方ガイド」も用意しております。ご興味のある方はぜひお問合せください。
関連記事
【国内最多の登校支援実績】トーコについて
私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。
「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。
それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。
無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。