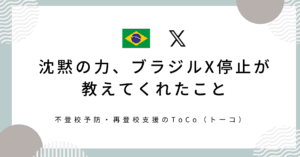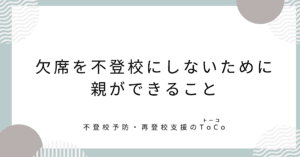不登校における「未病」の大切さとは?
目次
- 子どもが示す「小さなサイン」とその背景
- 未病段階での親子の対話の築き方
- 生活リズムを整えることで心と体を守る
- 夜の過ごし方が翌日に影響する
- 日中に“少しの活動”を取り入れる
- 生活リズムの改善は「習慣化」がカギ
不登校は、子どもが学校へ行かなくなる前に、さまざまな兆候を示すことがあります。これらのサインを早期に察知し、適切に対応することが、不登校の予防や早期解決につながります。本章では、子どもが発する小さなサインと、その背景にある心理状態、そして保護者としての具体的な対応策について詳しく解説します。
参考データ
子どもが示す「小さなサイン」とその背景
子どもが不登校に至る前には、以下のようなサインが見られることがあります。
- 朝起きるのがつらそうになる:以前はすぐに起きていたのに、「あと5分…」と布団から出られなくなることが増える。
- 体調不良を頻繁に訴える:「お腹が痛い」「頭が痛い」など、特に朝や登校前に体調不良を訴えることが増加する。
- 学校の話題を避ける:学校での出来事や友人関係について話したがらなくなる。toco.mom
- 宿題やテストへの強い拒否感:宿題をやりたがらない、テスト前に極度の不安を示す。
- 情緒の不安定さ:些細なことで怒ったり、泣いたりするなど、感情の起伏が激しくなる。
- 食欲の変化:食事量が急に減ったり、増えたりする。
- 睡眠リズムの乱れ:夜更かしが増え、朝起きるのが遅くなる。
これらのサインは、子どもが学校生活や人間関係でストレスや不安を感じている可能性を示しています。特に、いじめが原因の場合、子どもは直接的に「いじめられている」と言わないことが多く、上記のような間接的なサインでSOSを発していることがあります。
保護者としての具体的な対応策
子どもがこれらのサインを示した場合、保護者として以下のような対応が考えられます。
- 子どもの話をじっくり聞く:子どもが話したいと感じたときに、否定せず、遮らず、最後まで話を聞く姿勢を持つ。「そう感じているんだね」と共感を示すことで、子どもは安心感を得る。
- 焦らず待つ:子どもが自分の気持ちを言葉にするには時間がかかることもある。保護者が焦ると、そのプレッシャーが子どもに伝わり、さらに心を閉ざしてしまう可能性があるため、子どものペースを尊重する。
- 家庭を安心できる居場所にする:家庭がリラックスできる場所であることを子どもに感じさせる。保護者が穏やかに接することで、子どもは安心感を得る。
- 生活リズムを整える:夜更かしや昼夜逆転を防ぎ、規則正しい生活を送ることで、心身の健康を保つ。朝は一緒に朝食をとる、夜は決まった時間に就寝するなど、家族全体で生活リズムを整える努力をする。
- 学校や専門家と連携する:子どもの状況を学校の担任やスクールカウンセラーと共有し、適切なサポートを受ける。必要に応じて、外部の専門家や支援団体に相談することも検討する。
これらの対応を通じて、子どもが抱える不安やストレスを軽減し、再び学校生活に前向きになれるようサポートすることが重要です。
未病段階での親子の対話の築き方
子どもが不登校の兆候を見せ始めたとき、親ができる最も大切なことの一つが「対話」です。しかしこの“対話”とは、単に「話をすること」ではありません。ポイントは、子どもが心を開いて本音を話せるような“聞き方”にあります。
「問い詰めない」ことがスタートライン
子どもが学校に行きたがらない、あるいは不機嫌だったり、黙って部屋にこもるようになったとき、親としてはつい「何があったの?」「学校で何か嫌なことがあった?」と聞きたくなります。しかし、ここでストレートに原因を追及すると、子どもは「責められている」と感じてしまい、心を閉ざしてしまうことがあります。
この段階では、子ども自身も自分の気持ちをうまく言語化できていないことが多いです。頭の中がモヤモヤしていて、「理由は分からないけど学校に行きたくない」と感じていることもよくあります。ですから、親がまずやるべきは「答えを求めない姿勢」で向き合うことです。
「聞く」ではなく「聴く」姿勢
親子の会話で信頼関係を築くには、“傾聴”の姿勢がカギになります。以下のポイントを意識すると、子どもは安心感を得やすくなります。
- 目線を合わせて話す
子どもが安心できる距離で、正面からではなく横並びに座るのも効果的です。食事中や散歩中など「ながら会話」も有効です。 - あいづち・うなずき
「うん」「そうなんだ」「それは大変だったね」など、子どもの話を受け止めている姿勢を伝えましょう。 - 話の主導権は子どもに
「もっと詳しく教えて」とは言わず、「教えてくれてありがとう」と言うことで、無理に深掘りせず、安心できる場を保ちます。
小さな会話の積み重ねが「信頼」を育てる
不登校の未病段階では、毎日少しずつ会話の“回数”を重ねることが大切です。特別な話題を出さなくても構いません。「今日のおやつ何にする?」「一緒にコンビニ行く?」など、日常の些細な言葉のキャッチボールが信頼を育てます。
こうした何気ない会話の中で、子どもがふと本音をポロッと漏らすことがあります。それをきっかけに、「ああ、そう思ってたんだね」と受け止めることができれば、そこから少しずつ心の距離を縮めることができます。
無理に「学校」の話をしない
学校のことに触れたくない子どもに対して、「学校に行かないの?」といった言葉は重荷になります。あくまで学校の話題は子どもから出てくるまで待つことが原則です。
また、「将来どうするの?」「高校はどうするの?」という先の話をすると、子どもは自分を責めてしまったり、逃げ場がないと感じてしまいます。未来の話はタイミングを見て慎重に。
感情のコントロールは大人の仕事
子どもが親に心を開かない背景には、「親が感情的になることへの恐れ」がある場合も多いです。「なんでそんなにだらけてるの!」「いい加減にして!」といった叱責は、一瞬で子どもとの信頼関係を壊してしまいます。
親も人間ですから、感情的になってしまうことは当然あります。しかし、そのときこそ深呼吸をして、「この子は困っているだけかもしれない」と視点を変えてみてください。怒りではなく、共感と安心を与えることが、子どもが回復に向かう土台になります。
生活リズムを整えることで心と体を守る
不登校の未病段階において、子どもの心の問題は体のリズムと密接に関係しています。心が不安定になると睡眠が乱れ、生活リズムが崩れる。そしてその乱れがさらなる不安や無気力感を呼び、不登校につながる——これは珍しい流れではありません。
逆に言えば、「生活リズムを整えること」が、子どもの心身の安定を取り戻すきっかけになり得るのです。
「体を整えることが心を整える」
まず知っておきたいのは、「心の不調」は体に現れやすいということです。例えば、朝になると腹痛や頭痛を訴える、ぼーっとして無気力になる、食欲が落ちるといった変化です。これは決して「仮病」ではなく、自律神経が乱れているサインかもしれません。
自律神経は、規則正しい生活によって整っていきます。だからこそ、生活リズムの見直しは、未病段階の子どもにとって非常に重要な“予防的アプローチ”なのです。
朝が「一日の軸」になる
生活リズムの要は「朝」です。夜型の生活をしていると、朝起きることが苦痛になり、そこから「学校に行きたくない」「何もしたくない」へと気持ちが流れてしまいます。
保護者ができる支援として、次のような「朝のサポート」が効果的です。
● 一緒に朝日を浴びる
朝の光を浴びることで、体内時計がリセットされ、セロトニン(心を安定させる脳内物質)の分泌が促進されます。起きる時間がバラバラな子どもでも、「カーテンを開けて太陽の光を入れる」「5分だけでもベランダで深呼吸」など、できる範囲で十分です。
● 朝食を一緒にとる
食事をすることで身体が「活動モード」に切り替わります。朝食を抜くと低血糖状態が続き、頭がぼーっとしてしまい、気持ちも沈みやすくなります。最初は少量のフルーツやスープなど、子どもが食べやすいものから始めても構いません。
● 起床時間を徐々に調整
いきなり「7時に起きよう」としても難しい場合は、10時→9時→8時と、段階的に早めていきましょう。無理のないスケジュール調整が、ストレスを最小限に抑えます。
夜の過ごし方が翌日に影響する
夜遅くまでゲームやスマホをしていると、脳が刺激を受け続けてしまい、眠りの質が下がります。結果として翌朝起きられず、日中の活動に影響が出てしまうという悪循環が生まれます。
● スマホ・ゲームのルールづくり
「21時以降はスマホを親に預ける」「寝室にはスマホを持ち込まない」などのルールを家庭内で設けることも検討してみてください。強制ではなく「一緒に決めよう」というスタンスが大切です。
● 寝る前の“クールダウン”タイム
就寝の30分〜1時間前には、照明を落とし、テレビやスマホの画面を見ないようにします。代わりに、音楽を聴いたり、アロマを焚いたり、読書したりといった“脳を落ち着ける時間”を習慣にするとよいでしょう。
日中に“少しの活動”を取り入れる
「不登校=外出しない生活」になりがちですが、心身を安定させるためには、日中の適度な活動が不可欠です。特に軽い運動は、セロトニンの分泌を促し、抑うつ感や不安を和らげる効果があります。
● 散歩・公園・家庭菜園
「家の周りを10分歩く」「公園で花を見に行く」「家庭菜園で水をあげる」といった行動が、心をほぐします。大切なのは「がんばらなくていい活動」にすることです。
● 家事を一緒にやる
「洗濯物を一緒に干す」「野菜を一緒に切る」なども立派な活動です。達成感や役割意識を育てるとともに、生活の中にリズムを取り戻す足がかりになります。
生活リズムの改善は「習慣化」がカギ
生活リズムは一朝一夕に整うものではありません。親も子も、短期的な成果を求めすぎず、「一つずつ整えていこう」という気持ちで進めることが大切です。
また、スケジュールは子どもと一緒に作ることをおすすめします。カレンダーやホワイトボードを使って「朝8時に起きる」「10時に散歩する」と視覚的に共有すると、子ども自身の意識も変わっていきます。
まとめ
不登校の「未病段階」において、保護者ができることはたくさんあります。兆候に早く気づき、家庭の中で安心できる土台を整えること。そして、必要に応じて学校や専門機関とつながることが、子どもを支える強力な柱になります。
忘れてはならないのは、子どもの問題に向き合っている保護者自身も、強いストレスや不安を抱えているということです。
必要があれば、保護者自身がカウンセリングを受ける、信頼できる友人や家族に話すなど、“大人の心のケア”も大切です。親が穏やかでいることが、子どもにとって一番の安心材料となるからです。
「どうしていいかわからない」と感じる時は、立ち止まってもかまいません。大切なのは、そこで一人きりにならないこと。親が自分を責めすぎず、誰かとつながることで、子どもにも「大丈夫」と思える環境が広がっていきます。
【国内最多の登校支援実績】トーコについて
私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。
「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。
それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。
無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。