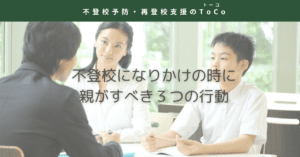「親」のスマホ依存が与える子どもへの影響とは?
目次
- 愛着形成とスマホ依存の影響
- スマートフォン依存の仕組みと親の行動変容の必要性
- スマートフォン依存を克服するための具体的な方法
- 親子の関係再構築が不登校克服のカギ
- 親子関係の再構築のための具体的なアプローチ
- 最後に: スマートフォンとの新しい付き合い方
愛着形成とスマホ依存の影響
はじめまして。不登校や引きこもりを専門に支援している児童心理カウンセラーの成田と申します。
今までの多くの事例から、不登校や引きこもりの問題は単なる「子どもの問題」ではなく、「親子関係や家庭環境の中で形作られる問題」であることが多いと感じています。
そして、現代の親子関係の課題として、近年急速に注目されつつあるのが「親のスマホ依存」です。
この問題は、親の無意識のうちに進行し、結果として子どもの心に深刻な影響を与える可能性があります。
子どもの健全な成長に欠かせないのは、親との良好な愛着形成です。
しかし、親がスマートフォンに多くの時間を費やすことで、この愛着形成が阻害されるケースが増えています。
まず、この問題の本質に触れるために、愛着形成がどのように子どもに影響を及ぼすか、そしてそれが親のスマホ依存によってどのように変容するのかを詳しく掘り下げていきます。
愛着形成の重要性
「愛着形成」という言葉を耳にされたことはあるでしょうか。
これは、乳幼児期から学童期にかけて子どもが親との間で築く、信頼や安心感の基盤を指します。
たとえば、子どもが泣いたときにすぐに対応してくれる親の姿を見たり、子どもが発した些細な言葉や行動に対して親が関心を持って応答する、こうした繰り返しの中で子どもは「自分は愛されている」と感じ、心が安定していきます。
しかし、この愛着形成の基盤が不十分であると、子どもは精神的な不安定さを抱えるようになります。
親からの適切な反応が得られない子どもは、「自分は大切にされていないのかもしれない」という感覚に陥りやすくなります。
このような状況は、子どもの自己肯定感を著しく低下させ、結果的に学校生活や人間関係において消極的になる原因を作り出します。
たとえば、カウンセリングを通じて接してきたある小学生のケースでは、親が家にいる間ずっとスマートフォンでSNSを見ているため、子どもが話しかけても「うん」や「後で」といった短い返答で終わってしまう状況が続いていました。
その結果、子どもは自分の話が重要ではないと感じるようになり、学校での出来事や友達との関係について話すことも次第に避けるようになりました。
最終的には、学校でのトラブルを一人で抱え込み、不登校という形で表面化したのです。
スマートフォン依存による親子の関係断絶
スマートフォンが親子関係に与える影響の一つに、「親子の断絶」が挙げられます。
断絶とは、物理的に離れているわけではなく、心理的な距離が広がることを意味します。
親がスマートフォンを使っている時間、子どもとの会話や視線の共有は明らかに減少します。
その結果、子どもは「親にとってスマホの方が自分より重要だ」と感じるようになります。
心理学的な視点から言えば、子どもにとって親からの視線や反応は、心の発達に欠かせない「栄養」です。
親の視線を通して子どもは「自分は価値のある存在だ」と感じることができます。
しかし、親がスマートフォンを見続けていると、この視線の共有が減少し、子どもに心理的な飢餓状態が生まれるのです。
この飢餓状態が続くと、子どもはどうなるでしょうか。
子どもはまず、親の関心を引こうとあらゆる手段を試みます。
しかし、それでも親がスマホに夢中で反応を示さない場合、子どもは「どうせ何をやっても無駄だ」と学習してしまいます。
この状態が長引くと、子どもは外の世界や他者との関係にも消極的になり、不登校や引きこもりの原因となる可能性があります。
親が意識しない「無視」の影響
興味深い研究があります。
それは、「無視」の影響が子どもの精神発達にどれだけ大きなダメージを与えるかを示したものです。
無視とは、言葉や行動での否定ではなく、親が子どもに関心を示さない状態を指します。
スマートフォン依存の親が無意識のうちに行う行動が、まさにこれに該当します。
この無視の影響を受けた子どもは、自分の存在意義に疑問を持ちやすくなります。
そして、それが引き金となり、学校生活や人間関係においても消極的な態度を取るようになります。
相談いただいたご家庭の事例では、親がスマホゲームに夢中で会話がほとんどなかったため、中学生の子どもは家庭内での孤独感を深め、学校でも友達との関係を構築できず、最終的に不登校となりました。
スマートフォン依存の仕組みと親の行動変容の必要性
スマホ依存の仕組みとその強力さ
現代のスマートフォンは、私たちの生活を便利にしてくれる一方で、非常に強力な依存性を持っています。
なぜこれほど多くの人がスマートフォンを手放せなくなってしまうのか。それは、スマートフォンやアプリが「人間の脳の仕組み」に巧みに働きかける設計になっているからです。
スマートフォンが私たちに与える刺激の一つに「断続的な報酬」があります。
これは、SNSの通知やゲームの報酬システムによって実現されています。
たとえば、SNSを開けば「いいね」やコメントといった小さな報酬が得られる可能性がありますが、そのタイミングは予測できません。
この「予測できない報酬」の仕組みは、人間の脳にとって非常に魅力的です。
脳内でドーパミンと呼ばれる快感を司る物質が分泌され、私たちはその刺激を求めてスマホを手に取るようになります。
さらに、ゲームでは「次に何か良いことが起きるかもしれない」という期待感を与え続けることで、ユーザーをゲームに引き込む仕組みが存在します。
このような射幸心を煽る仕組みが、親たちを含めた多くの人をスマートフォンに夢中にさせ、気づけば1日が終わっている、という状況を引き起こしているのです。

親がスマートフォン依存に陥る背景
親がスマートフォンに頼りがちな理由の一つに、「便利さ」や「息抜きの手段」という側面があります。
特に子育て中の親にとって、スマートフォンは情報収集や友人とのつながり、ストレス発散など、多くの役割を果たす貴重なツールです。
また、子育てにおいて孤立感を抱える親にとって、SNSやオンラインコミュニティは大切な居場所になることがあります。
しかし、こうした利用が「無自覚の依存」に変わると問題が生じます。
たとえば、子どもが目の前にいるのに無意識にスマートフォンを開いてしまう、子どもとの会話中に通知が来ると反射的に画面を見てしまう、という行動が積み重なると、親子の関係性に影響が出るのは避けられません。
親自身の変化が必要な理由
では、どうすればこの問題を解決できるのでしょうか。まず大切なのは、「親自身が変わること」です。
親がスマートフォン依存から抜け出すことで、子どもとの接点を増やし、家庭内のコミュニケーションを円滑にすることができます。
親がスマートフォンに費やす時間を意識して減らす努力をすることで、子どもにとって「自分は親にとって大切な存在だ」という感覚が再び生まれます。
また、親がスマートフォン依存を克服する姿を見せることは、子どもへの良い手本にもなります。
子どもは親の行動を観察し、それを模倣する傾向があります。
親が自らのスマートフォン依存をコントロールする姿勢を示せば、子どももその影響を受けて、スマートフォンとの適切な付き合い方を学ぶことができるのです。
スマートフォン依存を克服するための具体的な方法
親が依存を克服する第一歩
スマートフォン依存を克服するためには、まず「自分がどれだけスマートフォンを使っているかを知る」ことから始めるのが効果的です。
現在は、多くのスマートフォンに利用時間を記録する機能がついています。この機能を活用し、1日にどれくらいの時間をスマートフォンに費やしているのかを確認してみましょう。
例えば、1日に4~5時間をスマートフォンに費やしているとしたら、その時間の一部を子どもとの触れ合いに充てることを考えてみてください。
「子どもと一緒に過ごす時間を増やす」という明確な目標を立てることで、スマートフォンに依存する生活から少しずつ抜け出すことができます。
具体的な取り組み例
- 時間帯を決める
スマートフォンを使用する時間帯をあらかじめ決め、ルールを作ることが有効です。
たとえば、「子どもが起きている間はスマートフォンを見ない」「子どもと食事をする際はスマートフォンを別の部屋に置く」といった具体的なルールを設けてみましょう。 - スマートフォンの通知をオフにする
通知は依存を強化する原因の一つです。
通知が来るたびに画面を見る習慣がついてしまうため、SNSやゲーム、メールの通知をオフにすることで無駄な使用を防ぐことができます。 - 家族でスマートフォンの利用ルールを共有する
家族全員でスマートフォンの使用に関するルールを話し合い、共有することも効果的です。
「夜8時以降はスマートフォンを触らない」「家族で過ごす時間はスマートフォン禁止」など、家族全体で取り組むことで、親自身も習慣を守りやすくなります。 - 子どもと一緒に楽しむ時間を増やす
スマートフォンに時間を費やす代わりに、子どもと一緒に楽しめるアクティビティを増やしてみてください。
たとえば、一緒に料理をする、散歩に出かける、本を読むなど、スマートフォン以外の選択肢を意識して取り入れることが重要です。
親子の関係再構築が不登校克服のカギ
親の行動が子どもに与える影響
親がスマートフォン依存を克服し、子どもとの時間を増やすことで、子どもには多くのポジティブな変化が現れます。
まず、親が自分に向き合ってくれると感じることで、子どもは安心感を得られます。
この安心感は、子どもの自己肯定感を高め、学校生活や人間関係における積極性を引き出す原動力となります。
また、親がスマートフォンに頼らずに子どもと接する姿勢を示すことで、子どもは「人と向き合うことの大切さ」を自然と学ぶことができます。
これは、子どもが将来社会に出たときに良好な人間関係を築く力にもつながるのです。
不登校や引きこもりの問題を解決する上で、私は一貫して「親子関係の再構築」が最も重要な要素の一つであると考えています。
不登校の原因は、学業のプレッシャーや友人関係、個々の気質など様々ですが、その問題が「長期化する」要因の多くは、家庭環境に起因します。
そして、その中でも特に大きな役割を果たすのが親子関係です。
ここから、親子の関係が不登校克服にどのように関わるのかを深掘りし、さらに再構築の具体的なステップについて詳しく説明します。

不登校を長引かせる「日常のパターン化」
まず、不登校の大きな特徴として挙げられるのは、その状態が日常のパターンとして固定化されてしまうことです。
不登校が長期化する理由は、学校に行かない生活が「子どもにとって居心地が良いもの」として定着してしまう点にあります。
これは、単に子どもが怠けているわけではありません。不登校の初期段階では、学校での辛い経験や心の負担から一時的に逃れようとする防衛本能が働きます。
その結果、家での生活が「安全地帯」として位置づけられ、学校へ戻るモチベーションがどんどん失われていくのです。
ここで、親の行動が非常に大きな意味を持ちます。
親が無意識のうちに子どもの現状を「受け入れすぎる」ことで、子どもが学校に行かない生活をさらに当たり前と感じるようになります。
例えば、「家で子どもが落ち着いているなら、それで良いのではないか」と考え、子どもに特別なアプローチを取らず、ただ見守るだけの状態が続くとします。
このような見守りは、一見すると子どもの自立を尊重しているようにも見えますが、実は逆効果になることもあります。
親が子どもに「挑戦する機会」を与えないまま、日常のパターンを固定化させると、子どもはそのコンフォートゾーンから抜け出す力を失ってしまいます。
この状況を打破するためには、親が意識的に「関わり方」を変え、子どもとの関係を新たに築き直す必要があるのです。
親子の関係が不登校克服に及ぼす影響
不登校を克服する過程で、親子関係の再構築が重要である理由は、子どもにとって親の存在が心理的な「基盤」となるからです。
どれほど学校での経験が辛かったとしても、家庭が安心感に満ちていれば、子どもはもう一度外の世界に向き合う勇気を持つことができます。
一方で、家庭内に緊張感や孤独感があると、子どもはますます内向的になり、外の世界と関わることを避けるようになります。
親子関係を再構築する過程で特に重要なのは、「親が子どもの感情に寄り添う」という姿勢です。
不登校の子どもたちは、学校での辛さや友人関係のトラブル、または学業へのプレッシャーなど、さまざまなストレスを抱えています。
しかし、それを表に出すことが苦手な子どもも少なくありません。
特に小学校高学年や中学生になると、「自分の感情を伝えるのは恥ずかしい」と感じたり、「親に心配をかけたくない」と思ったりして、気持ちを隠すケースが多いのです。
このとき、親が「どうして学校に行かないの?」と問い詰める姿勢ではなく、「今どんなことが一番つらい?」と穏やかに問いかけたり、「学校に行くことだけが全てではないよ」と子どもの気持ちを肯定したりすることで、子どもは徐々に自分の感情を開示しやすくなります。
このプロセスが、子どもが不登校の状態から一歩を踏み出すための第一歩となるのです。
スマートフォン依存の改善が親子関係に与える影響
親子関係を再構築する上で見落とされがちなのが、親自身の行動、特に「スマートフォンの使い方」です。
親がスマートフォンを手放せない状態でいると、子どもは親の関心が自分ではなくスマートフォンに向けられていると感じてしまいます。
こうした感覚が続くと、子どもは「どうせ自分に話しかけても親はちゃんと聞いてくれない」と考え、親に対して心を閉ざしてしまうことがあります。
例えば、母親が毎晩リビングでスマートフォンを見続けていることが原因で、子どもが「自分の話をしても母親は聞いてくれない」と思ってしまう相談事例がありました。
そこで、トーコの支援を通じて母親がスマートフォンの利用時間を減らし、夜はスマホを別室に置いて子どもとの時間を増やすようにしたところ、(他の働きかけもありましたが)子どもが母親に悩みを打ち明ける機会が増え、最終的に学校復帰への意欲を見せるようになったのです。
親がスマートフォンホ依存を改善することは、親子の関係を再構築し、不登校克服への道を開くための大きな一歩となります。
親子関係の再構築のための具体的なアプローチ
親子関係を再構築するためには、以下のような具体的なアプローチが効果的です。
- 子どもの声に耳を傾ける
子どもが話をしたいと思ったときに、親がすぐに対応できるようにすることが大切です。
親がスマートフォンに夢中になっていると、この「タイミング」を逃してしまいます。
特に夜の時間帯はスマホを手放し、子どもと会話できる環境を整えましょう。 - 親自身が行動で示す
「スマートフォンの時間を減らす」「外出して一緒に体を動かす」「子どもの趣味に付き合う」など、親が積極的に行動を変える姿を見せることで、子どもは「自分のために親が変わってくれた」と感じ、親子の信頼関係が深まります。 - 小さな成功体験を共有する
子どもが家で取り組んだ些細なことでも、「よくやったね」と認めてあげることで、子どもは自己肯定感を高めることができます。
また、親子で一緒に楽しめるアクティビティを増やし、共有の思い出を作ることも関係改善につながります。
親子関係が築けるとき、子どもは動き出す
親子の関係が再構築され、家庭が子どもにとって本当の意味での「安心できる場所」となったとき、子どもは外の世界に向き合う力を徐々に取り戻します。
不登校の克服には時間がかかる場合もありますが、親が変わり、家庭環境が改善されれば、子どもも自然と変化していきます。
不登校を克服するための第一歩は、子どもを急かすことでも、問題を根掘り葉掘り聞き出すことでもありません。
親が「一緒にいること」「向き合うこと」に意識を向け、子どもとの絆を再構築することが、何よりも効果的な解決策なのです。
最後に: スマートフォンとの新しい付き合い方
親がスマートフォンを使う時間を減らし、子どもと向き合う時間を増やすことは、親子関係を深めるだけでなく、子どもの心の成長に大きな影響を与えます。
スマートフォンは便利なツールですが、それに依存することで失われるものも多いことを忘れてはいけません。
スマートフォンを使う時間を見直し、子どもとの触れ合いを優先することで、親子の絆はさらに強固なものになります。
そして、この絆こそが、不登校や引きこもりを克服し、子どもが自分の力で未来を切り開いていくための土台となるのです。
親が少しずつスマートフォンとの向き合い方を変えることで、子どもたちには必ず良い影響が現れます。
どうか、今日からその一歩を踏み出してみてください。
関連記事:スマートフォン制限の是非:フランスのデジタルブレイク実験を通して
【国内最多の登校支援実績】トーコについて
私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,000名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。
「2年間一度も学校に行けなかった」「両親に反抗して暴れていた」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。
それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。
無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。