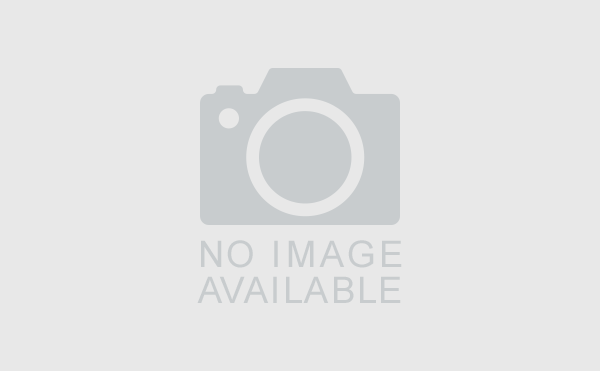GW明けに不登校が急増する理由と、家庭で出来る対策
こんにちは。不登校カウンセラーの竹宮です。
今日は「ゴールデンウィーク明けに不登校が急増する理由」と「家庭でできる対策」について書きたいと思います。
この時期になると、保護者の方からこんな声をよく聞きます。
「GWまでは頑張って登校していたのに、急に行けなくなってしまいました」
「休み明けが怖いと言っています。どう接したらいいかわかりません」
ゴールデンウィーク明けに不登校が増えるのは、実は珍しいことではありません。
けれど、それを単純に「怠け」や「甘え」と捉えてしまうと、お子さんの心に大きな負担をかけてしまいます。
今日は、よくある考え方に少し疑問を投げかけながら、家庭でできる現実的な工夫について考えてみたいと思います。
目次
- ゴールデンウィーク明けは「心の限界」が表れやすい
- では、家庭でできる現実的な工夫とは?
- 保護者自身も、心の余白を持つことが大切です
- 実際に役立つ、家庭での具体的なサポート
- 焦らず、遠回りを恐れない
- 最後に 〜親子で「柔らかくある」こと〜
ゴールデンウィーク明けは「心の限界」が表れやすい
まず、よく言われることとして、
「長い休みで生活リズムが崩れたから不登校になる」
という話を耳にすると思います。
たしかに、リズムの乱れも一因ではあります。
でも、私はこの説明だけでは少し足りないと感じています。
生活リズムが多少崩れても、楽しく学校生活を送れている子は、自然と戻っていけることが多いからです。
つまり、問題は「リズム」よりも「心の疲れ」のほうが大きい場合がある、ということです。
たとえば、最初は緊張しながらも新しいクラスや先生に馴染もうと頑張っていた子。
友達との関係を築こうと、一生懸命まわりに合わせていた子。
そういった努力は、表からは見えにくいけれど、実は相当なエネルギーを使っています。
ゴールデンウィークというひと休みを挟んで、その緊張の糸がぷつりと切れてしまう。
これが、休み明けに不登校が急増する大きな理由の一つだと考えています。
よくあるアドバイスとその問題点
ここで、よく言われるアドバイスに注目してみましょう。
「とにかく朝起きさせて学校に行かせなさい」
こうした言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
このアドバイスの背景には、「学校に戻ることが正しい」「まずは行動することが大事」という考え方があります。
たしかに、軽い抵抗感であれば、行動から気持ちが後からついてくることもあります。
しかしながら、心の疲弊が限界に達している子に対しては、この方法は逆効果になることが少なくありません。
無理やり登校させることで、心のエネルギーが完全に枯れてしまい、長期的な不登校に繋がることもあるからです。
具体例で言うと、風邪をひいて高熱が出ている子どもに、「気合いで学校行こう!」と言うようなものです。
もちろん、本人の状態を見ずに無理を強いるのは、よい結果にはなりません。
心の葛藤を抱える保護者の悩み
とはいえ、保護者の立場としては、
「このまま休ませたらずっと学校に行けなくなるのでは?」
という不安が湧くのも当然です。
子どもの将来を思えばこそ、心配になるのは自然なことです。
また、
「ここで甘やかしたらダメなのでは?」
という葛藤も、多くの方が抱えるところです。
このように、単純に「休ませるか」「行かせるか」だけの問題ではないことが、保護者をより苦しめています。
では、家庭でできる現実的な工夫とは?
その反面、私はこう考えています。
「無理に学校に行かせる」か「何もせずにただ休ませる」かの二択ではない、と。
家庭でできることは、もっと柔軟で、もっと子どもの気持ちに寄り添った形で用意できます。
たとえば、次のような対応が考えられます。
- 朝は起きるけれど、学校には行かない選択肢を認める
- 学校の話題を無理に振らず、普段通りの会話を心がける
- 「学校に行かないこと=悪いこと」というメッセージを無意識に送らない
- 少し元気が出た時にだけ、軽く外に出る機会を作る(散歩でも十分です)
こういった小さな工夫が、子どもの心に余裕を作り、回復への道筋をつくっていきます。
「休む勇気」も、子どもには必要です
ここで大事にしたい考え方は、
「休むことも一つの大切な力である」
という視点です。
大人でも、心が限界に達した時に「しっかり休む」という判断はとても難しいものです。
それを、小さな子どもが自分で感じ取り、休もうとしている。
これは、決して「甘え」ではありません。
例えるなら、走り続けたマラソンランナーが、自分の体調に異変を感じて立ち止まるようなものです。
その判断ができるのは、むしろ成長の証だと考えることもできます。

保護者自身も、心の余白を持つことが大切です
ここからは、保護者の方自身の心のケアについても触れていきたいと思います。
不登校になると、どうしても「子どもをなんとかしなきゃ」という気持ちが強くなります。
でも、それだけだと保護者の方自身が心のエネルギーを消耗してしまうのです。
たとえば、毎日「なんとか登校させよう」と試みてはうまくいかず、自己嫌悪に陥る。
あるいは、子どもの気持ちを考えすぎて、自分まで疲れ切ってしまう。
こういった状態は、よくあることです。
しかしながら、このような理由で保護者の方が限界に近づいてしまうと、結果的に親子で共倒れになってしまう危険もあります。
だからこそ、自分自身にも「少し休んでいい」と許可を出すことが、非常に大切です。
よくある誤解:「親が強くなれば子どもも強くなる」
世間ではよく、
「親が強くあれ」
と言われることがあります。
確かに、保護者の安定した姿は、子どもに安心感を与えることにつながります。
ですが、「強くならなきゃ」と自分を追い込むことは、違うのです。
本当に大切なのは、「強がること」ではありません。
「正直に疲れたと言えること」「時には頼ること」を大人自身が示してあげることです。
たとえば、
「ママもちょっと疲れちゃったから、今日は早めに寝るね」
と子どもに伝えるだけでも、子どもは「疲れたら休んでいいんだ」と学びます。
強さとは、無理をして固くなることではなく、柔らかく変化できることだと、私は思っています。
実際に役立つ、家庭での具体的なサポート
では、ここからはもう少し具体的に、家庭でできる対応について整理してみましょう。
1. 小さな「できた」を一緒に喜ぶ
学校に行けるかどうかに限らず、日常の中でできたことを一緒に喜びます。
たとえば、
- 朝起きられた
- ごはんを一緒に食べられた
- 外に一歩出られた
こんな小さな出来事でも、「できたね」と声をかけるだけで、子どもの自己肯定感は少しずつ回復していきます。
ここで注意したいのは、「すごいね!」と過剰に持ち上げないことです。
淡々と、自然に伝えることが大切です。
「今日は散歩行けたね。気持ちよかったね」
このくらいの温度感が、子どもにとって一番安心できるのです。
2. 不安を否定しない
子どもが「学校怖い」「行きたくない」と言ったとき、つい
「大丈夫だよ、頑張ればなんとかなる」
と言ってしまいたくなるかもしれません。
ですが、不安な気持ちを否定されると、子どもは「わかってもらえない」と感じてしまいます。
大事なのは、まずその不安を受け止めることです。
たとえば、
「怖いって感じるのは自然なことだよ」
「そんなふうに思うんだね」
と、受け止めるだけで十分です。
そのあとで、無理に励ます必要はありません。
子どもは、自分の気持ちを受け止めてもらえたと感じたとき、少しずつ安心していきます。
3. 日常生活のリズムを守る
学校に行かない日でも、できる範囲で生活リズムを整えることは役立ちます。
- 朝は一定の時間に起きる
- 朝ごはんを食べる
- 夜はなるべく同じ時間に寝る
これだけでも、子どもの心と体のバランスは安定しやすくなります。
「完璧にやらなきゃ」と思わず、「できる日はやる」「無理な日は休む」で十分です。
ここでもまた、柔軟さが鍵になります。
焦らず、遠回りを恐れない
不登校の回復は、「まっすぐ一直線」には進みません。
良くなったり、後退したりをくり返しながら、少しずつ前に進んでいきます。
たとえば、3日学校に行けたのに、また1週間休んでしまったり。
朝までは「行く」と言っていたのに、玄関で動けなくなったり。
そんな時、どうしても焦りや不安が押し寄せてきます。
でも、そこで無理に押し出すのではなく、
「今はまだ、準備の時期なんだ」
と考えてみてください。
植物が芽を出す前に、土の中でじっと根を張る時間があるように、目に見えない成長も確実に進んでいます。
最後に 〜親子で「柔らかくある」こと〜
ここまで読んでくださって、本当にありがとうございます。
ゴールデンウィーク明けの不登校は、親にとっても子にとっても、大きな試練です。
でも、試練だからこそ、今までとは違う「柔らかい関わり方」を考えるチャンスでもあります。
「無理に立たせる」よりも、「安心して休める」こと。
「正解を求める」よりも、「今ここにいる」こと。
そんな風に、親子で少しずつ柔らかくなれたら、きっと大丈夫です。
焦らず、比べず、責めず。
遠回りのように見える時間も、必ず子どもの力になります。
一緒に、ゆっくり進んでいきましょう。
【国内最多の登校支援実績】トーコについて
私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。
「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。
それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。
無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。