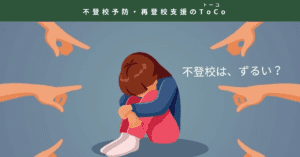不登校は子どもの甘え?
不登校や引きこもりの問題に取り組む児童心理司の竹宮と申します。また、私はToCo株式会社の顧問として、不登校が長期化する要因を解消し、子どもたちが再び学校に通えるようサポートするサービスに関わっています。本日は、「不登校は子どもの甘え?」というテーマについて、私の経験や知見をもとにお話ししたいと思います。
不登校を「甘え」と非難する声
不登校を経験するお子さんを持つ保護者の方々が、世間から心ない声を受けて心を痛めているという話を耳にすることは少なくありません。「学校に行かないなんて、甘えている」「少し厳しくした方がいいのでは」という意見を受けるたびに、親としての責任を問われているように感じ、苦しくなることもあるでしょう。こうした言葉は時に、家庭そのもののあり方や子どもとの関係性を否定するかのように響きます。
確かに、学校に行くことが社会でのルールのように捉えられる中で、そこから外れる行動をとるお子さんを「怠惰」や「甘え」と片付けてしまう声は根強いです。しかし、こうした声の背景には、不登校という現象に対する無理解があることが多いのです。不登校は単なる「サボり」や「わがまま」ではなく、子どもがさまざまな要因に押しつぶされそうになりながら出したSOSの形なのです。
私が相談を受ける中で感じるのは、学校生活が子どもにとっていかに大きな負荷になるかということです。人間関係、成績のプレッシャー、教師との相性、さらには日々繰り返される規律やルール。これらは、特に繊細で感受性の強い子どもたちにとっては耐え難いストレスになることがあります。そうした中で、子どもが学校に行けなくなるのは、単なる「甘え」ではなく、心身のバランスを守るための重要な自己防衛の手段であると言えるのです。
ではなぜ、「甘え」という言葉がこれほどまでに使われるのでしょうか。それは、世間が不登校という問題に対して持つ「厳しさ」が関係しているように思います。現代社会では「努力」や「競争」が重視される傾向があります。そのため、「学校に行かない」という行動が、あたかも「努力を放棄した」かのように見られがちです。ですが、適切な見方でしょうか?努力とは何か、成長とは何か、その意味を改めて問い直す必要があります。

ここで一つ、私が以前担当したケースをご紹介します。そのお子さんは、中学校1年生の時に突然不登校になりました。それまで元気に通学していた彼は、同級生の些細な言葉に傷つき、次第に学校に足を向けられなくなったのです。しかし、家族や周囲から「もう少し頑張れば」「逃げてはいけない」と言われるたびに、彼はさらに自分を追い詰めていきました。「頑張れ」という言葉が、逆にその子どもの心を蝕む結果となったのです。このようなケースを目の当たりにすると、社会が押し付ける「甘え」というレッテルがどれほど危険であるかを痛感せざるを得ません。
不登校になってしまう子どもは「甘え」なのか
不登校の子どもたちは本当に「甘え」なのでしょうか。私の答えは明確です。それは「違う」ということです。不登校になる子どもたちは、甘えているわけではなく、自分の中で何らかの困難や苦しみに直面し、それを乗り越える術を見つけられずにいるのです。
例えば、学校生活の中で繰り返される些細なトラブルやいじめは、大人から見れば取るに足らないことのように思えるかもしれません。しかし、子どもにとっては、それが世界のすべてを覆すほどの大きな問題に感じられることがあります。さらには、教師からの指導や親からの期待、友人関係のストレスなど、多くの要因が重なり合い、学校という場そのものが「安全ではない場所」に変わってしまうのです。
こうした状況に直面した子どもたちは、必死に自分を守るために行動します。それが学校を休むという形で現れるのです。これを「甘え」と呼ぶのはあまりにも酷です。むしろ、自分の心の声に耳を傾け、限界を超えないように自らを守ることができるという点で、その子たちは非常に賢明な選択をしていると言えます。
ここで理解しておきたいのは、不登校は一種の「警告サイン」であるということです。子どもたちは、自分自身では言葉にできない苦しみや不安を、その行動を通じて表現しているのです。親御さんがこのサインを見逃さず、適切に応じることが、子どもを救うための第一歩となります。
また、最近の研究では、不登校の背景に発達特性や感覚過敏、あるいは認知の特徴などが関与しているケースも多いことが分かっています。これらは決して「甘え」ではなく、子ども自身の特性であり、それに適したサポートが求められるものです。例えば、学校の騒がしさや、明確な指示がなく曖昧な場面が多い環境がストレスになる場合もあります。このような特性を理解しないまま、「甘え」と片付けることは、子どもの気持ちをさらに追い詰めるだけです。
親御さんが抱える葛藤も理解できます。「甘えを許していいのか」という不安や、「もっと頑張らせるべきなのではないか」という葛藤。しかし、これらの不安に向き合うことは決して簡単なことではありません。特に、世間の目や他の保護者との比較の中で悩むこともあるでしょう。それでも、子どもの心の声に耳を傾け、その苦しみを理解しようとする姿勢が、子どもにとって何よりも大きな救いとなるのです。
傷ついた時に甘えられないことのリスク
不登校の子どもを「甘え」と非難する声がある一方で、甘えを許されない環境に置かれた子どもたちがどのようなリスクを抱えるのかについて考える必要があります。甘えることができない状況、それは言い換えれば「助けを求めることができない環境」とも言えます。このような環境は、子どもたちにとってどれほど過酷なものなのでしょうか。
ある中学生の事例を挙げてみます。
彼女は小学校低学年の頃から家族に対して何も相談できなくなり、抱える問題をすべて一人で解決しようとしていました。テストで失敗した時も、友人関係で傷ついた時も、彼は親に助けを求めることをせず、「もっと頑張らなければならない」と自分を追い詰めました。しかし、努力すればするほど結果がついてこない状況に苛立ち、やがて自己評価を極端に低くするようになりました。そして最終的には学校にも行けなくなり、部屋に閉じこもるようになったのです。
このケースで重要なのは、「助けを求める」という基本的な行為が、この子にとってできないことになっていた点です。親としては「何かあれば言ってほしい」と思っていたかもしれません。しかし、子どもにとってそれが叶わない理由があったのです。それは、「自分が弱さを見せることで、親を失望させてしまうのではないか」という恐れでした。
甘えられない環境にいる子どもは、自分の弱さを隠し、表面的には何事もないように振る舞います。そのため、一見すると親は「何の問題もない」と思い込んでしまうことがあります。しかし、内面では絶えず孤独や不安、自己否定といった感情を抱えていることが多いのです。その結果、子どもの精神的なエネルギーは次第に枯渇し、自律神経のバランスを崩したり、うつ病のような症状に発展することも珍しくありません。
ここで考えたいのは、「甘え」とは本来どのような行為であるかという点です。甘えるという行動は、実は人間が持つ自然な自己防衛反応であり、困難に直面した際に誰かに助けを求め、状況を乗り越えるための重要な手段です。幼少期には親に対して甘えることが基盤となりますが、その基盤がしっかりと育まれることで、将来的には友人や同僚、パートナーといった他者に対しても適切に頼ることができるようになります。
甘える力は、子どもにとって成長のために欠かせない力です。それを奪われた環境にいる子どもは、周囲とのつながりを感じられず、自分一人で問題を抱え込むようになります。そして、何よりも危険なのは、「助けを求めても無駄だ」という学習をしてしまうことです。この学びは、人生のあらゆる場面で子どもを苦しめる大きな要因となります。
親御さんにとって、「甘え」をどのように受け止めるかは非常に難しい課題です。「甘えさせすぎてはいけない」という思いが強くなると、子どもが本当に助けを必要としているタイミングを見逃してしまうことがあります。逆に、適度な甘えを許し、子どもが心を開いて頼れる環境を作ることで、子ども自身が安心感を得られるだけでなく、親子の信頼関係もより深まるのです。
子どもの将来を思った「甘やかし」にするために
では、「甘えの容認」と「甘やかし」の違いについて、親としてどのように向き合えばよいのでしょうか。不登校を経験する子どもに対して、「甘え」を許す姿勢が必要だと述べましたが、それが過剰な「甘やかし」につながるのではないかと不安に思われる方もいるでしょう。この章では、「甘え」を子どもの将来にとって有益なものにする方法について考えます。
まず最初に、「甘やかし」とは何かを整理しましょう。甘やかしとは、子どもの要求に無条件で応じ続けることで、子どもが自分で考えたり努力したりする機会を奪ってしまう行為です。これに対して、「甘え」を受け入れることは、子どもが困難に直面した時に適切に手を差し伸べ、必要なサポートを提供することです。この違いは非常に重要です。
たとえば、不登校の子どもが「学校に行きたくない」と言った時、その言葉の背後にどのような感情や状況があるのかを親が理解しようとすることが「甘え」を受け入れる姿勢です。一方で、子どもの「学校に行きたくない」という言葉をそのまま受け止め、何の対策も取らずにその状態を放置してしまうことは、「甘やかし」に近い行動と言えます。
ここで、親ができることは、「子どもの気持ちに寄り添いながらも、再び前を向けるようなサポートを提供する」ことです。そのためには、まず子どもの話をしっかりと聞くことが大切です。親御さんが「学校に行かなければならない」と焦る気持ちをぐっと抑え、子どもが今抱えている悩みや苦しみを丁寧に聞き取ることで、子どもは「自分を受け入れてもらえた」という安心感を持つことができます。
また、親が子どもを支える際には、小さな目標を一緒に立てることが効果的です。たとえば、「学校に行くこと」をゴールにするのではなく、「朝、制服に着替えること」「リビングに出てくること」といった、子どもが無理なく達成できる小さなステップを積み重ねていくのです。このプロセスを通じて、子どもは少しずつ自信を取り戻し、自分の力で困難を乗り越えられる感覚を身につけることができます。
| 項目 | 甘えへの適切な対応 | 甘やかし |
|---|---|---|
| 基本的な姿勢 | 子どもの気持ちや困難を受け止め、共感しながら解決へのサポートを行う。 | 子どもの全ての要求に無条件で応じ、問題解決の責任をすべて親が負担してしまう。 |
| 目標 | 子どもが自分の力で課題を乗り越えられるようになることを目指す。 | 子どもが快適さだけを求める習慣を強化し、自分で考える力や責任感を育てない。 |
| 子どもへの接し方 | 子どもの不安や苦しみに耳を傾け、適度な支援を提供する。「一緒に考える」姿勢を重視する。 | 子どもの言い分を全面的に受け入れ、必要以上に手を貸すことで、子どもを依存的にさせる。 |
| 境界線 | サポートの範囲を明確にし、親としてのルールや価値観を示す。 | 境界線を設けず、子どもの要求に従いすぎて家庭内の秩序が崩れる。 |
| 例1: 不登校の場合 | 子どもの学校に行きたくない理由を丁寧に聞き取り、「今日1時間だけ教室に入ってみる」など小さな目標を一緒に設定する。 | 「学校に行きたくないなら行かなくていい」と、そのまま放置するか、過剰に擁護して学校側への不満を子ども以上に主張する。 |
| 例2: 勉強の課題 | 勉強ができない理由を探り、「苦手な部分だけ一緒にやろう」と具体的な手助けを提案し、自信を育てる。 | 勉強を完全に代わりにやってしまったり、課題をなかったことにする。 |
| 親の心の持ち方 | 子どもが困難を乗り越える力を信じ、「見守りつつ支える」というバランスを意識する。 | 子どもに嫌われることを恐れたり、子どもが失敗することを避けるために過剰に干渉する。 |
| 子どもの成長への影響 | 子どもが安心して親に頼ることができる一方、自分で課題を解決する力を育てられる。 | 自分で努力する力が育たず、失敗や困難を回避し続けることで、長期的な成長を妨げる。 |
さらに、親御さん自身もサポートを受けることを検討してください。不登校という問題は、家庭全体に影響を及ぼします。親が孤立したり、自分だけで解決しようと抱え込むと、かえって状況を悪化させることがあります。信頼できる専門家やサービスを活用し、親御さん自身も安心できる場を見つけることが重要です。
ToCo株式会社が提供するサービスもその一つです。私たちは、親御さんとお子さんが共に不登校という状況を乗り越えるためのサポートを提供しています。子どもが抱える具体的な課題に合わせたアプローチを提案し、家庭と学校の橋渡し役として機能することを目指しています。
「甘え」を許す社会を目指したい
不登校を「甘え」と見なす社会的な風潮は、親御さんや子どもたちを苦しめる大きな要因です。しかし、私たち一人ひとりがその捉え方を変え、子どもの「甘え」を自然な感情として受け止めることができれば、不登校に対する理解は大きく進むでしょう。
「甘えを許す社会」とは、助けを求める行為を恥ずかしいことだと思わず、むしろ称賛すべき行動と捉える社会です。子どもが学校生活に困難を感じた時、それを率直に表現できる環境があれば、深刻な不登校に発展する前に解決策を見つけることができるかもしれません。
親御さんもまた、この新しい価値観を受け入れることで、お子さんに対して柔軟で優しい対応ができるようになるでしょう。
【国内最多の登校支援実績】トーコについて
私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。
「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。
それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。
無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。