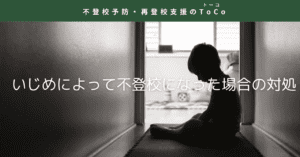不登校になりかけの時に親がすべき3つの行動とは?
目次
児童心理カウンセラーの藤原と申します。これまでに、不登校や引きこもりなどの課題を抱えた親子と長年向き合ってきました。現場で痛感するのは、「不登校は突然起きるものではない」ということです。
実際に多くの子どもたちは、不登校に至るまでに、いくつもの小さなサインを出しています。ですが、親はその変化に気づけず、気づいたときには長期化の兆しが出ている、というケースが非常に多いのです。
子どもの“不登校”を防ぐために一番大切なのは、早い段階で「何かおかしい」と気づき、冷静に対応する力です。今回の前編では、不登校の初期サインや親が最初にとるべき対応、そして「やってはいけない行動」について、具体例を交えてお伝えします。
参考データ
文部科学省【不登校児童生徒への支援の在り方について】
不登校児童生徒による学校以外の場での学習等に対する支援
「不登校は突然始まる」は誤解。小さな変化を見逃さない
不登校の多くは、ある日突然「行きたくない」と言い出すのではなく、その前に“兆候”が現れています。たとえばこんな行動が見られたら、要注意です。
- 朝、布団から出られず、身支度にも時間がかかるようになる
- 「頭が痛い」「お腹が痛い」など、身体症状の訴えが頻繁になる
- 学校や友達の話を避ける
- ゲームやスマホに使う時間が増え、依存気味になる
- 遅刻や欠席が徐々に増えていく
これらは一つひとつだけなら「ただの気まぐれ」「成長期の一時的なもの」と見逃してしまいがちです。ですが、複数が重なって出てきたときは、子どもの心がストレスを抱えているサインかもしれません。
特に注意したいのが、“身体の不調”です。大人のように言葉でうまく不安や緊張を説明できない子どもは、無意識のうちに体の不調としてそのストレスを表現します。「また仮病?」と決めつけず、「最近、体調が安定しないね。疲れてるのかな」と、心配する気持ちで受け止めてください。
叱るより、理解する姿勢。まずは「なぜ?」を手放す
子どもが学校に行きたがらないとき、親がまずしてしまうのが「なんで?」「何が嫌なの?」という問いかけです。ですが、実際には、子ども自身も理由が分からないことがよくあります。
不登校の背景には、友人関係のトラブル、先生との摩擦、授業についていけない不安、学校という環境自体への抵抗感など、複雑な要素が絡み合っています。そして、それらは多くの場合、言葉になりにくい感覚や気持ちと結びついています。
そのため、問い詰めるような接し方をすると、子どもは「責められている」と感じ、心を閉ざしてしまいます。
代わりに、「最近、朝つらそうだけど、何かあった?」「無理して学校行かなくていいから、今日はゆっくり話そうか」と、子どもの感情に寄り添う言葉をかけてください。
「甘やかし」と「受け止め」は違う。冷静に、愛情を持って接する
子どもが不安定な状態にあるとき、親の対応は“感情のバランス”が問われます。「休ませてあげよう」と思いながらも、「このままじゃいけない」という焦りが出て、つい叱ったり、強引に学校へ行かせようとしたりしてしまう。
でも、そこで大事なのは、親自身が冷静でいることです。親の不安や焦りは、子どもにすぐ伝わります。すると、子どもは「自分のせいで親が困っている」と感じて、さらにプレッシャーを感じることになります。
どうしても不安なときは、親自身も誰かに相談してください。学校のスクールカウンセラーや、地域の教育相談窓口を利用するのも一つの手段です。
「どうして不登校になったのか」は、親として気になるところです。でも、原因探しにばかり時間をかけるより、今の子どもの状態をよく観察し、必要な環境を整えることが何よりも優先されるべきです。
たとえば、今の生活リズムはどうか。家庭で安心して過ごせているか。ゲームやスマホばかりになっていないか。生活全体を見直すことで、「今できること」が少しずつ見えてきます。談するなど、他のリソースを活用することも視野に入れてください。
また、子どもが「お腹が痛い」「気分が悪い」と言ったとき、必要に応じて医療機関を受診することも有効です。「本当にどこか悪いのか」だけでなく、親が冷静になるための確認にもなります。
医師に「体には異常がありません」と言われるだけで、「この不調は心の問題かもしれない」と親が自覚しやすくなり、焦らず対応できるようになる場合もあります。
親が実際に取るべき行動3点
ここから、不登校の兆しを感じたときに「親が実際に取るべき行動」を3つに絞ってお伝えします。
どれも特別な知識や技術は必要ありません。家庭の中で、今日からできることばかりです。親の声かけ一つ、行動一つが、子どもの“安心の土台”になります。
行動1. 「学校とつながり続ける」〜対立ではなく協力を〜
子どもが学校を休み始めたとき、多くの親御さんが悩むのが「学校にどこまで関わればいいのか」という点です。先生に事情を話していいのか、担任と連絡を取るべきか、悩みますよね。
でも、子どもが休んでいる時期だからこそ、親と学校が“協力関係”を築いておくことが大切です。
子どもが登校できない間も、学校との関係性が切れてしまうと、子どもにとっても「戻る場所ではなくなる」可能性があるからです。
たとえば、こんな関わり方があります。
- 担任の先生に現状を正直に伝え、「焦らず見守っている」ことを共有する
- 学校からのお知らせや配布物を取りに行き、子どもに「学校とのつながり」を見せる
- 子どもが嫌がらなければ、担任から手紙やメッセージをもらうようお願いする
- 保健室登校や別室対応など、柔軟な登校方法の選択肢を相談する
ただし、ポイントは「学校にすべてを委ねない」ことです。学校側にも対応できる範囲がありますし、先生によって理解度や関わり方もまちまちです。「相談はするけれど、主導権は親がもつ」意識が大切です。

行動2. 家庭での「過ごし方」を見直す
不登校が長引く一因として、家庭が「居心地の良い場所」になりすぎている場合があります。親が子どもを心配するあまり、過保護になったり、子どもの言い分を全て受け入れたりすることで、家庭が過度に快適な空間になってしまうと、子どもは学校に戻る必要性を感じにくくなります。
たとえば、子どもが学校を休んでいる間に好きなだけゲームをしたり、スマホで友達と連絡を取ったりすることを許していませんか?これでは、「学校に行かなくても楽しい」と感じてしまい、結果的に不登校の状態を助長してしまう可能性があります。
親としては、家庭でのルールを見直し、一定の緊張感を持たせることが重要です。具体的には、以下のような取り組みを試してみてください。
- 平日の昼間はゲームやスマホを制限する
- 朝は必ず決まった時間に起きるよう促す
- 日中はできる限り机に向かい、学習や創作活動に時間を使わせる
- 家事の一部を手伝ってもらうなど、家庭内での役割を持たせる
これらの取り組みを通じて、子どもが「家での時間もそれなりに責任が伴う」という感覚を持つようになります。ただし、これらを実行する際には、決して感情的にならず、愛情を持った態度で接することが大切です。叱責や批判は、子どもをさらに追い詰めるだけで逆効果です。
また、親自身が「学校に戻ることが全てではない」という柔軟な考えを持つことも重要です。不登校は、時には子どもが自分のペースで成長するための時間でもあります。焦らずに見守りながら、少しずつ前進することを目指してください。
行動3. 子どもと向き合う姿勢を整える
不登校になりかけている子どもに対して、親が最も重要視すべきなのは「共感」と「信頼」です。子どもは、親のちょっとした態度や言葉から、自分が責められているかどうかを敏感に感じ取ります。そのため、「なぜ学校に行かないのか」「どうして頑張れないのか」といった言葉は、できるだけ避けるようにしましょう。
代わりに、「学校に行けない今の気持ちを教えてくれる?」といった共感的な言葉を使うことで、子どもが少しずつ自分の気持ちを親に打ち明けやすくなります。親が子どもの話を否定せずに受け入れることで、子どもは「親は自分の味方である」と感じ、不登校という状況から抜け出すための第一歩を踏み出しやすくなります。
また、親自身が冷静であることも大切です。不登校の問題に直面すると、親も焦りや不安を抱えやすくなります。しかし、親が感情的になると、子どもにもその不安が伝わり、状況がさらに悪化する可能性があります。親が心の余裕を持ち、冷静に対応することで、子どもにとっての安心感が生まれます。
子どもにとっての「安全基地」としての役割を果たしながら、必要なときには毅然とした態度で接する。これが、不登校を防ぐための親としての重要な心構えです。
最後に
不登校になりかけの時期に、親ができることは数多くあります。冷静に兆候を見極め、学校と建設的に連携し、家庭での生活習慣を整えることで、子どもが少しずつ学校に戻る準備を整えることができます。そして何よりも大切なのは、親が子どもの最大の理解者であり、応援者であることを示すことです。
【国内最多の登校支援実績】トーコについて
私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。
「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。
それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。
無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。