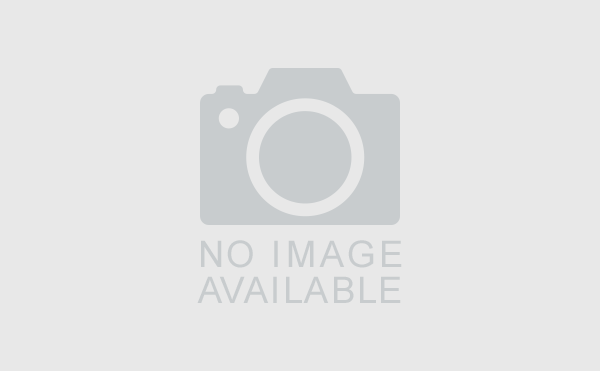母親/父親だけで不登校の子どもを支援することについて
こんにちは。不登校カウンセラーの竹宮です。
今日は「お母さん(またはお父さん)だけで不登校のお子さんを支えること」について書きたいと思います。
目次
よく「家庭の中で協力体制が整っていないと再登校は難しい」といった声を耳にします。たしかに理想を言えば、家族みんなが一丸となってサポートするのが望ましいです。でも、現実にはそういかないご家庭も多いのではないでしょうか。
たとえば、お父さんが子どもとの関わりに消極的だったり、逆に厳しく接してしまうことがある。あるいは、仕事で忙しく、家にいても「自分の時間」に徹してしまうタイプだったりもします。
そうなると、「私だけで何とかしないといけない」とお母さんが抱え込んでしまうことがあります。そして、その責任感の強さが、逆にご自身を追い詰めてしまう。こうした状況、実はとてもよくあるものです。
「家族全体で協力を」は正論だけれど
不登校支援に関する本やネット記事では、よく「家庭での協力体制づくりが大切」と書かれています。お父さんとお母さんが足並みを揃えて子どもに関わることが、安心感につながる——それ自体は間違っていません。
ただ、この言葉がプレッシャーになってしまうこともあります。
「うちは協力なんてできない」 「夫に話しても、そもそも理解してもらえない」
そんなふうに感じる方にとって、「協力体制を作りましょう」は、理想論に聞こえるのではないでしょうか。
その結果、協力できない自分たちの家庭に問題があるのでは、と余計に自信を失ってしまう。これは、本来前に進むためのアドバイスが、ブレーキになってしまっている状態です。
一人で向き合う現実と、そこにある力
実際、私のもとに相談に来る方の中にも、「夫は非協力的だから、自分一人でやるしかない」とおっしゃる方は多くいらっしゃいます。
ですが、そういったご家庭でも、お子さんが少しずつ元気を取り戻し、再登校につながったケースはたくさんあります。
大切なのは、「一人で全部を完璧にやろうとしないこと」だと思っています。
サポートの主軸を担うお母さんが、自分自身の負担に気づかず、無理をしすぎてしまうと、結果的に家の中の空気がギスギスしてしまうことがあります。子どもはとても敏感なので、その空気をすぐに察知します。
むしろ、完璧を目指すよりも、今できる範囲で「安心できる空間」を少しずつ作っていく。たとえば、朝「おはよう」と声をかける。好きなご飯を用意する。何も言わずにそっとしておく——そういう小さな積み重ねの方が、ずっと大きな支えになります。
子どもにとって「一人の安心できる大人」がいることの意味
不登校のお子さんにとって、「安心できる大人」がひとりでもいるということは、それだけで大きな支えになります。
たとえば、学校に行けない日が続く中で、「今日も家にいていいんだ」と思える空気があること。「無理に登校を促されない」という安心感があること。これだけで、子どもの心の緊張は少しずつほぐれていきます。
ここでポイントになるのが、「安心感」と「放任」は違うということです。
「安心感」は、子どもが受け入れられていると感じる状態です。「あなたはあなたのままで大丈夫」と伝えることです。
一方で「放任」は、関心を持たれない、ケアされないと感じる状態です。「どうでもいいと思われてるのかな」と子どもが感じてしまうこともあります。
これは、言葉だけでなく、表情や態度、空気感に出るものです。
だからこそ、お母さんが一人で関わる場合でも、「見守ってるよ」「気にしてるよ」「気にかけてるよ」というメッセージが、少しずつでも伝わるように意識してみてください。

少しずつ巻き込んでいく、という視点
では、家族の中で「今は自分しか動けない」状況の中から、どうやって少しずつお父さんを巻き込んでいくのか。この部分に悩まれる方も多いと思います。
まず大前提として、「いきなり理解してもらおうとしない」ことです。
人は、自分に関係があると感じられない話にはなかなか関心を持てません。たとえば、「子どもが不登校になっていて」「繊細な声かけが大事で」「今日の様子はこうだった」などと、一気に状況説明を始めても、聞く側には入りづらいことがあります。
これは、理解力や愛情の問題ではなく、「情報の量」と「タイミング」の問題です。
ですので、最初はほんの小さなことからで構いません。
たとえば、 「今日、○○(子どもの名前)、久しぶりに自分からお皿を運んでくれてね」 「夕方、ちょっとだけリビングに出てきたのよ」 というような、ごく短いエピソードを、何気なく共有してみてください。
これには、「状況を共有する」という目的だけでなく、「あなたにも関係ある話なんですよ」と、さりげなく伝える意味があります。
一度で響かなくても大丈夫です。こういうやり取りを繰り返す中で、少しずつ「子どもの今」が身近に感じられてきます。
そして、これが大切なのですが……人は「頼られると、役割を感じる」ものです。
「ちょっと声だけでもかけてもらえると嬉しいんだけど」 「夜、一緒にテレビ見てると子どもが安心するみたい」 など、負担にならない範囲でお願いをしてみるのも、一つの方法です。
反応が薄くても、それは「嫌だ」というより「どう関わったらいいかわからない」だけかもしれません。
だからこそ、急がず、焦らず、できるだけ短く、具体的に。「これをしてほしい」というより「これ、助かるんだけど」という伝え方のほうが、すっと心に入りやすいです。
「お父さんなりの関わり方」がある
一つ注意したいのは、「お母さんと同じように関わってもらおうとしない」ことです。
お母さんが感情を受け止めたり、様子を丁寧に観察したりするタイプであればあるほど、お父さんのシンプルな反応や無言の姿勢に対して「それじゃ伝わらない」と感じてしまうことがあります。
ですが、お父さんなりの関わり方というのも、ちゃんとあります。
たとえば、特別な会話がなくても、決まった時間に家に帰る。子どもが話しかけてきたら、素っ気ないようでいてちゃんと受け答えする。それだけでも、子どもは「あ、見てもらってる」と感じることがあります。
「なにかしてもらう」より、「存在としてそこにいること」が安心になることもあるのです。
その意味でも、無理にお父さんを変えようとするより、「今のスタイルでできること」を見つけていく方が、結果的にうまくいくことが多いです。
「一人でやる」ことの価値を、見失わないで
ここまで「巻き込む工夫」について書いてきましたが、最後にひとつ強調したいことがあります。
それは、「一人で子どもを支えている今のあなた自身には、大きな価値がある」ということです。
たしかに、時に孤独で、不安で、出口が見えない日もあるかもしれません。でも、お子さんにとっては、今そばにいてくれるあなたが、世界の中で一番の安心なのです。
このことは、誰かに評価されるものではありませんが、確かに存在する力です。
ですから、自分を責めないでください。
そして、支え方を少しずつ工夫しながら、できるタイミングで周囲を巻き込んでいく。そのプロセス自体が、親子にとって大切な時間になります。
目指す先が「再登校」であっても、そこに至るまでの道のりに、たくさんの意味があります。
今日の文章が、そんな道のりを歩く中で、少しでも気持ちを軽くできたなら嬉しく思います。
【国内最多の登校支援実績】トーコについて
私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。
「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。
それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。
無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。