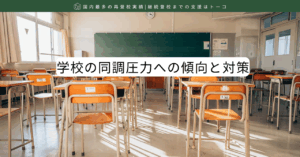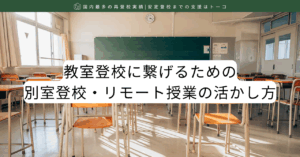新学期の登校を支えるために親が出来ること
こんにちは。カウンセラーの竹宮と申します。
新学期を迎える時期になると、多くのご家庭で「子どもがちゃんと学校に行けるのか」という心配が生まれます。特に不登校や長期欠席の経験があるお子さんを持つ保護者の方にとっては、胸の奥に重たい不安を抱える時期でもあると思います。
今日は「新学期の登校を支えるために、親ができる現実的な関わり方」についてお話ししたいと思います。よく耳にするアドバイスの一歩先を見据えて、心理的な視点から整理していきます。
目次
- 「頑張れば行けるはず」という考え方の落とし穴
- 不安を「先取り」して小さくする
- クラスメイトの視線への不安
- 勉強よりも登校を優先するという考え方
- 親の不安と子どもの不安はリンクする
- 「完璧な登校」を求めないこと
- 子どもの自己評価を高める声かけ
- 「他の子と比べない」という難しさ
- 現実的なハードルを一緒に整える
- 精神論ではなく、具体的な積み重ねを進める
- 関連記事
「頑張れば行けるはず」という考え方の落とし穴
よく耳にする言葉の一つに「最初が肝心だから、とにかく行かせましょう」というものがあります。
一見すると正しいように思えます。確かに新学期の初日に出席できれば、その後の流れもスムーズになる可能性があります。学校生活というのは、習慣性に大きく依存するからです。
しかしながら、心理学的に見ると「頑張って行かせる」というアプローチは高いリスクを伴います。なぜなら、緊張や不安が強い状態の子どもに無理をさせると、登校そのものが「恐怖の体験」として記憶されやすいからです。これはトラウマ的な記憶形成の仕組みで、無理な成功体験は必ずしも自信につながらないのです。
例えば、泳げない子どもをいきなり深いプールに突き落とすようなものです。確かに一度は浮かび上がるかもしれませんが、「また落とされるかもしれない」という恐怖心が強く残り、結果的に水嫌いが強まることがあります。
このように、「初日だからとにかく行かせよう」という考えは、親として理解しやすい一方で、子どもの心理に逆効果をもたらす場合があります。
不安を「先取り」して小さくする
そこで有効になるのが「不安の先取り」です。これは、事前にシミュレーションをすることで、未知の不安を少しでも小さくする方法です。心理学では「エクスポージャー(段階的曝露)」と呼ばれる技法の考え方です。言い換えると、怖さを分割して体験しておく、ということです。
具体的には、お子さんと一緒に「登校初日の流れ」を頭の中でたどってみます。
切り出すときは、あえて柔らかい雰囲気を意識してください。
例えば、夕食の後にリビングでくつろいでいるとき、自然な会話の中でこう言います。
「学校も緊張することあると思うから、ちょっと一緒に考えてみようか」
このように「一緒に」という言葉を添えることで、プレッシャーではなく協力的な空気が作れます。
やり方は簡単です。椅子に並んで座り、目を閉じてもらいます。
そして、こんなふうに声をかけてください。
- 「家を出て、通学路を歩いているところを想像してみよう。どんな気持ちになりそう?」
- 「校門を通って、学校に入るときはどうかな」
- 「教室に入った瞬間は、どんな気持ちになりそう?」
この過程で、おそらくいくつかの「不安ポイント」が出てくるはずです。
「教室に入るときが嫌だ」とか「校門を通るのがしんどい」という具合です。
そのときは、すぐに解決策を押し付けるのではなく、まず認めてあげることが大切です。
「そうだよね。緊張するよね」と、一言添えてください。
そのうえで、「じゃあどうすれば少し楽になるかな」と相談します。
例えば、親が校門まで付き添う、先生に連絡をして教室の前で一言声を交わしてもらう、など現実的な工夫が出てくるはずです。
これは単に登校をシミュレーションするだけではなく、「親と一緒に考えた」という安心感を子どもに与えます。親の伴走感覚が、不安を和らげる効果を持つのです。
クラスメイトの視線への不安
久しぶりに登校するお子さんが最も気にするのは「勉強の遅れ」よりも「友達の視線」です。心理的にいうと、子どもは認知的評価(自分がどう見られるか)に非常に敏感だからです。
よくある心配は「何で来なかったの」と聞かれるのではないか、あるいは「変に思われるのではないか」というものです。これは大人が職場に長期欠勤した後、同僚の前に戻るときの不安と似ています。
そこで有効なのが「視点の変換」です。つまり、子ども自身を「見る側」に立たせてみることです。
例えば、こんなふうに問いかけてみてください。
「もしあなたが教室にいて、久しぶりに来た友達を見たらどう思う?」
子どもはしばらく考えて、こう答えるかもしれません。
「来てくれてよかったと思う」
あるいは「別に何とも思わない」
その答えを受け止めてから、次につなげます。
「そうだよね。みんなも同じ気持ちなんだよ。『来てくれてよかった』って思うだけで、『なんで来たの?』とは思わないんだよ」
このやり取りによって、子どもは「自分だけが見られている」という認知の偏りを修正することができます。心理学的には「認知の再構成」と呼ばれる方法で、不安を現実的に捉え直す効果があります。
勉強よりも登校を優先するという考え方
もう一つ大きなテーマが「勉強の遅れ」です。
長く休んでいた子どもにとって、宿題が溜まっている状況は大きな負担です。保護者の方も「こんなに遅れていたら行けないのでは」と焦る気持ちを抱えがちです。
しかし、学校側の立場に立ってみると、多くの先生は「宿題も大事だが、まずは登校してくれることが一番大事」と考えています。私が学校現場で関わってきた経験でも、この意見は一貫しています。
理由はシンプルです。勉強は後から取り戻すことが可能ですが、登校習慣が途切れると回復に大きな時間がかかるからです。つまり、優先順位は「登校」→「学習」という順になります。
そのため、宿題に手を付けられていない場合には、先生と事前に相談して「とりあえず登校を目標にする」と共有しておくことが重要です。そうすることで、子どもも「勉強を全部やらないと行けない」というプレッシャーから解放されます。
この切り替えが、登校再開の大きな一歩になります。
親の不安と子どもの不安はリンクする
ここで忘れてはいけないのは、親の不安と子どもの不安は強く影響し合うという点です。心理学では「情動伝染」と呼ばれる現象があります。簡単に言えば、親が焦っていると子どもも無意識に緊張を感じ取るということです。
例えば、朝の支度のときに親が時計を何度も見ながら「早くしないと」と声を荒げると、子どもは登校準備そのものを「嫌な体験」として結びつけてしまいます。反対に、親が落ち着いて「今日はまず靴下を履こうか」と穏やかに声をかければ、子どもは不安を吸収しにくくなります。
つまり、親自身が安心できる状態をつくることが、子どもにとって最大のサポートになるのです。もちろん、保護者の方が心配になるのは当然です。しかし、その心配を子どもに直接見せてしまうと逆効果になります。
「心の中で不安を抱えながらも、表情は落ち着いて見せる」
この小さな工夫が、大きな支えにつながります。
「完璧な登校」を求めないこと
もう一つ強調しておきたいのは、「完璧な登校」を求めすぎないことです。
よくある誤解に、「初日から最後まで普通に過ごせなければ意味がない」という考え方があります。しかし、心理的な回復は段階的に進むものです。
たとえば、初日は午前中だけ出席できれば十分です。翌日は1時間だけ教室にいられたら、それも立派な前進です。子どもにとって「途中で帰っても大丈夫」という安心感があることで、最初の一歩を踏み出しやすくなります。
この考え方は、大人の生活習慣にも当てはめられます。運動不足を解消しようと思っても、いきなりフルマラソンを走る人はいません。最初は散歩から始めるように、登校も「小さな成功体験」を積み重ねていくのが現実的なのです。
子どもの自己評価を高める声かけ
登校に成功した日の夜は、ぜひ子どもと一緒にその一日を振り返ってください。
ただし、「よく頑張ったね」だけでは不十分です。
子どもは褒められると一瞬は嬉しくても、「本当に自分の力だったのかな」と疑問を抱くことがあります。そのため、具体的な行動に焦点を当てることが大切です。
例えば、このような言い方です。
「今日は教室に入るときに、一歩足を踏み出したのがすごく勇気を出せたね」
「先生と目を合わせて挨拶できたのがよかったよ」
このように行動を具体的に言葉にすることで、子どもは「できた自分」を実感できます。心理学では「内発的動機づけ」を強める効果があると言われています。つまり、外からの評価に依存せず、自分の中から「やってよかった」という感覚を持てるようになるのです。
「他の子と比べない」という難しさ
保護者の方からよく聞かれるのが「どうしてうちの子だけ」という気持ちです。クラスメイトが普通に学校へ通っているのを見ると、自然と比べてしまうのは当然のことです。
しかしながら、比較は親の焦燥感を強め、結果的に子どもへのプレッシャーになります。心理学的にも「社会的比較」は自己効力感を低下させやすいことが分かっています。
とはいえ、「比べないようにしよう」と思っても、心の中で浮かんでしまうのが人間です。大切なのは、その気持ちを否定しないことです。「そう思ってしまうのは仕方ない」と認めるだけで、気持ちは少し軽くなります。
そして、「他の子と比べるより、昨日のわが子と比べる」という視点を意識してください。昨日より一歩前に進んでいれば、それが最大の成果です。
現実的なハードルを一緒に整える
ここまで心理的な工夫をお話ししてきましたが、実際には物理的なハードルも存在します。例えば、朝の準備がスムーズにいかない、登校のタイミングで親が仕事に行かなければならない、兄弟姉妹の予定が重なる、などです。
こうした現実的な問題は、心理的な不安と結びつきやすく、「やっぱり無理だ」という気持ちを強めます。ですから、心理的な準備と同時に、生活リズムや家庭内の動線も整えることが重要です。
例えば、前日の夜にランドセルを玄関に置いておく、朝食を簡単にできるものにしておく、出発時間を10分前倒しにして余裕をつくる。小さな工夫の積み重ねが、登校へのハードルを下げていきます。
精神論ではなく、具体的な積み重ねを進める
新学期の登校は、子どもにとっても親にとっても大きな挑戦です。
「とにかく行かせなければ」と考えると焦りが増し、「勉強が遅れているから無理だ」と感じると不安が膨らみます。
しかし、心理的なアプローチを取り入れることで、状況は大きく変わります。
- 不安を先取りしてシミュレーションすること。
- クラスメイトの視線を「見る側」の立場で考えてみること。
- 勉強よりもまず登校を優先すること。
- 親の落ち着きが子どもの安心につながること。
これらを意識すれば、「登校」というハードルは分割され、子どもにとって現実的な一歩になります。
最終的に大切なのは「完全な解決」ではありません。
むしろ、「一歩ずつ進めばいい」という柔らかい視点を持つことです。
お子さんと一緒に歩む時間は、焦りや不安の中でも確実に意味を持ちます。親ができることは、その歩みを認め、伴走すること。そこから新しい学期が始まっていきます。
関連記事
【国内最多の登校支援実績】トーコについて
私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。
「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。
それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。
無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。