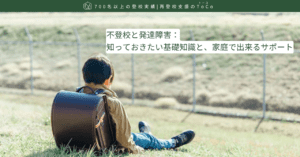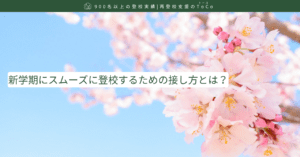学校に不登校を相談する前の準備とは?
不登校や引きこもりの問題に取り組む児童心理司の成田と申します。私は不登校予防や再登校支援を行うToCo株式会社の顧問として、多くの子どもたちと保護者の方々に関わってきました。不登校の問題は、家庭だけでなく学校との関係性が大きな鍵を握っています。
しかし、保護者の方々の中には、「学校とどう連携すればいいのか分からない」「学校に相談しても状況が変わらない」と感じている方も少なくありません。今回は「不登校の子のために親が知っておくべき学校との連携」というテーマで、具体的なポイントをお伝えします。
目次
- 第1章 不登校の背景を学校と共有する重要性とは?
- 第2章 学校との連携がうまくいかない時の原因とは?
- 第3章 再登校に向けた学校との具体的な連携ステップ
- 第4章 学校との連携を長期的に維持するポイント
- 第5章 子どもと学校との「信頼関係」を築くための支援とは?
- まとめ:親と学校の「協働」が子どもの継続登校を支える
第1章 不登校の背景を学校と共有する重要性とは?
不登校の背景には、子ども自身の心理的負担や学校内での人間関係、学業のつまずきなど、さまざまな要因が絡み合っています。しかし、その要因が学校側に十分に伝わっていない場合、適切な支援が行われず、状況が長期化してしまうことがあります。学校と保護者が正確な情報を共有し、現状を共通理解することが、再登校への第一歩です。
1.1 学校は「子どもの現状」を正確に把握できているか
学校側は、子どもが登校していない間の様子を把握することが難しい状況にあります。特に長期間の不登校の場合、担任や学年主任が「子どもが今、どのような状態なのか」「何を不安に感じているのか」を把握していないケースが多いです。そのため、保護者が学校に対して、子どもの状況を具体的かつ継続的に伝えることが求められます。
例えば、以下の情報は学校との共有が重要です。
- 子どもが不安に感じていること(友人関係、授業の進度、教師との関係など)
- 自宅での生活リズムや学習状況
- 心理的な状態(無気力、焦燥感、強い不安など)
これらの情報が学校側に伝わることで、子どもにとって適切な関わり方が見えてきます。
1.2 「問題点」より「子どもの願い」を伝える
学校に状況を伝える際、つい「学校の対応が悪かった」「クラスの雰囲気が合わない」といった問題点にフォーカスしてしまうことがあります。しかし、学校側に改善を求める場合も、子どもの「願い」や「望んでいること」を伝える方が、建設的な関係を築きやすくなります。
例えば、「〇〇先生の授業が分かりづらい」と伝えるより、「子どもは授業内容について、もう少しゆっくり進めてもらえると安心できると言っています」と伝える方が、学校側も柔軟に対応しやすくなります。子どもの立場に立った「前向きな希望」として伝えることが、学校との良好な連携につながります。

1.3 「学校に期待すること」を具体的に伝える
学校側も不登校の子どもへの対応に苦慮していることが多く、「どう関わればよいか分からない」という戸惑いを抱えています。そのため、保護者が「何を学校に期待しているのか」を具体的に伝えることで、学校側はより的確な対応ができます。
例えば、「週に1回、担任の先生から手紙をもらえると安心するようです」や「オンラインで少しでも授業の様子が分かると、復帰へのハードルが下がるかもしれません」といった具体的な提案は、学校側も動きやすくなります。
1.4 担任任せにせず、複数の教職員とつながる
不登校の子どもへの対応は、担任だけに任せてしまうと限界があります。担任の先生が熱心であっても、多忙な業務の中で十分に関わる時間を取れないこともあります。そのため、スクールカウンセラーや学年主任、特別支援コーディネーターなど、複数の教職員と情報共有を進めることが望ましいです。
「誰がどの役割を果たしてくれるのか」「どの先生が子どもと気が合うか」を見極めながら、複数の関係者と連携していくことで、より多角的なサポートが可能になります。況が変わればまた調整する」といった姿勢で、焦らず段階的に進めていくことが大切です。
第2章 学校との連携がうまくいかない時の原因とは?
学校との連携を試みても、思うように進まないケースもあります。学校側の対応が消極的であったり、子どもの状況に対する理解が不足している場合、保護者としては「どうして学校は動いてくれないのか」と不安や不満を抱くこともあります。この章では、学校との連携がうまくいかない原因と、それを解消するための具体的な対策について説明します。
2.1 学校側の「不登校に対する理解不足」
学校側は「不登校は家庭の問題」と捉えてしまう傾向があります。また、子どもが学校を拒否している理由を十分に理解せず、「本人がそのうち戻ってくるだろう」と様子見を続けてしまうケースもあります。このような状況では、保護者が学校に対して「我が子の状況は特別な配慮が必要である」ということを丁寧に説明する必要があります。
2.2 保護者が「学校に遠慮しすぎている」
一方で、保護者の方が学校との関係を悪化させたくないあまり、意見を伝えにくく感じてしまうケースもあります。しかし、不登校の解決には学校との連携が不可欠であり、「学校にお願いして申し訳ない」と感じる必要はありません。むしろ、子どものために必要なサポートを求めることは、親の当然の役割です。
2.3 「学校の限界」を見極めたうえでの関わり方
学校にもできることとできないことがあります。学校の対応が不十分であっても、全面的に依存するのではなく、「学校に求めること」と「家庭でできること」のバランスを見極めることが大切です。学校側が対応できない部分については、家庭で補完する形で支えていくことで、子どもの安心感が高まります。
第3章 再登校に向けた学校との具体的な連携ステップ
学校との連携が進むことで、子どもの不登校状態からの回復は大きく前進します。しかし、再登校に向けた支援は単に「学校に戻ること」をゴールとせず、「子どもが学校で安心して過ごせる環境を整えること」に焦点を当てる必要があります。ここでは、再登校に向けた学校との具体的な連携ステップについて、実践的な方法を解説します。
3.1 再登校の「タイミング」は子ども主体で決める
再登校に向けた連携で最も重要なのは、「いつ学校に戻るか」を子どもの気持ちを軸に決めることです。親としては「早く戻ってほしい」という焦りが生まれがちですが、子どもがまだ心理的に準備ができていない段階で無理に登校を促すと、再登校が長続きせず、再び不登校状態に戻ってしまうことが多いのです。
しかし、「子どもが戻りたいと言うまで待つ」という姿勢だけでは、状況が長期化してしまう恐れがあります。そこで、学校との連携では、「子どもがどの段階で戻れそうか」「どのような条件が整えば戻りやすいか」を見極めることが重要です。
具体的なステップ:
- 担任の先生やスクールカウンセラーと定期的に情報交換を行い、子どもの心理状態や意欲の変化を把握する。
- 子どもと「学校に戻ったときに不安に感じること」を具体的に話し合い、不安要素を一つずつ減らす取り組みを学校と共有する。
- 「別室登校」「短時間登校」「放課後の個別対応」など、子どもが段階的に学校に慣れる方法について、学校と柔軟に調整する。
3.2 「復帰後の環境」を事前に整える
再登校がスムーズに進むかどうかは、学校側の「受け入れ態勢」が整っているかに大きく左右されます。子どもが不安を感じる要素を取り除き、「戻っても大丈夫」と思える環境を学校と共に整えることが不可欠です。
環境調整の具体的なポイント:
- 学習面の配慮
長期間の不登校の場合、授業の進度についていけるかどうかが子どもの大きな不安材料です。学校側と相談して、復帰後の学習サポート体制(補講、個別指導、プリント補助など)を整える必要があります。ただし、無理に「遅れを取り戻す」ことを目的とせず、「自分のペースで学び直せる」という安心感を与えることが大切です。 - 人間関係の調整
不登校のきっかけが友人関係の場合、復帰後に同じクラスで過ごすことへの抵抗感があります。この場合、学校側と「席替えの配慮」「グループ活動の調整」「特定の友人との距離の確保」など、子どもが少しずつ人間関係を再構築できる環境を作ることが求められます。 - 教職員の理解と関わり方の調整
子どもが戻った時に、担任だけでなく教科担当の先生や学年主任が「今の子どもの心理状態」を正しく理解していることが大切です。保護者は、学校側に対して「どのような声かけが有効か」「子どもが安心して話せる教職員は誰か」といった情報を共有し、復帰後の関わり方を事前にすり合わせる必要があります。

3.3 再登校の「初期段階」を丁寧にサポートする
再登校の初期段階は、子どもにとって非常に大きな心理的ハードルです。この段階でのサポートが不十分だと、せっかく再登校してもすぐに「もう無理だ」と感じてしまい、再度の不登校につながることがあります。学校側と密に連携し、再登校の初期段階を丁寧にサポートすることが、長期的な安定につながります。
再登校初期のサポートポイント:
- 「登校日数」にこだわらず、学校との接点を増やす
最初は「毎日登校する」ことを目標にせず、「週に1回でも登校できたら十分」と考え、子ども自身が「できた」という達成感を積み重ねることが重要です。学校側には「登校日数よりも、まずは学校との関係を取り戻すこと」を目的とするよう伝え、柔軟な対応をお願いしましょう。 - 「教室に入れない場合」も想定したプランを準備
再登校した直後、教室に入れずに保健室や別室で過ごすこともよくあります。この場合も「教室に入れない=失敗」と捉えず、「学校の空間に慣れるステップ」として位置づけることが大切です。学校側と「教室以外の安心できる場所」「特定の先生が見守る時間帯」などをあらかじめ調整しておくことで、子どもは「万が一の逃げ場がある」と安心できます。
3.4 「親の役割」はあくまで伴走者
再登校に向けた過程では、親が「子どもを引っ張る役割」を担おうとすると、かえって子どもにプレッシャーを与えることになります。親はあくまで「伴走者」として、子どもが安心して学校に戻れる環境を整える役割に徹することが大切です。
伴走者としての関わり方:
- 学校側と子どもの間に立って、双方の思いを丁寧に伝えながら橋渡し役を務める。
- 「登校できたかどうか」ではなく、「学校に行こうと考えたこと」を評価する。
- 子どもが不安を口にした時は、否定せずに「それは大変だったね」と共感する。

第4章 学校との連携を長期的に維持するポイント
再登校が実現しても、そこから安定した学校生活を継続するには、学校との連携を長期的に維持していくことが不可欠です。再登校直後は、子ども自身も不安を抱えながら環境に慣れようとしています。しかし、登校が続くことで少しずつ安心感が芽生える一方で、些細な出来事で再び心のバランスを崩してしまうことも少なくありません。そのような時に、保護者と学校が継続的に情報を共有し、柔軟に対応していくことで、子どもは「困った時には守ってもらえる」という安心感を持つことができます。
4.1 「再登校後の不調」を想定して備える
再登校後、最初の数週間は順調に見えても、子どもが新たなストレスを感じ始めるのは少し時間が経ってからです。友人関係の微妙な変化、学業へのプレッシャー、教師との関係性など、さまざまな要因が重なることで、子どもは「やっぱり無理かもしれない」と感じ始めることがあります。
この「再登校後の不調」は、保護者と学校が見逃しがちなポイントです。しかし、ここで迅速かつ丁寧に対応することで、再度の不登校を防ぎ、安定した学校生活を継続できる可能性が高まります。
不調のサインに気づくポイント:
- 「朝、登校準備に時間がかかるようになった」「お腹が痛い、頭が痛いと言い出す」など身体症状の増加。
- 学校から帰宅後、以前よりも疲れやすくなり、何も話したがらなくなる。
- 学校での出来事に対して否定的な発言が増え、再登校前のネガティブな気持ちが戻ってきている。
不調を感じた時の対応:
- 早めに担任やスクールカウンセラーに状況を伝え、「しばらく様子を見ましょう」ではなく、具体的な対策を一緒に検討する。
- 一時的に別室登校や短時間登校を取り入れるなど、柔軟な選択肢を提示する。
- 子ども自身にも「調子が悪い時は、学校と相談して無理をしない方法がある」と伝え、不安を和らげる。
4.2 「担任任せ」にならない関係づくり
再登校後は、どうしても担任の先生との関係が中心になりますが、長期的な連携を維持するためには、担任だけに依存せず、複数の教職員と関係を築いておくことが重要です。担任の異動や学年の変化によって状況が変わった場合も、子どもの状況を理解している複数の教職員とつながっていることで、継続的な支援が途切れることを防げます。
関係構築のポイント:
- スクールカウンセラーとの定期面談
担任だけでなく、スクールカウンセラーとも定期的に面談を行い、子どもの状況を共有しておくと、担任が変わった場合にも継続的なフォローが期待できます。 - 特別支援コーディネーターとの連携
学校には特別支援コーディネーターが配置されていることが多く、学習面や心理的配慮が必要な子どもへのサポート体制について相談することができます。担任が多忙な時にも、コーディネーターが間に入ることで、スムーズな対応が可能になります。 - 学年主任や管理職とも関係を築く
学年主任や校長・教頭とも定期的に情報を共有しておくことで、学校全体の方針として子どもへの配慮が継続されやすくなります。
4.3 「学校からの情報」を積極的に引き出す
再登校後も、子どもは家庭で学校の出来事を細かく話すことは少なくなります。特に、うまくいっていない時ほど、自分の気持ちを言葉にできずに抱え込んでしまうケースが多いです。そのため、保護者としては、学校側から積極的に情報を引き出し、子どもの状況を把握することが重要です。
情報共有の方法:
- 定期的な面談や電話連絡の依頼
再登校後も「順調そうだから大丈夫」と思わず、定期的に担任やスクールカウンセラーと面談を行い、子どもの様子を確認します。必要があれば、電話連絡やメールで簡単に状況を把握するだけでも、安心材料になります。 - 「困った時のサイン」を学校側と共有
子どもが再び不安を抱え始めた時に現れるサイン(疲れやすくなる、教室に入れなくなる、授業中にぼんやりしているなど)を学校側に伝え、「このような様子が見られたら早めに知らせてほしい」と依頼しておくことで、早期対応が可能になります。 - 子どもと話す「きっかけづくり」
学校での出来事について子どもから話を引き出すために、「今日は〇〇先生と話せた?」「お昼は誰と食べた?」など、具体的で答えやすい質問を心がけることで、子ども自身の思いを少しずつ言葉にできるようになります。
4.4 「学校との関係」が途切れそうな時の対応
再登校が軌道に乗ると、学校側も「もう大丈夫だろう」と安心してしまい、連携が途切れがちになります。しかし、長期的に安定した学校生活を送るためには、学校との関係を意図的に維持し続けることが重要です。
関係を維持する工夫:
- 定期的に短い面談を申し込む
「特に問題はなさそうでも、今の状況を知りたい」という理由で、短時間の面談や電話連絡を依頼することで、学校側にも「引き続き気にかけている」という姿勢が伝わります。 - 学校行事や保護者会への積極的な参加
学校行事や保護者会への参加を続けることで、担任だけでなく他の教職員とも顔を合わせ、子どもの状況について自然な形で情報交換ができます。 - 「困った時だけ連絡する」のではなく、ポジティブな情報も共有
子どもが学校で「うまくいったこと」「前よりも成長したこと」を学校側に伝えることで、教職員も子どもの変化をポジティブに捉え、さらなるサポートへのモチベーションが高まります。
第5章 子どもと学校との「信頼関係」を築くための支援とは?
学校との信頼関係を築くことは、再登校後の安定した学校生活を維持するための重要な要素です。不登校を経験した子どもは、学校に対して「自分の気持ちを分かってもらえなかった」「助けてもらえなかった」というネガティブな記憶を抱えていることが多く、再登校後も「また同じことが起きるのではないか」と心のどこかで不安を感じています。その不安を和らげ、学校との信頼関係を再構築するには、保護者の適切な関わりとサポートが欠かせません。
5.1 「学校での安心感」を少しずつ積み重ねる
再登校後の子どもは、学校にいるだけで大きなエネルギーを消耗しています。そのため、最初のうちは「頑張って登校している」というだけで十分です。保護者としては、「教室で過ごせた」「授業を最後まで受けられた」といった成果を求めるのではなく、「学校に行けた」「先生と目を合わせられた」といった小さな成功体験を積み重ねることを大切にしてください。
安心感を積み重ねるための具体的な方法:
- 「学校で頑張れたこと」を子ども自身に気づかせる
「今日は教室に入れたね」「友達と少し話せたね」といったポジティブな声かけを意識することで、子ども自身が「自分は頑張れている」と自覚できます。
ただし、「頑張ったね」「偉いね」といった単純な褒め方ではなく、「〇〇ができたこと、すごいと思うよ」と、具体的に認める言葉をかけることで、子どもの達成感はより深まります。 - 学校側と「子どもの頑張り」を共有する
担任の先生に「今日は〇〇ができたと話していました」と伝えることで、学校側も子どもの努力に気づき、よりきめ細かいサポートを続けやすくなります。また、学校側からも「最近〇〇ができるようになりました」とフィードバックがあると、子どもは「学校も自分のことを見てくれている」と感じ、安心感が増します。 - 「学校外での成功体験」を学校に伝える
学校での成功体験だけでなく、家や習い事での小さな達成も学校側と共有することで、教職員は子どものポジティブな変化に気づきやすくなります。「最近、家で読書を始めた」「習い事で友達と話せるようになった」といった情報は、学校での関わり方のヒントになります。
5.2 「子ども自身の気持ち」を学校に伝え続ける
再登校後も、子どもは自分の気持ちを学校の先生にうまく伝えられないことが多いです。「学校で困っていること」「苦手なこと」「安心できること」を先生に伝えられず、心の中でモヤモヤを抱えたまま過ごしているケースは少なくありません。
そこで、保護者が「子どもの気持ちの代弁者」として、学校側に子どもの内面を丁寧に伝え続けることが、信頼関係の構築につながります。
子どもの気持ちを伝える際のポイント:
- 「子どもの言葉」をそのまま伝える
「〇〇ちゃんは、最近〇〇について少し不安に感じていると言っていました」「〇〇先生の授業が少し速く感じるみたいです」と、子どもの言葉をできるだけそのまま伝えることで、教職員は子どもの気持ちをよりリアルに理解できます。 - 「要望」ではなく「気持ち」として伝える
「〇〇してほしい」と学校側に要望を伝えるのではなく、「子どもは〇〇に不安を感じている」といった事実として伝えることで、学校側も柔軟に対応しやすくなります。 - 子どもの「良い変化」も積極的に共有する
「最近、〇〇が少しずつできるようになっています」とポジティブな変化を学校側に伝えることで、先生たちも「子どもは頑張っている」と感じ、信頼関係が深まります。
5.3 「学校で困った時の逃げ場」を確保する
学校での信頼関係がまだ十分に築かれていない段階では、子どもは「困った時にどこに行けばいいのか分からない」という不安を抱えています。この「逃げ場がない」という感覚が、再び不登校に戻ってしまう要因になりかねません。
そこで、学校側と連携して、子どもが「困った時に頼れる場所」を確保しておくことで、安心感を高めることができます。
逃げ場を確保する具体的な方法:
- 「保健室登校」や「別室対応」の選択肢を残しておく
再登校後も、教室で過ごすことが難しくなった時に、保健室や別室で過ごせる選択肢があると、子どもは「無理しなくていい」と感じられます。
ただし、「保健室に行く=失敗」と子どもが感じないように、「ちょっと休憩する場所」「気持ちを落ち着ける場所」としてポジティブに位置づけることが大切です。 - 「特定の先生」を避難先に設定する
子どもが信頼できる先生がいる場合、「何かあったら〇〇先生のところに行ってもいいよ」と伝えておくことで、子どもは「いざという時の避難先」を持てます。
学校側とも事前に「〇〇先生が避難先として対応する」という共通認識を持っておくことで、緊急時の対応がスムーズになります。
5.4 「子どもの意見」を学校生活に反映させる
子どもが学校に対して信頼感を持つためには、「自分の意見が尊重されている」と感じることが重要です。不登校を経験した子どもは、「学校は自分の気持ちを分かってくれない」と感じることで、さらに心を閉ざしてしまうことがあります。
そこで、学校との連携では「子どもの意見を学校生活に反映させる」という視点を持つことで、子ども自身が「学校は自分を大切にしてくれている」と感じやすくなります。
意見を反映させるための方法:
「困った時のサイン」を子どもと共有しておく
「教室にいられなくなった時は、保健室に行ってもいいよ」「先生にサインを出していいよ」といったルールをあらかじめ決めておくことで、子どもは「自分で状況をコントロールできる」という自信を持てます。
「登校スケジュール」を子どもと一緒に決める
再登校の際、登校日数や時間帯、別室で過ごすかどうかなどの選択肢を子どもと一緒に考え、「自分で決めた」という感覚を持たせることが大切です。
「授業の受け方」を柔軟に調整する
「全部の授業を受けるのがしんどい」と感じている場合は、「まずは1時間目だけ参加」「得意な教科から入る」といった方法を、子どもと話し合いながら決めます。
学校側にも「〇〇は、今のところこのスタイルでやってみたいそうです」と伝えることで、子どもの意思が尊重されていると感じやすくなります。
まとめ:親と学校の「協働」が子どもの継続登校を支える
| 各章 | 要点 | 必要な行動 |
|---|---|---|
| 不登校の背景共有 | 学校に子どもの状況・心理状態を具体的に伝え、共通理解を深めることが再登校への第一歩。 | 子どもの不安、生活リズム、心理状態を正確に学校へ伝え、希望するサポート方法を明確に伝える。 |
| 連携がうまくいかない時 | 学校側の不登校への理解不足や、保護者の遠慮が連携を妨げる原因になる。 | 学校の限界を見極めつつ、具体的なサポートを求め、複数の教職員との関係構築を図る。 |
| 再登校へのステップ | 再登校は子どもの心理的準備を見極めながら、段階的かつ柔軟に進める必要がある。 | 無理のないスケジュールで段階的に復帰し、学習・人間関係・教職員の関わり方の環境調整を進める。 |
| 連携の維持 | 再登校後も継続的な情報共有と複数の教職員との関係構築が、安定した学校生活を支える。 | 定期的な面談や情報共有を続け、子どもの変化に気づきやすい関係を維持する。 |
| 信頼関係の構築 | 子どもが「学校は自分を理解している」と感じることで、長期的な安心感につながる。 | 子どもの気持ちを代弁し、学校との関係を築き、安心できる逃げ場の確保や意見の反映を促す。 |
再登校後の安定した学校生活は、保護者と学校が継続的に連携し、子どもを支え続けることで実現します。
子どもが「学校は自分を理解してくれている」「困った時には助けてくれる」と信じられる環境を整えることが、不登校の再発を防ぎ、将来的に子どもが自信を持って社会に踏み出すための土台となります。
最後に強調したいのは、保護者と学校の関係は「親が学校にお願いする立場」ではなく、「子どもを一緒に支えるパートナー」という協働の姿勢であるべきだということです。お互いの立場や意見を尊重しながら、子どもが安心して自分らしく成長できる環境を整えていくことが、私たち大人の大切な役割です。
再登校はゴールではなく、子どもの未来につながる新たなスタートです。学校と連携しながら、子どもが自分のペースで前に進めるよう、温かく見守っていきましょう。
【国内最多の登校支援実績】トーコについて
私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。
「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。
それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。
無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。