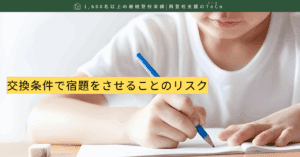子どもの嘘との付き合い方
こんにちは。
ToCoの不登校カウンセラー、竹宮です。
今日は「子どもの嘘」について書きたいと思います。
これは、保護者の方からよく聞かれるテーマです。
「うちの子、最近よく嘘をつくんです」
「隠しごとばかりして、何を考えてるのか分からなくて……」
このようなお悩み、とても多いです。
親子関係のご相談を受ける中で、「嘘をつく子ども」について心を痛めている親御さんは少なくありません。
目次
嘘をつくのは悪いこと?
まず、一般的な考え方を確認してみましょう。
多くの親は「嘘はよくないこと」と教えられて育ちます。だから、自分の子が嘘をつくと「このままで大丈夫だろうか」と不安になるんです。
「嘘をついてはいけません」
「正直に話しなさい」
これらは、保育園や小学校でもよく言われるフレーズですね。
善悪を教える道徳教育の一環として、「嘘=悪」という構図はわかりやすいものです。
でも、ここでちょっと考えてみてください。
本当に、すべての嘘が悪いことなんでしょうか?
「よくない嘘」と「必要な嘘」
実は、嘘にはいろんな種類があります。
たとえば
・テストの点数を誤魔化す嘘
・ゲームをやっていないと主張する嘘
・「学校、行きたくない」と言えずに「体調が悪い」と言う嘘
全部を一括りにして「悪いこと」としてしまうのは、少し乱暴かもしれません。
人はなぜ嘘をつくのか。それは、自分を守るためです。
特に、子どもはまだ「うまく伝える力」や「適切な自己防衛の方法」が育っていません。
だからこそ、「本音を言うのが怖い」「怒られたくない」「分かってもらえないかもしれない」と感じたときに、嘘という手段をとってしまいます。
つまり、嘘はその子の“今の限界”を教えてくれているサインでもあるのです。
「嘘をつく子は信用できない」という誤解
ここで、少し厳しめの意見を紹介します。
「嘘をつくなんて、信用できない」
「そんな子、社会に出て困る」
こうした言葉は、親が子どもに対して抱いてしまうこともあります。
心配から来る感情なのは分かります。ただ、この考え方には注意が必要です。
子どもが嘘をついたとき、それを「性格の問題」や「人間性の欠陥」と捉えるのは早計です。
大人でも、場の空気を読んで「本当のことを言わない」ことってありますよね。
社会生活には、正直さが誰にとってもマイナスとなる場面があります。
他者を思いやっての嘘さえも完全に否定してしまうと、かえって生きづらくなるのではないでしょうか。
「どうせ言っても分かってもらえない」と感じている子どもたち
また、子どもが嘘をつく背景には、「言っても伝わらない」という諦めが潜んでいることがあります。
これ、親としてはとてもつらいことですよね。
でも、たとえばこんな場面を思い出してみてください。
子:「今日、学校で嫌なことがあった」
親:「また?それぐらいで気にしすぎじゃない?」
この返し、つい言ってしまうこともあるかもしれません。
ただ、子どもはこの一言で「やっぱり、話してもムダだ」と感じてしまうことがあります。
そして次からは、話す代わりに嘘をつくようになります。
「行きたくない理由を言っても分かってもらえない」
「だから、体調が悪いってことにしよう」
このように、嘘の背景には「話せない事情」や「伝えたい気持ち」が隠れていることが多いのです。
嘘を責める前に、まず理解すること
子どもの嘘に対して、「どうしてこんなことを言うの?」と問い詰めたくなる気持ちは分かります。
でも、まずは少し立ち止まって考えてみてください。
「この子は、なぜこの嘘を選んだんだろう?」
「どんなことを隠したかったのかな?」
その背景を想像するだけで、接し方はずいぶん変わってきます。
たとえば、学校に行きたくない理由を隠して「お腹が痛い」と言っている子がいたとします。
そのとき、「本当は学校がイヤなんでしょ?サボるつもり?」と返すのと、
「そっか、今日はお腹が痛いんだね。どんな感じ?」と声をかけるのとでは、
子どもが感じる安心感は大きく違います。
もちろん、嘘を肯定するわけではありません。
でも、「嘘をつかなくてすむ関係」を築くことは、十分にできるんです。
嘘を叱るより、まず気持ちを拾う
「どうして嘘なんかついたの?」
「本当のことを言いなさい」
これは、つい言いたくなる言葉です。
でも、言われた側の子どもが感じるのは、「責められている」という気持ちです。
嘘を指摘されると、多くの子どもは防御モードに入ります。
つまり、それ以上本音は話せなくなります。
では、どうすればいいのか。
コツは、「嘘をついたこと」ではなく、「嘘をつかなければいけなかった気持ち」に注目することです。
たとえば、こう声をかけてみてください。
「今日のこと、全部じゃなくてもいいから、ちょっとずつ教えてくれたら嬉しいな」
「○○って言ってたけど、何か心配なことがあったのかな?」
こうした言葉には、「嘘を責めないよ」「気持ちを知りたいだけだよ」というメッセージが込められています。
すぐに全部を話してくれるとは限りません。
でも、繰り返すことで、「この人は、ちゃんと話を聞いてくれる」と感じてもらえるようになります。
「正直=善」という固定観念の落とし穴
よく、「正直でいることは良いこと」と言われます。
もちろん、それは大切な価値観です。
でも、「正直じゃない=悪い子」という構図になってしまうと、かえって子どもを追い込むことになります。
たとえば、親が「何でも正直に言ってね」と言いながら、子どもが失敗を告白したときに強く叱ってしまうと、
「正直に話すと損をする」と学習してしまいます。
そして次からは、隠すようになります。
つまり、正直さは「怒られない安心感」があってこそ育つんです。
「失敗しても大丈夫」
「本当のことを言っても、見捨てられない」
この安心感があるとき、子どもは自分から真実を話すようになります。
親の「構え方」が、子どもの正直さを育てていくのです。
嘘を減らすために、親ができる3つの工夫
ここからは、少し実践的な話です。
子どもが嘘をつく回数を減らすために、親としてできることを3つご紹介します。
① 「嘘を責めない日」をつくってみる
たとえば、週に1回、「正直に話しても怒らない日」を決めてみるのもひとつの方法です。
この日は、どんなことでも冷静に聞く。
「叱らないよ」「聞くだけにするね」と前もって伝えておくことで、子どもは話す準備がしやすくなります。
実際にやってみると、「こんなことを考えてたんだ」と驚くような話が出てくることもあります。
安心できる時間があると、心の距離が少しずつ縮まっていきます。
② 「質問の仕方」を変えてみる
「○○したの?」とYes/Noで答える質問だと、子どもはとっさに嘘をつきがちです。
たとえば「宿題やったの?」と聞かれると、「うん」と答えてしまう子も多いです。
それよりも、「今日の宿題、どこまで進んだ?」とか、「どこが難しかった?」といった聞き方の方が、嘘をつきにくくなります。
答え方に“余白”があると、正直に話しやすいのです。
③ 「正直なとき」に注目する
嘘をついたときにだけ反応するのではなく、
「正直に話してくれたとき」にしっかりリアクションすることも大切です。
たとえば、こんなふうに言ってみてください。
「本当のことを言ってくれて、ありがとう」
「それを話すのって、ちょっと勇気がいったよね」
こうした言葉は、「正直でいていいんだ」という感覚を育てます。
特に思春期の子どもにとって、これは大きな支えになります。
嘘が続くときの親の辛さ
ここまで読んで、「そんなふうに冷静に対応できたら苦労しない」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
それも、ごもっともです。
子どもに嘘をつかれると、親は本当に辛いです。
「信用されてないのかも」
「何が本当なのか分からない」
「このままじゃ将来が不安」
こんなふうに、不安や怒り、悲しみが入り混じります。
だからこそ、まずは「親も揺れて当然」と思っていてください。
完璧な対応なんて求めなくていいんです。
大切なのは、「嘘を減らすこと」ではなく、「嘘をつかなくて済む関係を作ること」です。
時間はかかるかもしれません。
でも、じわじわと、関係は変わっていきます。
嘘の奥にあるものを、ちゃんと見ていく
最後に、少しまとめを。
正直さが大切ではなく、相手を思う心こそ大切であること。
例えば、こんな会話も考えられます。
子ども「今日さ、友達の服がちょっと変だなって思ったけど、本当のこと言ったら傷つきそうで言わなかった。」
親「うん、それでいいと思うよ。」
子ども「でも正直に言うのが大事なんじゃないの?」
親「たしかに正直は大事だけどね。全部をそのまま言うことだけが正しさじゃないよ。
たとえば、病院で入院している人が『お見舞いに来てくれて嬉しい』って言うのは、本当は会うのが辛い状態でも、嬉しい気持ちを伝えたいからだよね」
子ども「ああ…そういうのも嘘ってことか。」
親「そう。優しさからの嘘もあるんだよ。だから、嘘かどうかより、『その言葉が誰かを大事にしてるかどうか』を考えるといいかもしれないね。」
そして、子どもの嘘は、単なる問題行動ではありません。
むしろ、「自分の気持ちをうまく言えない」「伝える力が育っていない」という発達のサインでもあります。
嘘を見たときに、それをどう受け止めるか。
この視点の持ち方が、親子関係に大きく影響します。
責めるより、想像する。
詰めるより、待つ。
問い詰めるより、「聞いても大丈夫だよ」と伝える。
その積み重ねが、子どもを少しずつ変えていきます。すぐに変化があるわけではありません。
でも、今日のやり取りが、数ヶ月後の信頼につながることもあります。
焦らず、でも諦めずに。
子どもの嘘と、上手につき合っていけるよう、少しでも参考になれば嬉しいです。
【国内最多の登校支援実績】トーコについて
私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。
「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。
それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。
無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。