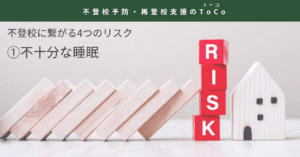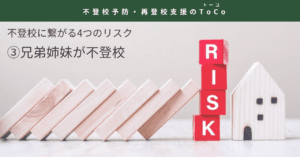不登校に繋がる4つのリスク: ②欠席の経験が多い
不登校や引きこもりの問題に取り組む児童心理司の藤原と申します。私は現在、ToCo株式会社の顧問として、不登校が継続してしまう要因にアプローチすることで、子どもたちが再び学校に戻れるようになるためのサポートを行っています。
今回は、「不登校を未然に防ぐために知っておくべき4つのリスク」の中から、2つ目の「欠席の経験が多い」ことについて詳しくお話しします。
不登校を単なる「出来事」として捉えるのではなく、その背景にある心の動きや環境要因を冷静に理解することが、不登校の未然防止に繋がります。
目次
「過去の欠席歴」の心理的影響
人間は、どのような理由であれ「自分だけが長期間休む」という状況に直面すると、不安や孤独感を覚えやすくなります。それは大人でも同じことですが、小さな子どもにとっては、こうした経験が心に残す影響は計り知れません。
たとえば、長期間学校を休んだ理由が病気やけがであった場合でも、子どもたちは「自分はずる休みをしてしまった」「他の子のような”普通”ではなくなった」という感覚を持ちやすくなります。そして、復帰する際に、周囲の目や反応を過剰に気にすることが多くなります。この不安感が、「また同じ状況になったらどうしよう」という恐れを生み、さらなる不安を抱かせるのです。
一方で、不登校の直接的な原因が人間関係のトラブルや学校生活への不適応である場合は、「学校に行かない」という選択肢が心の中でより強く根付くことがあります。この選択肢は、最初こそ本人にとって「非常手段」だったかもしれませんが、一度それが功を奏したと感じれば、次回以降は容易に同じ道を選ぶようになります。
これらの心理的な動きは、子どもにとって必ずしも意識的なものではありません。むしろ無意識のうちに、過去の経験が現在の行動に影響を与えているケースがほとんどです。したがって、「過去の欠席歴がある」というリスクは、その子どもの持つ内面的な傾向を理解するための重要な手がかりとなります。
一度不登校を経験した場合の特有の課題
よく頂く質問の一つに、「長期欠席となったことは、その後の学校生活にどう影響しますか?」というものがあります。多くの場合、子どもたちは再登校に成功することで自信を取り戻します。しかしながら、ここで注意すべきは、過去の不登校経験が完全に「リセット」されるわけではないということです。
不登校の経験をした子どもは、再び困難な状況に直面したときに「学校に行かない」という選択肢を容易に思い浮かべる傾向があります。これには心理的なメカニズムが関係しています。人間はストレスを感じると、過去にとった行動を無意識のうちに繰り返しやすくなる性質を持っています。たとえば、大声をあげて不安を解消する人は、次回も同じ行動をとる可能性が高いのです。同じように、「学校を休む」という選択肢が一度でも心に根付いた子どもは、その後も同じ手段を取りがちになるのです。
この傾向は、特に小学校から中学校、そして高校といった新しい環境に移行する際に顕著になります。環境が変わるたびに適応が求められるため、過去の不登校経験が「次もそうなるかもしれない」という不安を呼び起こしやすくなるのです。これは不登校経験のある子どもたちが、新しい環境でつまずきやすい理由の一つとも言えます。
家庭や学校ができる具体的な対策
では、「過去の欠席歴がある」子どもをどうサポートすれば良いのでしょうか?ここでは、家庭と学校で実践できるいくつかの具体的な方法を紹介します。
1. 家庭での対応
お母さまがまず取り組むべきなのは、子どもが「安心感」を持てる環境を整えることです。たとえば、次のような取り組みが効果的です。
- 肯定的な声かけを習慣化する
「学校に行かないと将来困る」という脅しではなく、「休むのは悪いことではないけれど、どのように戻るかが大切だよ」といったポジティブなメッセージを伝えることが重要です。 - 過去の欠席経験について話し合う
子どもが過去に欠席していた理由や、そのときの気持ちを振り返る機会を持つことで、次に同じ状況になった際の対策を一緒に考えることができます。 - 失敗を恐れない姿勢を伝える
子どもが学校生活で失敗することを過剰に恐れないよう、「失敗は成長の一部」という考え方を伝えることも効果的です。
2. 学校での対応
一方で、学校側も過去の欠席歴を考慮した対応が求められます。
- 復帰支援の計画を立てる
例えば、長期欠席明けの子どもが徐々に登校日数を増やせるよう、柔軟なスケジュールを組むことが考えられます。 - 担任の先生のサポート体制
担任の先生が、子どもの過去の欠席歴や家庭環境についてしっかり把握し、復帰時に積極的なフォローを行うことが大切です。 - クラスメートの理解を促す
周囲の生徒に、復帰してきた子どもを受け入れる姿勢を育むための教育を行うことも、再登校を支える上で欠かせません。
最後に
「欠席の経験が多い」というリスクを抱える子どもにとって、最も重要なのは家庭と学校の連携による支援体制です。不登校は決して悪いことではありませんが、その経験を適切に理解し、将来に向けて活かすための努力が必要です。家族が子どもたちの心に寄り添って、安心して自分のペースで前進できる環境を提供することで、不登校という問題を乗り越える道が見えてきます。
| ポイント | 要点 | 必要な行動 |
|---|---|---|
| 過去に多い欠席歴がある | 過去に長期間の欠席経験がある子どもは、不登校を選択しやすくなる。休むことが「できる選択肢」として心に根付く場合が多い。 | 過去の欠席経験を学校と共有し、復帰時のフォローを丁寧に行う。少しずつ学校生活に慣れる支援を続ける。 |
| 欠席が心に与える影響 | 長期間の欠席経験が「再び休むのも簡単」との認識を強化し、不登校を選びやすい心理状態を作る。 | 過去の欠席経験を否定せず、それを乗り越えたことを子どもと共に振り返り、前向きな経験として活用する。 |
| 欠席経験の連鎖のリスク | 休むことに対する心理的なハードルが低くなるため、再度の欠席が起こりやすくなる傾向がある。 | 欠席が続く場合でも、日常生活のリズムを維持するよう促し、登校再開への準備を整える。 |
| 学校との情報共有の重要性 | 欠席経験がある場合、担任や支援者に情報を共有することで、きめ細やかなフォローが可能になる。 | 登校再開前の面談や電話連絡を通じて、子どもが安心して学校に戻れる準備を整える。 |
| 安心感を与える環境作り | 長期欠席を経験した子どもが学校に戻る際、安心感を与える環境が重要となる。 | 友人関係やクラスでの過ごし方に配慮し、最初は短時間から徐々に登校時間を延ばしていく。 |
関連記事
不登校に繋がる4つのリスク: ①不十分な睡眠
不登校に繋がる4つのリスク: ②欠席の経験が多い
不登校に繋がる4つのリスク: ③兄弟姉妹が不登校
不登校に繋がる4つのリスク: ④周囲への過敏性(HSP)
【国内最多の登校支援実績】トーコについて
私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。
「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。
それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。
無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。