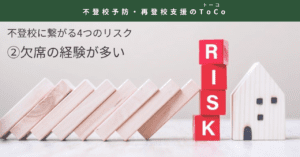不登校に繋がる4つのリスク: ①不十分な睡眠
不登校や引きこもりの問題に取り組む児童心理司の藤原と申します。私は現在、ToCo株式会社の顧問として、不登校が継続してしまう要因に焦点を当て、子どもたちが再び学校に戻れるようになるための支援を行っています。本日は、「不登校を未然に防ぐために知っておくべき4つのリスク」の中から、最初の「不十分な睡眠」に関するリスクについてお話しします。
「睡眠不足」や「睡眠の質の低下」は、不登校のリスクに大きく関わる要因です。子どもの心身の発達にとって睡眠は不可欠であり、そのバランスが崩れると、学業や人間関係、そして何よりも子どもの意欲や自信に深刻な影響を与えます。本稿では、このリスクの背景と、その対策について詳しく考えていきたいと思います。
目次
睡眠と不登校の関係性
1. 子どもの「睡眠」の重要性
子ども時代の睡眠は、大人以上に重要な役割を果たします。睡眠中、脳は日中に受けた刺激を整理し、情報を記憶として定着させるだけでなく、体の成長や免疫力の維持にも関わっています。小中学生の子どもたちは、成長ホルモンが夜間に活発に分泌されるため、十分な睡眠が確保されていないと、心身両面での健康に支障をきたすことがあります。
しかしながら、現代の子どもたちは「十分な睡眠」が得られていないケースが少なくありません。理由はさまざまですが、主に以下のような点が挙げられます:
- スマホやゲームなど、夜遅くまでのデジタル機器使用。
- 学校や塾の宿題、部活動による過密スケジュール。
- 家庭の夜型化による就寝時間の遅延。
特にデジタル機器の影響は大きく、夜間にスマホやタブレットを使用すると、ブルーライトが脳の覚醒状態を維持してしまい、入眠を妨げます。その結果、子どもたちは夜更かしが常態化し、翌朝の起床が困難になり、登校が難しくなるのです。
2. 不十分な睡眠が不登校に与える影響
十分な睡眠が取れていないと、以下のような影響が子どもたちに現れることがあります:
- 気分の不安定さ
睡眠不足は脳の感情をコントロールする部分に直接影響を与えるため、イライラしやすくなったり、悲観的になったりします。これにより、学校生活における人間関係のトラブルが増える可能性があります。 - 集中力や記憶力の低下
学業成績の低下につながり、「学校に行きたくない」という気持ちを引き起こす原因となります。 - 身体的不調
睡眠不足は免疫力を低下させ、体調を崩しやすくします。これが繰り返されると、「体調が悪いから学校を休む」というパターンができ、登校意欲の低下につながります。 - 生活リズムの乱れ
一度生活リズムが崩れると、元に戻すのは難しくなります。夜更かしと昼夜逆転が習慣化すると、朝起きるのが苦痛になり、不登校のリスクが一気に高まります。
「不十分な睡眠」の背景にある現代的課題
1. スマホやゲームが子どもたちに与える影響
現代の子どもたちは、スマホやゲームといったデジタル機器に囲まれて生活しています。それ自体が悪いわけではありませんが、使用時間や使い方が適切でない場合、睡眠不足を引き起こす要因になります。特に、以下のような影響が指摘されています:
- 夜間の使用による入眠障害
スマホやタブレットのブルーライトは、脳内のメラトニン(眠気を誘発するホルモン)の分泌を抑制します。その結果、夜遅くまで覚醒状態が続き、自然な眠気が来にくくなります。 - 過剰な刺激による興奮状態
アクションゲームやSNSでのやり取りは、子どもの脳を興奮状態にします。この影響で、ベッドに入ってもなかなか眠れない、という子どもが増えています。
2. 家庭の夜型化と生活リズムの乱れ
家族全体が夜型の生活を送っている場合、子どももそのリズムに引きずられることがあります。たとえば、夜遅くまでテレビを見ていたり、親が夜更かししている姿を見たりすることで、子どもにとって「遅くまで起きていること」が当たり前になります。このような環境では、規則正しい生活リズムを維持するのが難しくなります。
不十分な睡眠を防ぐための具体的アプローチ
睡眠不足が不登校のリスクを高めることを考えると、家庭内で睡眠環境を整え、生活リズムを改善することが重要です。ここでは、具体的なアプローチをいくつかご紹介します。
1. 睡眠環境を整える
子どもがリラックスして眠れる環境を作ることが大切です。
- 寝室の照明を見直す
就寝前は、蛍光灯ではなく暖色系の間接照明に切り替えることで、脳がリラックスしやすくなります。 - デジタル機器の使用制限
寝る1時間前にはスマホやタブレットの使用を控えるルールを設けることが有効です。リビングに充電スペースを設け、子どもの枕元にスマホを持ち込ませないようにするのも良いでしょう。 - 快適な寝具を用意する
マットレスや枕の硬さ、肌触りなどを見直し、子どもに合った寝具を選びます。
2. 規則正しい生活リズムを促す
生活リズムを整えることで、自然と睡眠の質が向上します。
- 朝日を浴びる
起床後に太陽光を浴びることで、体内時計がリセットされ、1日のリズムが整いやすくなります。 - 食事のタイミングを一定にする
朝食をしっかりとることで、体が活動モードに切り替わりやすくなります。また、夜遅い時間の食事は避けるようにしましょう。 - 寝る時間と起きる時間を固定する
平日と休日で大きく睡眠時間が異ならないようにすることが重要です。
3. 睡眠の大切さを学ばせる
子ども自身が睡眠の重要性を理解することで、主体的に生活を改善する意欲が高まります。科学的なデータを使って、「十分な睡眠が取れていると集中力が上がる」「成績が良くなる」といったメリットを伝えるのも効果的です。
最後に
「不十分な睡眠」というリスクは、不登校の背後に隠れがちな要因の一つですが、実際には非常に大きな影響を及ぼします。子どもたちが十分に眠れる環境を整え、生活リズムを見直すことで、不登校のリスクを大幅に減らすことが可能です。
睡眠は、体と心を整える基盤です。お母さまが家庭全体の生活リズムを見直し、子どもたちが安心して休める環境を整えることが、不登校の予防につながります。まずは、今日からできる小さな一歩を始めてみてください。
| ポイント | 要点 | 必要な行動 |
|---|---|---|
| 不十分な睡眠 | 睡眠不足は気分や集中力の低下、生活リズムの乱れを引き起こし、不登校の大きな要因となる。 | デジタル機器の使用制限や規則正しい生活リズムを整え、朝日を浴びるなどして睡眠の質を向上させる。 |
| 睡眠不足の影響 | 睡眠不足は学業成績や人間関係に悪影響を与え、不登校リスクを高める。 | 規則正しい睡眠習慣を家庭全体で共有し、子どもが十分な休息を取れる環境を整える。 |
| デジタル機器の影響 | 夜間のスマホ使用が睡眠を妨げる要因となり、昼夜逆転の生活を招く可能性がある。 | スマホやタブレットの使用時間を制限し、寝る1時間前にはデジタル機器を使用しない習慣をつける。 |
| 家庭の夜型化 | 家族全体が夜型の生活を送ると、子どももその影響を受けやすくなる。 | 家庭全体で規則正しい生活を心がけ、親が睡眠習慣の良いロールモデルとなる。 |
| 睡眠の質の改善 | 時間だけでなく睡眠の質も重要で、環境やリズムが整わないと十分な休息が得られない。 | 寝室の環境を整え、暗く静かな空間を用意する。寝具や照明にも気を配り、快適な睡眠をサポートする。 |
関連記事
不登校に繋がる4つのリスク: ①不十分な睡眠
不登校に繋がる4つのリスク: ②欠席の経験が多い
不登校に繋がる4つのリスク: ③兄弟姉妹が不登校
不登校に繋がる4つのリスク: ④周囲への過敏性(HSP)
【国内最多の登校支援実績】トーコについて
私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。
「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。
それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。
無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。