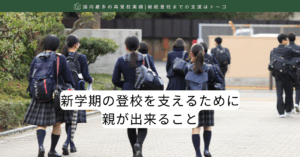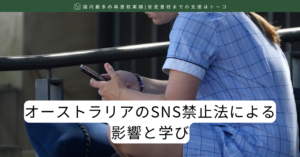教室登校に繋げるための、別室登校・リモート授業の活かし方
こんにちは。カウンセラーの竹宮と申します。
今日は、別室登校やリモート授業をどのように捉え、どう活かしていくと教室登校に繋がりやすいのかについてお話ししたいと思います。
不登校に関する相談を受けていると、
「まずは別室から慣れさせましょう」
「リモートだけでも参加させましょう」
といったアドバイスを耳にすることがあります。
その言葉自体には一定の合理性がありますが、私は少し立ち止まって考える必要があると感じています。なぜなら、誰かのための「表面的な参加」なのか、次に繋がる「主体的な参加」なのかによって、同じ行動でも意味が大きく変わるからです。
目次
- 「別室でも通えている」という安心が抱えるズレ
- 「別室に慣れる」ことが目的化したときの問題点
- 本人の「今の気持ち」を聞き取ることが最も重要
- 「親も心配だから、これくらいは頑張ろう」の危うさ
- 今後の進路を考えて「慣れたい」という気持ちが見えたとき
- リモート授業は「継続的な関わり」をつくる手段
- 親が感じる“期待”と“心配”の葛藤
- 「聞き出しの会話」ではなく「受け止めの会話」が必要
- 教室登校に繋がる“心理的プロセス”を理解する
- 「部分的な教室登校」をどう扱うか
- まとめ:視点を変えると、焦りは減り、見える景色が変わる
「別室でも通えている」という安心が抱えるズレ
まず、多くの保護者が感じるのは「学校に行けているなら、一歩前進している」という安心です。
これはとても自然な感情ですし、無理なく登校できる場所を選ぶことは悪いことではありません。
ただし、ここで一つ確認しておきたい点があります。
その別室登校は、お子さんにとって“前向きな一歩”になっているのか、それとも“周囲を安心させるためだけの行動”なのかという点です。
この違いは、教育心理学の領域では「外発的動機づけ」と「内発的動機づけ」の差として扱われます。
外発的動機づけとは「親が喜ぶから」「先生に言われたから」のような外からの理由。
一方、内発的動機づけとは「自分なりの目的がある」「授業内容に触れたい」といった内側からの理由です。
別室登校は、どちらの動機でも成立してしまうところに難しさがあります。
もし外発的動機づけが中心であれば、行動は続いているように見えても、学校生活に対する前向きな感情は育ちにくいのです。
ここが、一般的な「とりあえず別室から」というアドバイスが抱えている盲点になります。
「別室に慣れる」ことが目的化したときの問題点
別室登校は便利な方法であるがゆえに、「まずは慣れること」が目的化しやすい側面があります。
しかし、慣れることそのものがゴールになってしまうと、本来目指していた教室登校へのイメージがぼやけてしまうことがあります。
児童心理学では、安心できる場所を確保することは重要だとされていますが、同時に安心のために作った場所が新たな固定化した居場所になるリスクも指摘されています。
別室が落ち着ける空間だと感じると、そこから動き出すエネルギーはどうしても小さくなります。
これ自体は悪いわけではないのですが、もしお子さんの中に「いつかは教室にも少し戻れたら」という気持ちがあるのなら、別室の利用方法を調整する必要が出てきます。
つまり、別室登校が効果的に働くかどうかは、お子さんの目的意識がどこにあるのかで大きく変わるということです。
本人の「今の気持ち」を聞き取ることが最も重要
では、どのようにして「前向きな一歩」なのか「周囲を安心させるための一歩」なのかを見分ければよいのでしょうか。
その答えは、お子さんの言葉を丁寧に聞くところにあります。
ここで大切なのは「今日行けるの?」「参加するの?」といった確認ではなく、
学校をどんな場所として捉えているのか
今どんな距離感で関わりたいと考えているのか
といった、もう少し根本的な感情や意図に触れることです。
例えば、
「別室なら行けるけれど、教室に入る気持ちはない」
という言葉が出てきたのなら、それは“現状を保つための選択”である可能性があります。
逆に、
「授業内容は受けておきたい」
「昼休み以外なら少し参加してみたい」
といった気持ちがあるのなら、それは“将来を見据えた選択”のサインです。
前向きな方向性が少しでも見えるのであれば、そこを丁寧に広げていくことで教室登校の一歩が自然と見えてきます。
お子さんの言葉の背景には不安や緊張が混ざっていることも多いですが、意欲の芽があるかどうかを感じ取ることが最も大切なのです。
「親も心配だから、これくらいは頑張ろう」の危うさ
相談の場でよく耳にするのが、
「親も心配しているから、別室くらいは行こうと思う」
という子どもの言葉です。
このフレーズには優しさも含まれていますが、同時に深い葛藤も隠れています。
ここには「自分の気持ちよりも、親の安心を優先させよう」とする傾向が見られることがあります。
一見すると素直で健気な言葉のようですが、実際には次に繋がりづらい心理状態です。
なぜなら、これは先ほど説明した外発的動機づけの典型であり、本人が“自分のために学校に向かっている”状態ではないからです。
この状況が続くと、
・別室には行けるが、教室には全く近づこうとしない
・リモート授業には出るが、学校に関心が向かない
・周囲は「良くなっている」と思うが、本人は疲弊している
といった深刻なギャップが生じることがあります。
そのため、この言葉が出てきたときこそ、
「あなた自身はどうしたいか」を丁寧に扱う必要がある場面なのです。
今後の進路を考えて「慣れたい」という気持ちが見えたとき
別室登校やリモート授業が効果的に働く瞬間があります。
それは、本人が
「将来のために学校の雰囲気には慣れておきたい」
「教室がすぐには難しくても、いつかは戻りたい」
といった意図をもっている時です。
この方向性が確認できる場合、
別室に完全に落ち着くのではなく、
短時間・特定の授業・先生のいる時間帯だけなど、部分的な教室登校を組み合わせるという選択肢が浮かび上がります。
この「組み合わせ」は、本人のペースを尊重しながら、学校全体の雰囲気に触れるための非常に重要なステップになります。
別室を利用しつつも、必要に応じて教室との距離を少しずつ調整していく。
この柔軟さが、長い目で見て本人の負担を減らし、自己効力感(自分でできるという感覚)を育てることにつながります。
リモート授業は「継続的な関わり」をつくる手段
リモート授業は、不登校の子どもが学校との関わりを保つための有効な方法です。
しかし、ここでも重要なのは方法そのものではなく、参加する目的と気持ちの方向性です。
リモート授業は、
・身体的な負担が少ない
・教室の緊張感を避けられる
・授業内容の遅れを軽減できる
といった利点がありますが、同時に、
・緊張要素が少なすぎて学校との距離が広がる
・授業は見ていても学校生活には触れない
・参加しても達成感が生まれにくい
といった課題もあります。
これらはどちらが良い悪いではなく、本人の状態によって効果が変わるということです。
特に「親を安心させるための参加」であった場合、リモート授業は長期的なモチベーションに繋がりにくくなることがあります。
しかしながら、
「学習内容を理解したい」
「先生の声を聞くと落ち着く」
「同級生の様子を遠くから見ておきたい」
といった、自分なりの目的が見えている場合、リモート授業は学校との接点を保ち、その後の登校に向けた準備段階として機能しやすくなります。
つまり、リモート授業は「学校との距離感を自分なりに調整するための窓口」として扱うことが重要です。
親が感じる“期待”と“心配”の葛藤
保護者の方は、多かれ少なかれ、
「せめてリモート授業だけでも参加してほしい」
「これ以上遅れが広がると不安だ」
「完全に学校と離れるのは心配だ」
と感じるものです。
この気持ちは、決して押し付けではありません。
子どもの今後を考えれば当然の感情であり、そこに迷いや揺れがあっても不自然ではありません。
しかし、この“期待”がそのまま言葉になると、子どもは「失望させたくない」と考えやすくなります。
その結果、
・本心を隠す
・負担の大きい行動を続ける
・意欲が湧かないまま学校に関わる
といった状態が生まれ、行動はできていても、心理的には消耗していくことがあります。
このような状態は、専門的には「表面適応」と呼ばれます。
一見すると順調に見えるため周囲も安心しやすいのですが、本人の心の中では停滞や疲労が進んでいることがあります。
このような理由から、リモート授業や別室登校が続いている時ほど、
本人の気持ちがどこにあるのかを知るための対話
が必要になるのです。
「聞き出しの会話」ではなく「受け止めの会話」が必要
登校や授業参加について親が聞きたくなることは当然ですが、
「今日は参加できる?」
「別室には行けそう?」
という聞き方は、どうしても“判断を迫られる”形になりやすい傾向があります。
子どもは、自分の気持ちよりも“どう答えたら期待に応えられるか”を優先してしまいやすくなります。
そこで、会話を「確認」ではなく「共有」に切り替えることが大切になります。
例えば、
・最近の学校に対する印象
・授業の内容で気になる部分
・先生との関わりで安心できる点
・逆にまだ不安が残る点
などについて、ゆるやかな形で話をすることができれば、子どもの言葉の中に「次の一歩のヒント」が見つかります。
共有の会話では、結論を急がず、
「その気持ちは今の段階として自然なこと」
というスタンスを保つことが大切です。
この姿勢が、子どもに「自分の気持ちを話しても良い」という安全感を与え、結果として次に繋がる行動が自然に生まれます。
教室登校に繋がる“心理的プロセス”を理解する
教室に戻るためには、単に「慣れる」だけでは足りません。
子どもは、段階を踏みながら心理的に準備を整えています。
児童心理学では、このプロセスを以下のように整理できます。
1. 回避の理由が言語化される段階
学校が怖いのか、教室が緊張するのか、何が不安なのかを本人が自覚する段階です。
この段階では、行動よりも“気持ちを整理する時間”が大切です。
2. 自分ができる範囲を把握する段階
「別室なら大丈夫」
「リモートなら参加できる」
という形で、自分の限界や安心できる領域が明確になる段階です。
3. 小さな達成体験を積む段階
少しの時間、短い関わり、個別対応など、無理のない挑戦ができる段階です。
この段階では量より質が重要です。
4. 将来を見据えた目的意識が芽生える段階
高校進学、単位取得、友人関係など、具体的な理由が生まれてくる段階です。
ここで初めて“部分的な教室登校”が現実的になります。
5. 教室への自然なステップが踏める段階
本人の中で、精神的な準備が整い、行動が無理なく続けられる段階です。
別室登校やリモート授業は、このプロセスの途中にある“手段のひとつ”であって、ゴールではありません。
どの段階にいるのかを理解しておくと、焦りが減り、必要以上のプレッシャーをかけずに関われるようになります。
「部分的な教室登校」をどう扱うか
前半でも触れましたが、お子さんの中に、
「進路を考えると学校に慣れたい」
「授業は受けたい」
といった目的意識が見え始めたら、部分的な教室登校が選択肢に入ります。
部分的とは、
・特定の授業のみ
・短い時間だけ
・席ではなく後方から
・先生が声掛けしてくれるタイミングのみ
といったように、負荷を細かく調整した上で行う形です。
このステップは、お子さんの“意欲の方向性”が明確であるときに初めて意味を持ちます。
本人の気持ちよりも先に行動を押し出してしまうと、逆に後退することがあります。
そのため、部分的な教室登校を検討する際は、
「本人がどの段階にいるのか」
を丁寧に確認することが大切になります。
まとめ:視点を変えると、焦りは減り、見える景色が変わる
ここまで、別室登校とリモート授業を教室登校に繋げるための考え方を整理してきました。
大切なのは、方法そのものではなく、お子さんの気持ちです。
別室登校やリモート授業は、
・使い方次第で大きな力になる
・使い方を間違えると停滞の要因になる
という“両面性”を持っています。
そして、その違いを決めるのは、
「自分の意思で選んだ行動かどうか」
という一点です。
親御さんとしては不安が尽きないと思いますが、
視点を“行動”ではなく“気持ち”に向け直すと、見えてくる景色が変わります。
焦りが少し減り、子どものペースを理解しやすくなります。
お子さんがどんな距離感で学校と関わりたいのか、
その声を丁寧に受け取りながら、今できる一歩を一緒に考えていくこと。
それが、最終的に教室登校へと繋がるもっとも自然で、もっとも確かな道だと私は考えています。
【国内最多の登校支援実績】トーコについて
私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。
「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。
それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。
無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。