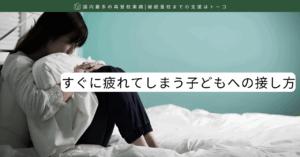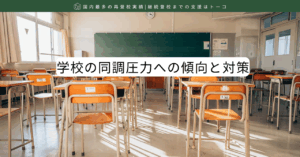親子間の適切な礼儀について
こんにちは。カウンセラーの竹宮と申します。
今日は「親子の礼儀」について、少し踏み込んでお話ししたいと思います。
不登校の相談を受けていると、子どもと親の距離感にまつわる悩みをよく伺います。中でも最近増えているのが、「親や兄弟に対して、子どもがきつい言葉を使う」「横柄な態度で見下すような話し方をする」といった声です。
こうした態度に対して、親としてどう向き合えば良いのか。厳しく叱るべきなのか、それとも受け流すのが良いのか。悩まれるのは当然のことだと思います。
一見、小さな口のきき方の問題に見えるかもしれませんが、実はこれは不登校の背景に潜む、もっと根深い問題とつながっていることもあります。
そこで今日は、
- 家庭内での礼儀とはどのような意味を持つのか
- 「仲が良ければ何でも許される」の落とし穴
- 子どもが家族を下に見るとき、心の中で何が起きているのか
- 親として、何を基準に線引きすればよいのか
といった点を整理しながら、親としての立ち位置を考えていきたいと思います。
目次
- 「親しき仲にも礼儀あり」は古い価値観なのか?
- 「子どもにへりくだる親」が抱える落とし穴
- 子どもが親を見下すようになる心理的背景
- 横柄な言動は「愛着のズレ」のサインでもある
- 「自由な言葉遣い」と「相手を貶める態度」は違う
- 「注意すべきかどうか」ではなく「何を軸に伝えるか」
- 親が「親であること」を放棄しない
- 関連記事
「親しき仲にも礼儀あり」は古い価値観なのか?
最近の育児論では、「子どもの自由を尊重しよう」「子どもを対等な存在として扱おう」という考え方が主流になっています。
その一方で、「家庭内での上下関係は必要ない」「親も子も対等だから、礼儀にこだわるのはナンセンスだ」という声もよく聞きます。
確かに、昔のように一方的に親が権威を振りかざし、子どもを従わせるやり方は、今の時代にはそぐわない部分もあります。子どもが親に気を遣ってばかりで本音を言えないような家庭では、心の安心も育ちにくいでしょう。
しかしながら、「親しき仲にも礼儀あり」という言葉が今もなお語り継がれているのには、それなりの理由があります。
礼儀とは、ただの形式ではありません。相手との距離感を大切にするための配慮です。
家庭は、子どもにとって一番安心できる場所であると同時に、人間関係の基本を学ぶ最初の場でもあります。ですから、そこで親を下に見るような態度が習慣化してしまうと、学校や社会で他者と接するときにも影響が出てくるのです。
たとえば、弟や妹に対して「お前はバカだな」などと日常的に言っている子は、クラスメイトに対しても無意識に似たような態度をとるようになります。
家庭内で許されていたことが、外の世界では通用しない。
そのギャップに戸惑い、人間関係がうまくいかなくなり、自信をなくす子も少なくありません。
「子どもにへりくだる親」が抱える落とし穴
もう一つよく見かけるのが、子どもが不登校になった後に、親が「この子を傷つけたくない」「なるべく刺激しないようにしよう」と考えて、必要以上にへりくだるケースです。
もちろん、子どもの心が繊細になっている時期には、無理に叱ったり正論をぶつけたりするのは逆効果になります。優しさや受け止める姿勢が必要な場面もあるでしょう。
ただ、だからといって、子どもが親に命令口調で話したり、侮るような態度を取っているのに何も言わないままでは、親子の力関係が逆転してしまいます。
たとえば、こんな場面を想像してみてください。
お母さんが夕飯の支度をしている最中、ゲームをしていた子どもが部屋から出てきて、「飯、まだ?遅いんだけど」と言い放つ。
このとき、「うん、もうすぐできるよ」とにこやかに返したとします。子どもが不登校で心の調子が悪いことを考慮しての、精一杯の対応だったのかもしれません。
けれど、これを繰り返していると、子どもの中で「自分が一番」「親は自分のために動いて当然だ」という認識が強まっていきます。
このような思考のクセが定着してしまうと、学校に戻ったときや、将来的に社会に出たときに、他者との対等な関係が築きづらくなるのです。
子どもが親を見下すようになる心理的背景
ここで一つ、子ども側の視点にも目を向けてみましょう。
なぜ子どもは、親に対して横柄な態度をとるようになるのでしょうか。
これは単純に「反抗しているから」でも、「性格が悪いから」でもありません。
児童心理の観点から見ると、こうした態度は「不安」や「無力感」の裏返しであることが多いのです。
不登校になってしまったことで、子どもは自分に対する評価や存在価値に揺らぎを感じています。「自分はダメな人間なんじゃないか」「何もできないのではないか」という不安を抱えているのです。
その不安を抱えたまま過ごすことは、とても苦しいことです。
だから、自分の優位性を感じられる相手(つまり親)に対して強く出ることで、一時的にその不安を打ち消そうとする。
これは一種の防衛反応です。
親を見下すような態度は、「自分が弱っている」と感じている子どもが、「弱さを隠すために力を誇示している」ような状態とも言えます。
もちろん、それが許されるわけではありません。
でも、ただ叱って抑え込もうとするのではなく、なぜその態度を取っているのかという心の背景を理解しておくことは、対応を考えるうえでとても重要です。
横柄な言動は「愛着のズレ」のサインでもある
もう一つ見落とされがちなのが、家庭内での力関係が逆転しているとき、そこには「愛着のズレ」が存在している可能性があるという点です。
心理学における「愛着(アタッチメント)」とは、子どもが特定の養育者に対して築く、安心感の土台のようなものです。これは言い換えると、「この人に守られている」「この人となら大丈夫だ」と感じる心の基盤です。
本来、子どもは親に対して「守られる側」であり、親は「守る側」です。
ところが、不登校が長引いたり、子どもに過度に気を遣いすぎる生活が続くと、この役割が少しずつ曖昧になります。すると、子どもの中で「親は自分より下の存在だ」といった誤った位置づけが生まれてしまうことがあります。
このズレが、横柄な態度や失礼な言動となって表面化するのです。
たとえば、親が何か提案したときに「うるさいな。あんたに関係ないでしょ」と返す。これは、単なる反抗ではなく、「お前は黙ってろ」と同義で、上下の逆転が起きているということです。
そして、これは一時的なものでは済みません。長く続けば続くほど、家庭という場が「安心の場」ではなく、「自分が支配する場」になってしまい、対人関係の基礎が大きく歪みます。
「自由な言葉遣い」と「相手を貶める態度」は違う
ここまでの話を聞くと、「じゃあ、家の中でも常に丁寧な言葉を使わせなきゃダメなのか」と感じられる方もいるかもしれません。
けれど、そうではありません。
家族同士、多少砕けた言葉を使ったり、冗談交じりの会話があること自体は、何も問題ではありません。むしろ、そうした垣根のない関係性が、家庭に温かさや安心感をもたらしてくれます。
ただし、注意すべきは「相手を下に見る言い方かどうか」という点です。
たとえば、
- 「お母さん、さっきの言い方ムカついたんだけど」
- 「は?何言ってんの?うざいんだけど」
- 「黙ってて。意味ないから話しかけないで」
このような言葉は、冗談では済まされません。明らかに相手を攻撃する意図を含んでおり、「親を見下しても構わない」という無意識の認識が前提にあるからです。
もちろん軽口や、日常のやり取りの中でのふざけた発言が一概に悪いわけではありません。言葉自体よりも、背後にある関係性が大切です。
つまり、同じような言葉でも、「相手に敬意を持っているかどうか」で意味合いが変わってくるということです。
「注意すべきかどうか」ではなく「何を軸に伝えるか」
ここまでの話を踏まえると、「親に対して横柄な態度を取る子どもに注意すべきかどうか」という問いに対しては、「注意は必要。ただし、どう伝えるかが大事」という答えになります。
大切なのは、叱責や命令口調で「やめなさい」と言うのではなく、
- それがなぜ問題なのか
- 相手がどう感じるか
- どうすれば対等な関係が築けるのか
といった点を、冷静かつ具体的に伝えていくことです。
たとえば、
「今の言い方、私は少し悲しかったよ。言いたいことがあるのはわかるけど、もう少し違う伝え方ができたら嬉しいな。」
といった一言でも、子どもは「言葉の持つ力」に気づきやすくなります。
一度で変わるわけではありません。でも、繰り返し、落ち着いたトーンで伝えることで、少しずつ子どもの中にも「相手を思いやる」という視点が芽生えてきます。
そしてその視点は、学校での友人関係、将来の職場、パートナーシップにも必ず活かされます。
親が「親であること」を放棄しない
不登校という状況の中で、子どもを守りたいという思いが強くなるのは、ごく自然なことです。
けれど、親が「嫌われたくない」「これ以上崩れたくない」という不安から、自分の役割を放棄してしまうと、子どもの中に「この人は自分の下だ」という誤った認識が生まれてしまいます。
子どもを尊重することと、子どもに気を遣いすぎることは違います。
家庭の中での最低限の礼儀は、人間関係の基礎となるものです。だからこそ、子どもの態度が明らかに相手を下に見ているようなものであれば、それは親として、冷静に線を引くべき場面です。
逆に言えば、そこにきちんと向き合える親こそが、子どもにとって本当の意味で「安心できる存在」になります。
関連記事
【国内最多の登校支援実績】トーコについて
私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。
「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。
それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。
無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。