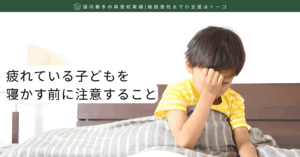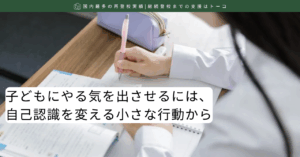自己肯定感が低いとモチベーションが生まれにくい理由
こんにちは。カウンセラーの竹宮と申します。
今日は「自己肯定感とモチベーションの関係」についてお話ししたいと思います。
このテーマは、不登校のお子さんを持つ保護者の方から日常的に寄せられるご相談と深く関係しています
「うちの子、やる気がないみたいで」
「どうしたら前向きになってくれるのでしょうか」
こうした問いかけをいただくたび、世の中で当たり前のように使われている「やる気」や「モチベーション」という言葉の意味を考えさせられます。
一見前向きな言葉の裏に、子どもたちを追い詰めてしまう構造が隠れていることもあります。
今回は、そのような現実を一緒に見つめながら、少し気持ちが軽くなる考え方をご紹介できたらと思います。
目次
- よくある「やる気を出そう」というアドバイス
- モチベーションの正体を見つめ直す
- コンフォートゾーンという考え方
- 自己肯定感が低いと、なぜモチベーションが出にくいのか
- 「頑張るエネルギー」が湧かないのは、自然なこと
- ポジティブ思考だけでは、かえって苦しくなる
- 「本当はもっとできるのに」を見逃さない
- モチベーションの新しい捉え方
- 気持ちを少し軽くするために
- 関連記事
よくある「やる気を出そう」というアドバイス
「前向きに考えてほしい」と願う気持ち
子どもが学校に行きたがらない。
何かに取り組もうとしない。
そんな姿を見ていると、「なんとかやる気を出してほしい」と思うのは当然のことです。
保護者の方がかける「頑張ってみようよ」「前向きに考えようよ」という言葉には、愛情が込められています。子どもに力を貸したい。元気を取り戻してほしい。そうした親心が背景にあることは、私もよく分かります。
ただし、このアドバイスが本当に子どもの助けになっているかというと、そこには慎重に目を向ける必要があります。
正しいアドバイスが、負担になることも
「やる気を出して」「前向きになろう」といった言葉は、学校でもテレビでも、よく聞くフレーズです。ポジティブ思考が良いことだという価値観は、すっかり社会に浸透しています。
しかし、その価値観に子ども自身がついていけないとき、「自分はダメなんだ」と思わせてしまうことがあります。
たとえば、朝どうしても起き上がれない子どもに、「今日こそ頑張って学校行こう」と声をかけたとします。一度なら、子どもも「うん、頑張ってみようかな」と思うかもしれません。
でも、それが何度も続くとどうでしょうか。
「またダメだった」
「私はやっぱりできない」
「やる気が出せない自分が悪い」
このように、自分を責める気持ちが積み重なっていくことが少なくありません。
モチベーションの正体を見つめ直す
モチベーションは「頑張る力」ではない
そもそも「モチベーション」という言葉には、「前向きになること」や「やる気を出すこと」といった印象があるかもしれません。
しかし、心理学的にモチベーションは「プラスに向かって進む力」ではなく、「現在の不快や不安を解消しようとする自然な動き」として捉えるほうが、実態に近いです。
もう少しかみ砕いて言えば、「何かがおかしい」「このままでは嫌だ」と感じたときに、それを元に戻そうとする力のことです。
たとえば、部屋が散らかっていて落ち着かないとき、片付けたくなる。
お腹が空いているとき、食べたくなる。
こうした自然な行動も、立派なモチベーションの一種です。
本当のモチベーションは「違和感」から生まれる
人が動こうとする原点には、「なんとなくおかしい」という違和感があります。
「もっと自分らしくいたい」
「このままじゃいけない気がする」
そんな微細な感覚が、変化のきっかけになることがあります。
このとき、モチベーションは「前向きに頑張るぞ」と無理やり奮い立たせるものではなく、「自分の中のズレを整えようとする自然な反応」だと考えるほうが、腑に落ちやすいのではないでしょうか。
コンフォートゾーンという考え方
コンフォートゾーンとは何か
ここで一つ、心理学の用語を紹介します。
「コンフォートゾーン」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
これは簡単に言えば、「自分にとって心地よく、安心していられる状態や場所」のことです。
たとえば、自宅のリビング、気の合う家族との会話、慣れた手順で行う家事などがこれにあたります。
人は本能的に、このコンフォートゾーンに留まろうとします。そして、そこから外に出ることには、強いストレスを感じます。
コンフォートゾーンは“甘え”ではない
子どもが学校に行きたがらず、家で過ごすことを選んでいるとき、それを「怠けている」と捉える方もいます。
けれど、安心できる場所に戻ろうとする行動は、人間としてごく自然なものです。むしろ、コンフォートゾーンに戻ることで、心や体を回復させている可能性もあります。
たとえば、仕事で疲れた日の夜、誰とも話したくなくてテレビをぼんやり見ていたくなることはありませんか。
それと同じように、子どもにとっての「今は何もしたくない」という状態も、回復のために必要な時間だと捉えることができます。
動き出すきっかけは「違和感」から
重要なのは、そのコンフォートゾーンにずっと留まっているとき、「このままでいいのかな」「何かが物足りない」といった小さな違和感が芽生える瞬間です。
この違和感こそが、モチベーションの原点です。
「本当は友達に会いたい」
「ちょっと勉強してみたくなった」
こうした内側から湧いてくる動きが出てきたとき、その子はすでに自分なりのペースで一歩を踏み出そうとしているのかもしれません。
自己肯定感が低いと、なぜモチベーションが出にくいのか
自己肯定感とは何か
自己肯定感とは、「自分には価値がある」と感じられる気持ちのことです。
自分の存在や行動を、他人と比べずに素直に認められる力とも言えます。
自己肯定感が高い人は、失敗しても「またやればいい」と考えられます。できなかったことより、できたことに目を向けることができます。
しかし、自己肯定感が低いと、「やっぱり自分はダメだ」と思いがちです。うまくいかなかったときに、自分を責めてしまいやすくなります。
「やったことを認められない」感覚
実際に不登校の子どもたちと話していると、「自分ができたことを、認めるのが苦手」という声をよく聞きます。
たとえば、家の手伝いをしても、「そんなの当たり前だから」
絵を描いて褒められても、「どうせみんなに合わせて言ってるだけ」
このように、せっかくの成果や行動を、自分のものとして受け止められないケースが多いのです。
これは、「結果を出しても、認められるには足りない」という感覚が、根っこにあるからです。
このような感覚は、大人の中にもあります。
たとえば、毎日料理や洗濯をしていても、「私は何もしていない」と感じてしまうことはないでしょうか。家族に感謝されても、「そんなの大げさよ」と受け流してしまう。
それと同じように、子どもも「自分はまだまだ」「やる気を出すにはもっと成果が必要」と思い込んでしまうことがあります。
この考えが強まるほど、自分に期待ができなくなり、結果としてモチベーションが湧いてこない状態になります。
「頑張るエネルギー」が湧かないのは、自然なこと
「どうせ無理だ」と感じてしまう心理
自己肯定感が低い状態では、「頑張っても報われない」「やっても意味がない」と感じやすくなります。
たとえば、学校に行ってみたいと思っても、
「行ってもまたついていけないだろうな」
「先生に変な目で見られるかもしれない」
そんな不安が先に立ちます。
たとえ「できるようになりたい」という気持ちがあっても、「きっと無理だ」と思ってしまえば、動くことはできません。
ここで大切なのは、「動けないのは甘えではない」という視点です。
「やる気を出そう」と言われても動けない理由
「やる気を出して」と言われたとき、それが心に響くには、前提条件があります。
それは、「自分にもできるかもしれない」という期待感が、少しでも心の中にあることです。
しかし、自己肯定感が低いと、その前提が存在しません。
「どうせまたダメだろう」
「期待されても、応えられない」
こうした感覚に覆われている子どもにとって、「やる気を出せ」という言葉は、単なる重荷になってしまいます。
モチベーションの源である「違和感」を見落とさない
子どもが「なんかおかしい」と感じる瞬間は、たしかにあります。
たとえば、友達の話を聞いて「楽しそうだな」と思う。
テレビで運動会の様子を見て「自分も参加したかったな」と感じる。
これらはすべて、内側にある「もっとこうありたい」という違和感です。
ただし、自己肯定感が低いと、その違和感をすぐに行動に結びつけることができません。「そう感じても、自分にはできない」と、ブレーキがかかってしまいます。
このとき必要なのは、「その違和感を、否定しないこと」です。
ポジティブ思考だけでは、かえって苦しくなる
「前向きに考えよう」は万能ではない
「ポジティブに考えよう」「前を向こう」という言葉は、確かに励ましとして機能することもあります。
しかし、気持ちが落ちているときに、それを求められると、逆にしんどくなることもあるのです。
たとえば、寝不足で体が重く、気持ちも沈んでいる朝。
そんなときに「さあ、今日も明るくいこう!」と言われても、正直なところ、ついていけないのではないでしょうか。
これは子どもも同じです。
無理にポジティブを目指すと、現実とのギャップに苦しむ
「もっとポジティブにならなきゃ」
「こんな自分じゃだめだ」
このように、自分を奮い立たせようとすればするほど、「できない自分」との落差が苦しくなります。
実際には、気持ちが沈んでいるときに一番必要なのは、「今の自分をそのまま認めてあげる」ことかもしれません。
「こんな気分のときもある」
「今日は何もしなくてもいい」
そう思える時間を確保できて初めて、次の行動への余白が生まれていきます。
「本当はもっとできるのに」を見逃さない
違和感は、行動の種になる
私自身、日々のカウンセリングで大切にしているのは、「子どもが発した小さな違和感」に耳を傾けることです。
「ずっと休んでるけど、ちょっと退屈」
「最近、〇〇ちゃん元気かなと思うときがある」
このような何気ない言葉の中に、行動のきっかけとなる気配が含まれていることがあります。
保護者の方も、「あの子、本当はもっとできるはずなのに」と感じることがあるかもしれません。ですが、それは「だからもっと頑張って」という意味ではありません。
むしろ、その違和感を尊重し、焦らず見守ることが、子どものモチベーションの再起動にとって大きな意味を持ちます。
日常の中で生まれる「もっとこうしたい」
違和感は、日常のあらゆる場面に隠れています。
たとえば──
料理をしていて、今日はうまくいかなかった。
それを「もう少し丁寧にやればよかったかな」と思う。
この気持ちは、失敗を責めているのではなく、自然と「次はうまくやりたい」という感覚につながっています。
子どもも同じです。
「テレビばかり見ていたけど、なんか飽きてきた」
「昨日、昼まで寝ていたけど、今日は少し早く目が覚めた」
こうした感覚を、自分で捉えることができたとき、少しずつモチベーションが芽生えていきます。
モチベーションの新しい捉え方
「頑張ること」を目的にしなくていい
よく「やる気が出たら行動できる」と考えられがちですが、実際はその逆です。
「動いてみたら、少し気持ちが変わった」
「やってみたら、悪くなかった」
そうした経験が積み重なって、少しずつやる気が戻ってくるものです。
モチベーションを、「一気に自分を変えるための力」と捉える必要はありません。
むしろ、「ちょっとだけ動いてみようかな」と思える瞬間を大切にすることが、現実的で効果的です。
小さな一歩をちゃんと認めること
自己肯定感が低い状態では、行動したとしても「これくらい当たり前」と思いがちです。
ですが、たとえば──
今日は5分だけ早く起きられた。
昨日より少しだけ声が大きく出せた。
家族に「ありがとう」と言えた。
こうした一つひとつの行動には、大きな意味があります。
最初の一歩は、いつも小さくてかまいません。
そして、その一歩を「よくできたね」と認めることが、次の一歩の後押しになります。
気持ちを少し軽くするために
今日は、「自己肯定感が低いと、なぜモチベーションが生まれにくいのか」について考えてみました。
私が大切にしたいのは、「モチベーションは、頑張るためのエネルギーではない」という視点です。
むしろ、モチベーションとは、「何かが足りない」「今の自分には合っていない」と感じたときに、それを埋めようとする自然な反応です。
そして、その反応が起こるには、まず「自分の今」をそのまま受け止める土台が必要です。
モチベーションを無理に出させようとするのではなく、
違和感に気づき、それを否定せずに見つめる。
その繰り返しが、自己肯定感を少しずつ高め、やがて「やってみようかな」という気持ちを生み出してくれます。
明確な正解があるわけではありません。
でも、少し見方を変えることで、心がふっと軽くなることがあります。
そんな小さな変化を、大切にしていただけたらと思います。
関連記事
【国内最多の登校支援実績】トーコについて
私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。
「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。
それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。
無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。