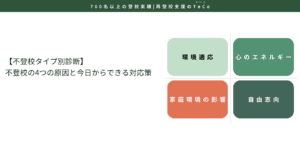不登校の子どもの進路選択ガイド:高校・大学・就職、後悔しないための道筋とは?
不登校や引きこもりの問題に取り組む児童心理司の竹宮と申します。私は、不登校予防や再登校支援を行うToCo(トーコ)の顧問を務めております。
お子様が不登校の状態にあると、進路についての悩みは尽きないことと思われます。「このままでは高校に行けないのでは?」「大学進学や就職はできるのだろうか?」と、不安を感じる保護者の方も多いはずです。しかし、焦って誤った選択をすると、お子様の将来に大きな影響を及ぼす可能性があります。
本稿では、不登校のお子様の進路選択について、後悔しないための道筋を詳しく解説します。高校・大学・就職のそれぞれの選択肢と、不登校からの回復を前提とした進路の選び方について、具体的なアプローチをお伝えします。
目次
1. 不登校が進路選択に与える影響
まず、不登校の経験が進路選択にどのような影響を及ぼすのかを正しく理解することが重要です。不登校の期間が長引くと、学力の遅れ、対人関係の困難、自己肯定感の低下など、さまざまな問題が生じます。これらが進路選択にどのように関わるのか、具体的に見ていきましょう。
1-1. 学力の遅れと進学への影響
不登校の間は学校の授業を受けていないため、学力が低下することが多く、特に主要科目(国語・数学・英語など)において大きな影響を受けることがあります。
たとえば、中学時代に不登校だった生徒が高校進学を考えた際、内申点の不足や学力試験のハードルが問題になります。全日制高校は一定の学力を求めるため、学習の遅れを取り戻さなければ選択肢が狭まります。また、大学進学を考える場合、高校時代の成績や受験勉強の影響を受けるため、不登校の影響が長期にわたって残る可能性があります。
1-2. 社会性の発達と就職への影響
学校に通わない期間が長くなると、対人関係の構築が難しくなることがあります。特に、集団生活に適応する力が低下し、コミュニケーションを避ける傾向が強まることが多いです。
就職の際には、学歴だけでなく「コミュニケーション能力」や「協調性」などが重視されます。不登校の影響で人間関係を築くのが苦手になっていると、就職活動や職場での適応に苦労するケースもあります。
1-3. 自己肯定感の低下と選択肢の制限
長期間の不登校経験があると、「自分は何をやってもダメだ」と感じ、自己肯定感が低下しやすくなります。すると、新しい挑戦を避ける傾向が強まり、進学や就職に対して消極的になってしまうことがあります。
進路選択は、本人が「やってみよう」と思えるかどうかが重要です。自己肯定感が低い状態では、挑戦する意欲が湧かず、結果として選択肢が狭まってしまうのです。
このように、不登校は進路選択にさまざまな影響を及ぼします。しかし、適切な支援を受けながら準備を進めることで、不登校の影響を最小限に抑え、希望する進路を目指すことが可能です。
2. 不登校の子どもが高校進学を目指す際の選択肢
不登校のお子様が高校進学を目指す場合、大きく分けて「全日制高校への進学」「通信制・定時制高校への進学」の2つの選択肢があります。それぞれの特徴と、お子様の状況に応じた適切な選び方について解説します。
2-1. 全日制高校への進学
多くの保護者の方がまず考えるのが、一般的な全日制高校への進学でしょう。不登校経験があっても、全日制高校に進学することは十分に可能です。ただし、学校選びと準備が非常に重要になります。
(1)進学のためのハードル
- 内申点の影響
中学時代に不登校が長引くと、成績がつけられず、内申点が低くなりがちです。多くの公立高校では内申点を重視するため、不登校期間が長かった場合、一般入試の選択肢が狭まることがあります。 - 学力試験への対応
受験科目の学習が十分に進んでいない場合、一般入試での合格が難しくなります。そのため、学習の遅れを取り戻すことが必要になります。 - 面接や作文の重要性
不登校経験がある場合、面接や作文試験で「なぜ不登校だったのか」「高校でどのように過ごしたいか」を問われることがあります。ここでしっかりとした回答ができるよう準備が必要です。
(2)不登校生を受け入れやすい高校の特徴
最近では、不登校経験者を積極的に受け入れる高校も増えてきています。こうした高校には、以下のような特徴があります。
- 特別支援体制が整っている
カウンセリングや個別指導が充実しており、不登校経験者が安心して通学できる環境を提供している。 - 出席扱い制度を活用できる
たとえば、フリースクールや家庭学習の一部を「出席」として認める制度を採用している学校もあります。 - 学び直し支援が充実している
学力補充のための特別クラスや、個別指導のプログラムがある。

2-2. 通信制高校・定時制高校への進学
不登校経験が長く、全日制高校への進学が難しい場合、通信制高校や定時制高校を選ぶケースもあります。
(1)通信制高校の特徴
通信制高校は、通学の負担を減らしながら高校卒業資格を取得できる仕組みになっています。
- 自宅学習が基本:レポート提出やオンライン授業で単位を取得する形式。
- スクーリング(登校日)が少ない:週1回程度の登校が求められる学校もあるが、全日制よりは負担が軽い。
- 学習のペースを自分で調整可能:不登校経験がある生徒でも、無理なく学習を進められる。
ただし、通信制高校は自主学習が基本のため、自己管理能力が求められます。「学習のモチベーションが続かない」「誰かのサポートがないと勉強が進まない」といったタイプのお子様には、十分なサポート体制があるかを確認することが大切です。
(2)定時制高校の特徴
定時制高校は、夕方から夜にかけて授業が行われるスタイルの高校です。
- 対面授業が中心:通信制と異なり、基本的には学校に通いながら授業を受ける。
- 学力不問で入学できる学校もある:一部の公立定時制高校は、学力試験なしで入学できる。
- 社会人や年齢の異なる生徒と学ぶ機会がある:異年齢の人と交流できるため、社会性を身につける場にもなる。
2-3. 進学のために必要な準備
お子様が高校進学を希望する場合、不登校の状況から抜け出し、学習のリズムを取り戻すことが必要不可欠です。そのために、以下のような取り組みが有効です。
- 学習習慣をつける
- まずは1日30分でも良いので、学習時間を確保する。
- 不登校期間が長い場合、基礎学力(小学校レベルからの復習)を重視する。
- 再登校の準備をする
- 高校進学後の環境変化に適応できるよう、徐々に外出や他者との交流機会を増やしていく。
- 再登校支援サービスを活用し、無理のない形で学校生活へ戻る準備を進める。
- 志望校の情報を集める
- 学校説明会やオープンキャンパスに積極的に参加し、お子様に合う環境かどうかを確認する。
- 進学後に続けられるかどうかを第一に考え、通学時間やサポート体制を重視する。
不登校の期間が長くても、高校進学は十分に可能です。ただし、進学後に再び学校に行けなくなるケースを防ぐために、「高校に入ること」ではなく「高校生活を続けること」を意識した準備が必要です。
3. 不登校からの大学進学
不登校を経験したお子様が大学進学を目指す場合、高校以上に「自分に合った学びの環境」を見極めることが重要になります。不登校経験があるからといって大学進学が難しいわけではありませんが、適切な準備をしないと、進学後に授業に出られなくなるなどの問題が生じる可能性があります。本章では、不登校経験者の大学進学の選択肢と、成功するためのポイントを解説します。
3-1. 不登校経験者が大学進学を目指す際のハードル
大学進学に向けた道のりは、不登校の期間や理由によって異なりますが、以下のような共通する課題があります。
- 学力不足の問題
高校時代の不登校期間が長かった場合、受験科目の学習が十分にできていない可能性があります。特に、一般入試では高校3年間の内容を問われるため、基礎学力が不足していると合格が難しくなります。 - 受験方式の選択
不登校経験者の場合、一般入試よりも総合型選抜(旧AO入試)や推薦入試を活用したほうが合格しやすいことがあります。これらの入試では、学力試験よりも面接や志望理由書が重視されるため、不登校経験を前向きに伝えることができれば有利になる可能性があります。 - 大学進学後の適応
高校と異なり、大学は自主的に学ぶ場です。不登校経験があると、「講義に出席できない」「課題を計画的に進められない」などの問題に直面することがあります。そのため、進学前に学習習慣や生活リズムを整えておく必要があります。
3-2. 大学進学の選択肢
不登校を経験したお子様が大学進学を目指す場合、以下のようなルートがあります。
(1)一般入試(学力試験)
一般入試は、共通テストや各大学の個別試験を受けて合格を目指す方法です。
- メリット:受験対策をしっかり行えば、どの大学にも挑戦できる。
- デメリット:学力試験がメインのため、不登校期間が長く学習が遅れている場合は不利。
(2)総合型選抜(旧AO入試)
学力試験よりも「学ぶ意欲」や「将来の目標」を重視する入試方式です。
- メリット:不登校経験を逆に強みに変えられる。面接や志望理由書で「なぜ大学で学びたいのか」をしっかり伝えることができれば合格の可能性が高まる。
- デメリット:志望理由の記載難易度が高い。面接の準備に時間がかかる。
(3)推薦入試(学校推薦型選抜)
高校の推薦を受けて出願する入試方式。公募制推薦(学力試験あり)と指定校推薦(試験なし)の2種類がある。
- メリット:指定校推薦であれば、基本的に合格が保証される。
- デメリット:内申点や高校での成績が重視されるため、不登校期間が長かった場合は選択肢が限られる。
(4)オンライン大学・通信制大学
通学が難しい場合、オンラインで学位を取得できる大学を選ぶという方法もある。
- メリット:自宅で学習できるため、不登校経験があっても無理なく進学できる。
- デメリット:自主的に学習を進める必要があるため、自己管理能力が求められる。
3-3. 大学進学のために必要な準備
大学進学を成功させるためには、単に合格するだけでなく、入学後に継続して学べる環境を整えることが重要です。
- 学習習慣を取り戻す
- まずは、毎日決まった時間に学習する習慣をつける。
- 大学受験を考える場合、高校の基礎科目を重点的に復習する。
- 志望理由を明確にする
- 特に総合型選抜を利用する場合、「なぜこの大学で学びたいのか?」を具体的に言語化できるようにする。
- 過去の不登校経験をどのように乗り越え、今後に生かしたいかを整理する。
- 再登校支援を活用する
- 大学進学後に学び続けるためには、生活リズムを整え、通学への不安を解消することが重要。
- 一部の民間サービスや塾では、大学進学を見据えた学習サポートや生活改善のプログラムを提供している。
4. 不登校経験者の就職
高校や大学に進学せず、直接就職を目指す場合、不登校経験が社会での適応に影響を及ぼすことがあります。不登校経験者の就職活動には特有の課題があり、これを理解し適切な準備をすることが重要です。
4-1. 不登校経験者が就職で直面する課題
不登校のまま社会に出る場合、次のような課題に直面しやすくなります。
- 履歴書の空白期間の説明が必要
就職活動では、履歴書や面接で「なぜ高校や大学に通わなかったのか?」を問われることが多く、不登校の期間をどのように説明するかが重要になります。正直に話すことは大切ですが、単に「学校に行けなかった」と伝えるだけでは不利になりやすいため、「その期間に何をしていたのか」「今はどう向き合っているのか」を前向きに説明する準備が必要です。 - 対人スキルの不足
学校生活を通じて培われる「人と関わる経験」が不足しているため、職場での人間関係に不安を感じることが多いです。特に、上下関係のある環境に馴染めず、職場のルールやコミュニケーションの壁を感じるケースが少なくありません。 - 継続的に働くことが難しくなる可能性がある
不登校が長引いた場合、「継続的に働くこと」そのものに心理的なハードルを感じることがあります。たとえば、「決まった時間に出社するのが苦痛」「仕事のストレスに耐えられない」「同僚と馴染めずに孤立する」といった問題が発生することがあります。
4-2. 不登校経験者の就職に向けたフォローアップ
上記の課題を持っていても、適切な準備をすれば就職の道は開かれています。ここでは、主な就職ルートについて詳しく説明します。
(1)職業訓練校を活用する
職業訓練校(ハロートレーニング)は、実践的なスキルを身につけながら、就職に必要な知識を学べる機関です。特に、不登校経験者にとって、専門スキルを身につけることで「学歴」ではなく「能力」で評価される道を作ることができます。
- メリット:学歴が不問で、実践的なスキルを短期間で習得できる。
- デメリット:受講期間中のモチベーション維持が必要。
特に、IT、介護、調理、デザイン、製造業など、手に職をつけられる分野は、不登校経験があっても成果を出しやすい仕事が多く、就職に結びつきやすい傾向があります。
(2)インターンシップやアルバイトから始める
いきなり正社員として働くことが難しい場合、アルバイトやインターンシップを通じて、仕事に慣れていく方法があります。
- メリット:社会経験を積みながら、自分に合った仕事を見極めることができる。
- デメリット:正社員への道が保証されるわけではないため、キャリアアップの道を考える必要がある。
コンビニや飲食店、工場、倉庫作業など、比較的ハードルの低い職種から始め、徐々に社会での適応力を高めていくのが有効です。また、アルバイト先で評価され、正社員登用されるケースもあります。
(3)就労支援サービスを利用する
不登校経験者や引きこもり状態にある若者向けの就労支援サービスを活用することで、段階的に社会復帰することが可能です。
- メリット:専門家のサポートを受けながら、無理なく就職活動を進められる。
- デメリット:支援機関によってサービス内容に差があるため、自分に合ったプログラムを選ぶ必要がある。
ToCoでは、再登校支援だけでなく、社会復帰に向けたサポートも行っています。たとえば、「企業訪問」や「職場体験」などを通じて、実際の職場環境を知り、仕事への不安を軽減するプログラムを提供しています。
(4)資格取得を目指す
学歴ではなく、資格を武器にすることで、就職の選択肢を広げることができます。特に、不登校経験がある方には、以下のような資格取得を目指すのがおすすめです。
- IT系資格(ITパスポート、基本情報技術者試験など):オンラインで学べるため、自宅学習でも取得可能。
- 医療・介護系資格(介護職員初任者研修、登録販売者など):資格を取得すれば、未経験からでも就職しやすい。
- クリエイティブ系資格(Webデザイン、動画編集、イラスト制作など):フリーランスや在宅ワークの道も開ける。
4-3. 就職成功のために必要な準備
不登校経験者が就職を成功させるためには、単に「仕事を探す」だけでなく、社会に適応するための準備が不可欠です。
- 生活リズムを整える
- 毎朝決まった時間に起きる習慣をつける。
- 週に数回でも外出する機会を増やし、人と接することに慣れる。
- コミュニケーション能力を向上させる
- 家族や信頼できる人と積極的に会話する。
- ボランティア活動や地域のイベントに参加し、人と関わる機会を作る。
- 履歴書・面接対策を行う
- 不登校期間について、前向きに説明できるようにする。
- 模擬面接を受けて、話し方や表情に慣れる。

5. まとめ——後悔しない進路選択のために
不登校からの進路選択は、「どこに進むか」だけでなく、「その進路をどのように進んでいくか」が重要です。そのために、以下の点を意識してください。
- 現在の状態を正しく把握し、焦らずに進路を考える
- 短期的な目標と長期的な目標を分けて考える
- お子様の得意なことや興味のあることを活かす
- 進路を決めた後の準備をしっかり行う
大切なのは、「お子様がなるべく後悔しない選択をすること」です。一歩ずつ着実に前に進めるよう、環境を整え、支援を活用しながら、お子様と一緒に最適な選択を見つけていきましょう。
【国内最多の登校支援実績】トーコについて
私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。
「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。
それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。
無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。