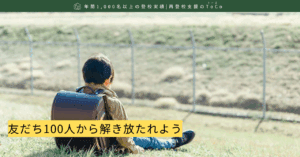子どもが将来の夢を、職業で語ることのリスク
こんにちは。ToCoの不登校カウンセラー、竹宮です。
今日は「将来の夢を職業でしか語らない日本」というテーマで書いていきます。
お子さんが不登校になったとき、保護者の方は「この子は将来、どうやって生きていくんだろう」と不安になることがあると思います。
とくに、将来のことを考えるタイミングで「夢は何?」「どんな仕事がしたいの?」という話が出てくると、そこでつまずいてしまう子も多いんです。
でも、ここにはひとつ、大きな落とし穴があります。
目次
「夢=職業」という前提が苦しさを生む
日本では、小学校の頃から「将来の夢は?」と聞かれることがよくあります。
多くの子どもは「サッカー選手」「ケーキ屋さん」「お医者さん」などと答えます。
もちろん、これは悪いことではありません。
職業を夢として語るのは、わかりやすくて、答えやすいからです。
でも中学生、高校生になっても、「将来の夢は職業の名前で言うものだ」という感覚が強く残ってしまうと、次のような悩みにぶつかります。
- どんな仕事がしたいかわからない
- 特別に好きなことがない
- 好きなことが仕事になるイメージが持てない
- 職業で語れない夢は「ダメな夢」だと感じてしまう
この時点で、「夢を持っていないといけない」「将来の目標がないのはおかしい」と自分を責めてしまう子がいます。
不登校と「夢=職業」プレッシャーの関係
実はこの構造は、不登校とも深く関係しています。
不登校の背景には、「学校の中で自分の価値を見いだせなかった」という思いがある子が多いです。
そんな中で「夢=職業」「職業=社会で役立つこと」という考え方が刷り込まれると、こう感じてしまうのです。
「学校にも行けてない自分が、将来の夢を語るなんて…」
「どうせ何者にもなれない」
これは、とても危険な考え方です。
なぜなら、「夢がない=ダメな自分」と無意識に思い込んでしまうからです。
よくあるアドバイスが、逆効果になるとき
「将来の夢を持とう」
「目標があれば頑張れるよ」
「夢があれば学校にも行けるようになるかもね」
こうした言葉は、悪気なく言われがちなアドバイスです。
でも、これが子どもにとっては大きなプレッシャーになることがあります。
たとえば、今は部屋から出るのもしんどい子にとって、「将来」や「夢」を問われるのは、100m先にあるものを指差されて「今すぐ走れ」と言われているようなものです。
「夢=職業」しか見えていないと、夢が遠くなる
たとえば、「人の役に立ちたい」と思っている子がいたとします。
それを「看護師」「介護士」「先生」といった職業に直結させようとすると、急にハードルが上がってしまいます。
でも、「まずは家の中で、自分にできることで人を喜ばせてみる」ことだって、その夢の一歩です。
夢は、職業だけではなく、あり方・価値観・生活スタイルにも表れるものです。
「こうなりたい」が最初にあって、その後に必要なスキルや手段がついてくることもあるのです。

「職業としての夢」にしがみつくリスク
ここまで、「将来の夢は職業で語るべきだ」という前提が、子どもにプレッシャーを与えることについて書いてきました。
ここからは、その「職業としての夢」が持つリスクを、もう少し掘り下げて考えてみたいと思います。
「夢が壊れる」ことのダメージ
職業としての夢を持つこと自体は悪いことではありません。
ですが、それを唯一の正解のように子どもに提示すると、失敗や挫折が起きたとき、子どもは「自分の存在そのものが否定された」と感じやすくなります。
たとえば、
- 声優になりたい → オーディションに受からなかった
- 看護師になりたい → 成績が届かない
- プログラマーになりたい → 数学が苦手だった
このとき、職業としての夢が「アイデンティティ」と直結していると、夢が崩れた瞬間に「自分も崩れる」ような感覚に陥ります。
この感覚が強いほど、立ち直るのに時間がかかります。
特に、自己評価がもともと低い子や、周囲との比較で苦しんできた子ほど、「自分にはもう居場所がない」と感じやすいです。
「夢=職業」が子どもの選択肢を奪う
さらに、「夢=職業」と決めつけることのもう一つのリスクは、多様な生き方の選択肢を奪ってしまうことです。
たとえば、
- 地域でのんびり暮らしたい
- 毎日決まった時間に起きなくてもいい生活がしたい
- 家族や動物と静かに過ごす時間を大切にしたい
こういったライフスタイル志向の夢は、「仕事」とは別のベクトルにあります。
しかし、職業ありきで将来像を描く教育や社会の中では、「それって夢なの?」という空気がどこかにある。
結果として、「働くことでしか価値がない」「職業に就かない人生は失敗」というメッセージを無意識に受け取ってしまうのです。
不登校の子が「夢」を抱えられない理由
不登校の子どもにとって、「将来」や「夢」という言葉は、ときに現実から遠すぎて、ただの不安材料になることがあります。
特に次のような状況では、それが顕著です。
- 学校に行けない自分を責めている
- 同級生と比べて“遅れている”ことを気にしている
- 社会や大人への信頼が揺らいでいる
この状態で「夢を持とう」「将来のために今をがんばろう」と言われても、心は動きません。
むしろ、「将来のことなんか考えられない自分はダメなんだ」というメッセージに変換されてしまう。
その結果、焦りと自己否定ばかりが膨らんでいくのです。
親として直面する葛藤
ここで、保護者としての葛藤にも触れておきたいと思います。
親御さんにとって、「夢を持ってほしい」という思いは、希望を見たいという自然な気持ちです。
- このまま社会に出られなかったらどうしよう
- 夢や目標があれば、きっと元気になれるはず
- やる気があれば、何かが変わるのでは?
こうした期待は、とてもよく分かります。
ただ、その期待が強くなりすぎると、知らず知らずのうちに「正解の形」を子どもに押し付けてしまうことがあります。
たとえば、「やりたいことがあるなら、勉強しなきゃ」「夢があるなら学校に行けるよね」というように。
これは裏を返せば、「夢がないと努力しないとダメ」「今のままじゃダメ」と聞こえてしまう可能性もあるのです。
「夢を持たせよう」としない勇気
大切なのは、「夢を持て」という目的を子どもに押しつけるのではなく、その子が自分で“何を心地よいと感じるか”に気づける環境をつくることです。
夢は、職業ではなく、「感覚」から始まることもあります。
- なんとなく、居心地がいい場所
- 無理をしないで過ごせる人間関係
- 自分の好きなことが咎められない空間
これらを少しずつ取り戻していく中で、「こういう毎日がいいな」「こういう生き方がしたいな」という感覚が芽生えてきます。
それが職業に変換されるのは、ずっと後でもいいんです。
まとめ:職業以外の「夢を持つ」大切さ
まとめとして、お伝えしたいことがあります。
「夢」は、未来に何かを成し遂げることじゃなくても構いません。
今この瞬間、自分に正直に過ごすこと。それも立派な“夢を生きている”状態です。
- 今はまだ何者でもないけど、何者かにならなくていい
- 自分の好きに素直でいる時間を、大事にする
- 「将来」ではなく、「今ここ」に小さな希望を見つける
「夢が見えないこと」を不安に思う方も多いですが、夢を職業で語らない選択肢があってもいいんです。
どうか、「何になりたいか」よりも、「どうありたいか」を大切にしてあげてください。
【国内最多の登校支援実績】トーコについて
私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。
「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。
それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。
無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。