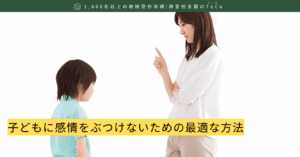交換条件で宿題をさせることのリスク
こんにちは。児童カウンセラーの竹宮です。
今日は、「交換条件で宿題をやらせること」についてお話ししたいと思います。
「●●したら、宿題やろうね」
「ゲームは、宿題が終わったらにしよう」
「ご飯の後にちゃんとやろうって、約束したよね?」
日常の中で、親御さんがこんなふうにお子さんに声をかける場面は、よく見かけます。私も、子どもを持つ一人の親として、その気持ちは本当によくわかります。
ですが、今回はあえてこの「交換条件」という方法に潜む、意外なリスクについて掘り下げてみたいと思います。
目次
- 宿題をやらせるには「条件」が必要?
- 「でも、宿題は大事じゃないの?」
- 「将来、本人が困るんじゃないか…」という不安
- 「やらされる」ではなく「やってみようかな」の種を育てる
- 親の不安が、知らず知らず子どもに伝わっていることも
- 「勉強がすべてじゃない」と言い切れなくてもいい
- おわりに
宿題をやらせるには「条件」が必要?
特に小学生、中学校お子さんを前にすると、どうしても「せめて宿題だけでもやって欲しい…」という責任感が生まれていきます。
その気持ちが、「ゲームするなら宿題をやろう」といった“交換条件”という形で現れるのも、無理のない流れです。
でも、ここでちょっと立ち止まって考えてみてください。
この方法で、お子さんは本当に「宿題をする意味」を理解できているのでしょうか?
一般的な考え方:「報酬」でやる気を引き出す
行動心理学では、「報酬によって行動を強化する」考え方があります。
これは「オペラント条件付け」とも呼ばれ、簡単に言うと、「○○したらいいことがある」と学習することで、行動が習慣化していくという仕組みです。
大人でも、「仕事を頑張ったら給料が増える」と思えばやる気が出ますよね。
このように、行動と報酬をセットにすることで、やる気を引き出すという考え方は、実際に多くの場面で使われています。
それゆえ、「ゲームをしたいなら、宿題を終わらせよう」と言いたくなるのも自然なことなのです。
それは「報酬」ではなく「交換条件」かもしれません
ただし、ここで注意したいのは、「報酬」と「交換条件」は似ているようで、実は少し意味が違うということです。
「報酬」は、自分の行動の結果として得られるごほうび。
「交換条件」は、「これをやってくれたら、これをあげるよ」と、取引のような形です。
この違いは、小さなようでいて、実は子どもの心に与える影響が大きいのです。
交換条件での宿題は、「やる意味があるからやる」ではなく、「これをやらないと、好きなことができないからやる」という構図を生み出します。
つまり、「自分の学び」のはずだったものが、「交渉材料」や「プレッシャー」に変わってしまうのです。
交換条件がもたらす“静かな副作用”
こういったやり取りを繰り返すうちに、子どもの中には次のような気持ちが生まれやすくなります。
・「宿題=楽しくないこと」と刷り込まれる
・「やりたくないことをやらされている」と感じる
・「親は僕がゲームをするのをコントロールしてる」と不満を持つ
さらに怖いのは、「親が求めていることをやらなければ、愛されない」という認知が育ってしまうケースです。
もちろん、親としては愛情ゆえに言っているだけです。ですが、子どもの心はまだ未熟で、理屈よりも感情で物事を受け止めるものです。
「また今日も怒られたな」
「ちゃんとやってないとダメなんだな」
そんな風に感じさせてしまうリスクがあることは、覚えておいて損はありません。
「でも、宿題は大事じゃないの?」
ここまで読んで、「とはいえ、宿題をやらせないままでいいの?」と思われたかもしれません。
その疑問、とてもまっとうだと思います。
勉強は大切ですし、学ぶことの積み重ねは、子どもにとって将来の財産にもなります。
だからこそ、どうにかしてやらせたい。その気持ちが湧いてくるのは当然なのです。
しかしながら、「勉強は大事だから、やらせる」というロジックは、子どもにとって必ずしも自然には響きません。
たとえば、大人が「健康のために毎日ジョギングをしよう」と思っても、三日坊主で終わることってありますよね。
「いいこと」だからといって、実行するモチベーションになるとは限らないのです。
子どもが自分で「意味づけ」できるかどうか
学びというのは、本来は「本人が必要だと感じたとき」に、もっとも力を発揮するものです。
誰かに言われてやる勉強より、自分から「知りたい」「分かりたい」と思ってやる学びのほうが、何倍も頭に残ります。
交換条件を使って、短期的に「やらせる」ことはできても、長期的に「意味づけ」を育てることはできません。
たとえば、野球にハマった子どもが、バッティングの理屈を調べたり、プロ野球選手の成績をノートにまとめたりするのは、誰かに言われたからではありませんよね。
「自分の興味」と「学び」がつながった瞬間、それは本当の意味での“勉強”になるのです。

「将来、本人が困るんじゃないか…」という不安
ここでまた、別の不安が湧いてくる方もいらっしゃるかもしれません。
「今、やらないと、将来困るのは本人なのでは?」
「そのとき、親として後悔しないだろうか…?」
とてもよく分かります。
見ているだけで、どうにかしたくなる。
放っておくなんて、できるはずがない。
子どもに苦労させたくない。
その気持ちは、どれも親として自然な感情です。
ですが、その反面、いま子どもが感じている「やらされている感」や「コントロールされている感覚」は、将来の“自律”を遠ざけてしまうリスクもあるのです。
本人が困るのは、悪いことではない?
「今はいいかもしれない。でも、このままだと本人が後で困るんじゃないか」
不登校のお子さんを持つ保護者の方から、何度となく聞いた言葉です。
たしかに、勉強しないまま学年が上がっていくと、教科書の内容が難しくなっていきます。
周りと比べて「分からないこと」が増えると、焦りや不安を感じるかもしれません。
けれど、それは必ずしも「悪いこと」とは言い切れません。
なぜなら、「困ること」には、人を動かす力があるからです。
「困って初めて気づく」こともある
たとえば、旅行に出かける日にスマホを忘れたら、かなり焦りますよね。
地図も見られないし、予約情報も確認できない。そんな不便さを一度経験すると、「次は絶対に忘れないようにしよう」と強く思うものです。
これは一種の“学び”です。
人は、失敗や不便を通して、自分に必要なことを肌で感じ、それを次の行動に活かしていきます。
子どもも同じです。
たとえ今は「宿題をやらない」ことで、後で困ったとしても、その経験から「どうにかしたい」と自分で思うことができれば、それは大きな力になります。
「やらされる」ではなく「やってみようかな」の種を育てる
逆に言えば、親が先回りして困らせないようにすると、「本人の中で芽生えるはずの動機」が育ちにくくなることもあります。
少し厳しい言い方になりますが、これは「学びの機会を奪ってしまう」ことでもあるのです。
もちろん、放っておくという意味ではありません。
大事なのは、「あなたがどうしたいかを大切にするよ」という姿勢です。
子どもにとって、「自分の判断を尊重してもらえる」という体験は、自信や自己決定感につながります。
それが、将来的な「自分で選んで動ける力」につながっていくのです。
「任せる」と「見捨てる」の違い
ここで誤解してほしくないのは、「任せる」ということが、「放置する」とイコールではないという点です。
子どもが宿題をやらなくても、何も言わずに放っておく。それは「無関心」に近い行動です。
一方、「あなたがどうしたいのかを見守る。でも、気になることがあればいつでも話そうね」と伝えるのは、「信頼」と「関心」の表現です。
これは、子どもにとって大きな違いになります。
「どうしても宿題をやってほしい」と思ってしまうときほど、一度この違いを意識してみてください。
親の不安が、知らず知らず子どもに伝わっていることも
親が「このままだとダメかもしれない」と思っていると、子どもはそれを敏感に察します。
たとえ言葉で「大丈夫だよ」と言っていても、態度や声のトーン、表情に不安がにじむと、子どもは「自分は親にとって、あまり良くない子どもなんだ」と感じてしまうことがあります。
これは、子どもの自己肯定感に影響を与える原因にもなります。
だからこそ、「自分が不安だから、子どもに行動させたいのかもしれない」と気づけるだけでも、子育てのスタンスが少し楽になります。
「今の気持ちに名前をつけてみる」という手
では、親自身の不安にどう向き合えばいいのでしょうか。
一つの方法は、「今の自分の気持ちに名前をつけてみる」ことです。
たとえば、
・「将来への焦り」
・「ちゃんとした親でいたい気持ち」
・「周囲と比べてしまう焦燥感」
・「子どもが嫌われないか心配な気持ち」
こんなふうに、自分の気持ちを言葉にしてみるだけで、ぐるぐるしていた感情が少し整理されます。
これは心理学で「ラベリング」と呼ばれる方法で、心を落ち着ける効果があります。
不安な気持ちを無理に消す必要はありません。
ただ、それを「見える形」にしてみると、感情に振り回されにくくなるのです。
宿題より大切な「自分を信じる体験」
最終的に、子どもにとって何より大事なのは、「自分で選んで、自分で行動できた」という実感です。
それはたとえ、宿題ではなくても構いません。
・自分で好きな本を読む
・自分から台所を手伝う
・自分で時間を決めてゲームを終わらせる
こういった日常の小さな選択を、自分でやってみて、「できた」「やれた」と感じること。
その積み重ねこそが、自信と主体性を育てていきます。
「勉強がすべてじゃない」と言い切れなくてもいい
ここまで読んで、「そうは言っても、勉強は大事だし…」とまだモヤモヤする方もいらっしゃるかもしれません。
そのモヤモヤ、自然なことだと思います。
「全部を任せて、何もしないのも違う気がする」
「かといって無理にやらせたくもない」
その揺れの中にいることが、親として真剣に向き合っている証だと思います。
大切なのは、「100か0か」ではなく、「その間のグラデーションの中で、何ができるか」を考えることです。
その中に、「交換条件以外の伝え方」もきっとあるはずです。
子どもを信じて任せる時間を増やしていく
子どもの状況は一人ひとり違いますし、家庭の環境や本人の特性によって、対応の仕方も様々です。
ですから、私は安易に「これで大丈夫です」と言うことはできません。
けれど、それでも一つだけお伝えしたいことがあります。
それは、「焦らなくていい」ということです。
子どもが何かを選び取っていく力は、少し時間がかかっても、ゆっくり育っていきます。
その芽を信じて、必要以上に急がず、今できることを少しずつやっていく。
その積み重ねが、きっと意味のある形になります。
おわりに
子どもの学びをどう捉えるか。
親の不安とどう向き合うか。
どれも簡単なテーマではありません。
ですが、「やらせる」以外にも「任せる」という選択肢があること。
「今困ること」には、未来の力につながる側面もあること。
この二つの視点が、あなたの中に少しでも残ってくれたら嬉しいです。
【国内最多の登校支援実績】トーコについて
私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。
「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。
それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。
無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。