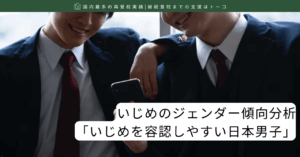子どもにやる気を出させるには、自己認識を変える小さな行動から
こんにちは。カウンセラーの竹宮と申します。
不登校のお子さんを支える保護者の方々から、よくこんなご相談を受けます。
「この子、やる気がないわけじゃないと思うんです。でも、動こうとしないんです」
「何か小さな行動でも起こせたら、少しは変わってくる気がするのに……」
「ただ、無理に動かせば逆効果になるのも怖くて……」
このような悩みは、とても現実的です。
子どもの状態を見ていると、「やる気はゼロではないように思う。でも、そのきっかけがどこにあるのか分からない」というジレンマに、多くのご家庭が直面しています。
そこで今回は、「やる気」という目に見えにくいものが、どのように生まれ、どのように回復していくのかについて、児童心理学と認知行動療法(CBT)の観点から、丁寧に整理していきます。
結論から言えば、やる気は「行動を通して自己認識が少し変化したとき」に生まれるものです。
ただ、ここでいう「行動」とは、単に勉強するとか、登校するとか、そういった“外から見える結果”のことではありません。
「自分はこういう人間かもしれない」という感覚を本人の中に育てるための行動。
それが、やる気をつくる“起点”になります。
目次
- 「やる気がない」のではなく、「やる気を持てる自己イメージが持てない」
- 認知行動療法が重視する「行動による認知の更新」
- 保護者ができるのは、行動の「意味づけ」に口を出さないこと
- 「意味のある行動」ではなく「意味づけを委ねる行動」を支える
- 「固定化された自己認識」を揺らすには
- やる気とは、自己認識のわずかな変化を感じられる力
- 関連記事
「やる気がない」のではなく、「やる気を持てる自己イメージが持てない」
表面的な無気力の背後にあるもの
不登校の子どもたちに対して、「やる気がない」「何もしようとしない」と感じることはよくあります。
しかし、臨床の現場で見えてくるのは、多くの子どもたちは“動きたい”気持ちを完全に失っているわけではないという事実です。
問題は、「自分が動いたとき、うまくいく」というイメージが持てないことにあります。
心理学ではこれを「自己効力感(selfefficacy)」と呼びます。
これは「自分にはそれをやる力がある」「自分にも何かができる」という感覚のことです。
この自己効力感が著しく低下していると、子どもは動く前から「どうせ無理だ」「やっても意味がない」という認知を持ちます。
この認知は、単なる気持ちの問題ではありません。
「過去の失敗経験」「自分に向けられた期待と比較」「自分の行動が周囲にどう見られるかへの不安」など、非常に現実的な要素に根ざしています。
ですから、子どもの中では、「やる気を出す」ことそのものが、すでに高いハードルになっているのです。
認知行動療法が重視する「行動による認知の更新」
自己認識は“行動のあと”に書き換わる
ここで認知行動療法の視点を活かして考えてみましょう。
認知行動療法では、「認知(ものの捉え方)」と「行動」の間に双方向の関係があると考えます。
つまり、人の考え方が行動を変えるだけでなく、行動がその人の考え方を更新することもあるということです。
やる気の問題も、まさにこの構造に含まれます。
「やる気がないから行動しない」のではなく、
「自分はやってもうまくいかない人間だ」と思っているから動けない。
そして、「動けなかったから、やっぱり自分はダメだ」と、さらにその認識が強化されてしまう。
この悪循環を止める鍵が、「小さくて、結果を求めない行動」です。
結果を目的としない行動が取れたとき、人は自分のことを少しだけ違って感じられるようになります。
- 「今日はなんとなく起きてみた」
- 「ちょっとだけ顔を洗った」
- 「たまたまリビングに来ただけ」
これらの行動は、それ自体は目立った成果ではありません。
しかし、本人の内面では、
「自分は全く何もできないわけではないかもしれない」
「以前より、ほんの少し変わってきたかもしれない」
という“認知のゆらぎ”が生まれています。
そして、この微細な変化こそが、やる気の本質的な起点になります。
変化は「やる気→行動」ではなく、「行動→違和感→再評価」
やる気が自然に湧き上がってくるのを待つのではなく、「あれ?今日の自分は少し違うかも」という違和感に気づかせること。
これが、認知行動療法的にも最も自然な支援の形です。
この違和感は、強制的な行動では決して生まれません。
本人のペースで、自分の価値観に照らし合わせて、「まあ、これくらいなら」と思えるような行動。
その繰り返しが、「自分はどういう人間か」に対する自己認識を少しずつ更新していきます。
やる気とは、そうした自己認識の変化が一定の濃度に達したとき、「あ、やってみてもいいかも」と浮かび上がってくる感覚です。
保護者ができるのは、行動の「意味づけ」に口を出さないこと
評価は、自己認識の芽を潰すことがある
子どもが小さな行動をしたとき、私たち大人はつい「前より元気になったね」「えらいね」「じゃあ次はこれやってみようか」と言いたくなります。
ですが、それは大きなリスクを含みます。
なぜなら、「親がそれに意味を与えてしまうと、子どもはそれが“期待に応える行動”に変わってしまう」からです。
そうなると、次の瞬間にはもう、
- 「またやらなきゃいけないのか」
- 「これをやると、期待されてしまう」
- 「やっぱり次は失敗しそう」
という自己認識に引き戻されます。
行動の意味づけは、本人に任せることが鉄則です。
行動できたことを認め、褒めたり励ましたりした上で、本人がもし少しでも自分の中で意味を見出そうとしていたら、それを言葉にできる余白を与えてあげてください。
「意味のある行動」ではなく「意味づけを委ねる行動」を支える
小さな行動を「再評価のきっかけ」にする
認知行動療法において、行動は「変化を生むための実験」として扱われます。
重要なのは、その行動が成功したか失敗したかではなく、その行動を通して何が起きたか、本人がどう受け取ったかです。
たとえば、「外に出たら気分が変わった」という事実よりも、
- 「思ったよりしんどくなかったかも」
- 「思った通り疲れた。けど、自分にはこのペースが必要かもしれない」
といった内面的な認知の動きが、最も価値のある変化です。
このような“再評価の回路”が一度でも起動すれば、次の行動は「義務」ではなく、「検証」の位置に変わります。
つまり、「やるかやらないか」ではなく、「どうなるか見てみよう」という姿勢に変わるのです。
これは非常に大きな違いです。
やる気とは、“正解に向かって努力する力”ではなく、「今の自分にとって合うやり方を探す意思」に近いものだからです。
保護者が担う伴走者としての役割
このプロセスにおいて、保護者ができる最も効果的な関わり方は、監督ではなく伴走者であることです。
つまり、「子どもが適切に行動したかどうか」ではなく、
- そのとき、どんな選択をしたか
- 何に時間をかけていたか
- 何を避け、何に関心を持っていたか
といった、認知を見る姿勢が重要になります。
この視点に立つと、「今日は元気だった」「昨日はダメだった」といった短期的な評価は意味を持ちません。
そのかわり、「今、どんな意味づけの変化が起きつつあるか」という長期的な“流れ”が見えてきます。
たとえば、同じ「今日は起きなかった」日でも、
- 前日は「起きようとして、でもやめた」
- 今日は「最初から起きるつもりがなかった」
この違いを見抜けるかどうかで、対応は大きく変わります。
後者は疲弊のサインかもしれませんし、前者は「選択の余地を感じ始めた」兆しかもしれません。
こうした微細な差異を見極め、過剰に介入せず、しかし確かに気づいているという態度で接することが、子どもの自己認識をより柔軟にしていきます。
「固定化された自己認識」を揺らすには
レッテルから“プロセス”へ
不登校の子どもたちがよく口にする言葉に、「自分はこういう人間だから」があります。
- 「自分はダメなタイプだから」
- 「自分はみんなと同じようにできないから」
- 「もう失敗したくないから」
これは、長期化する不登校の中で構築された“固定化された自己認識”です。
この認識の問題は、「行動する/しない」というレベルではなく、「自分に対する捉え方が変わらない」という構造にあります。
では、どのようにすればこの固定化された認識がほぐれていくのでしょうか。
それは「完了した人格像」ではなく、「変化する過程としての自己イメージ」を経験させることです。
つまり、「私は◯◯な人間だ」というラベルから、「今の自分はこうかもしれないが、また違う状態にもなり得るかもしれない」という“仮説的な自己像”に移行させる必要があるのです。
この移行を可能にするのが、小さく、意味のないように見える行動です。
「たまたま起きた」「気まぐれで食べた」「暇だから読んだ」
このような行動は、本人にとって“人格を反映しない行為”であるからこそ、心理的抵抗が少なく、その分、「もしかしたら自分はこういうこともできるのかも」という揺らぎを生み出します。
認知行動療法では、こうした行動のことを“習慣化のための前段階”として、行動実験(behavioral experiment)と捉えます。
このフェーズでは、成果や成長を求めることよりも、「経験を積む」ことに主眼を置くことが推奨されます。
やる気とは、自己認識のわずかな変化を感じられる力
ここまで、「子どもにやる気を出させるには、行動ではなく自己認識を動かす」と題してお話してきました。
それは「自己認識を動かす行動」をどう見つけるか、という問いです。
不登校の支援において、「行動」そのものを目標にすると、子どもはプレッシャーを感じ、自分を責め、動けなくなってしまうことがあります。
しかし、「この子がどのような自己認識を持っているか」「何がその認識を形作ってきたか」「何がそれを少しだけ揺らす可能性があるか」という視点を持つことで、関わり方の質は大きく変わります。
やる気とは、「自己イメージと行動が一致している」という感覚です。
その一致は、突然起きるのではなく、
- 小さな行動によって
- ごくわずかに
- 本人の内側で「意味づけ」が変化したとき
初めて芽生えます。
ですから、私たち大人ができるのは、
- 無理に動かそうとしないこと
- 動いた意味を決めつけないこと
- 気づいた変化を静かに伝えること
この3つに尽きます。
不登校は、単に“行動が止まった状態”ではありません。
それは「自分がどういう存在か」をもう一度考え直す時間でもあります。
子どもが、自分自身の新しい認識を少しずつ持ち直していく過程に寄り添うこと。
それが結果として、最も確かな「やる気」につながっていくのです。
関連記事
【国内最多の登校支援実績】トーコについて
私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。
「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。
それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。
無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。