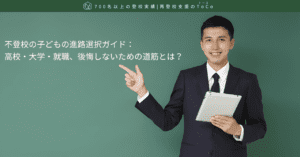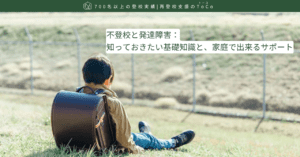不登校の子と親の「心の距離」を縮める、今日からできるコミュニケーション術
不登校や引きこもりの問題に取り組む児童心理司の藤原と申します。私は、不登校予防や再登校支援を行うToCo(トーコ)株式会社の顧問を務めております。
不登校に直面する保護者の多くが、「どう接したらよいのかわからない」「子どもと話す機会が減ってしまった」と悩みを抱えています。
しかし、親子のコミュニケーションが途絶えると、不登校の長期化や家庭内での孤立を招くリスクが高まります。本稿では、今日から実践できる「心の距離」を縮めるコミュニケーション術について、具体的な方法とその心理的背景を詳しく解説していきます。
参考:文部科学省「不登校対策(COCOLOプラン等)について」
目次
第1章:子どもの感情を理解し、受け止めることの重要性
不登校の子どもの心理
不登校の子どもたちは、学校に行けないことへの罪悪感や、親に迷惑をかけているという後ろめたさを抱えていることが少なくありません。特に、もともと真面目で頑張り屋の子ほど、「行かなければならないのに行けない」という自己否定のループに陥りやすい傾向があります。その結果、「自分はダメな人間だ」と感じ、自信を失い、家にこもる状態が続いてしまうのです。
こうした子どもの心理状態を理解せずに、「どうして学校に行かないの?」「いつまでこのままなの?」と問い詰めると、子どもはますます追い詰められ、親との心の距離が広がってしまいます。
子どもが抱えている本当の気持ちを知るためには、まず「親が子どもの感情を受け止めること」が欠かせません。ここで大切なのは、「なぜ行かないのか」と理由を問い詰めるのではなく、「今どんな気持ちでいるのか」に焦点を当てることです。
たとえば、子どもが言葉少なげにしている場合、「最近、なんとなく気分が沈んでいる?」とそっと尋ねてみるのもよいでしょう。もし子どもがうなずいたなら、「そうなんだね。ずっとつらかったね」と共感の言葉をかけることで、子どもは「自分の気持ちをわかってもらえた」と感じ、少しずつ話しやすくなります。
不安を大きくしないための言語化
また、不登校の子どもたちは、自分の気持ちをうまく言語化できないことがよくあります。特に小学生の子どもは、「学校が嫌だ」とは言うものの、具体的に何が嫌なのか説明できないことが多いのです。
こうした場合、「学校のどんなことがしんどいのかな?」「教室に入るのがつらいの?」「勉強が大変なの?」と、いくつかの選択肢を示してあげると、子どもが自分の気持ちを整理しやすくなります。もし、どの質問にも答えられないようであれば、「話したくないときは、無理に話さなくてもいいからね」と伝え、無理に聞き出そうとしないことも大切です。
さらに、子どもの話を聞く際には、「否定しない・アドバイスをしない」ことを意識しましょう。例えば、子どもが「学校に行くのが怖い」と話したときに、「そんなの気の持ちようだよ」「みんな頑張っているんだから、あなたも頑張りなさい」といった言葉をかけると、子どもは「この人にはわかってもらえない」と感じ、ますます心を閉ざしてしまいます。
親としては励ましたい気持ちがあるかもしれませんが、不登校の子どもにとって、もっとも必要なのは「共感されること」です。「怖いんだね」「毎朝、学校のことを考えると胸が苦しくなるのかな」と子どもの感情に寄り添いながら話すことで、子どもは安心して気持ちを話せるようになります。
また、言葉だけでなく、非言語的なコミュニケーションも大切です。親の表情や態度は、子どもに大きな影響を与えます。例えば、親が険しい顔をしていたり、ため息をついたりしていると、子どもは「自分のせいで親がこんなに疲れている」と感じ、さらにプレッシャーを感じてしまいます。逆に、穏やかな表情で、落ち着いた声のトーンで話すと、子どもは安心して自分の気持ちを伝えやすくなります。親が子どもの話を聞くときには、意識的に表情を柔らかくし、「あなたのことを大切に思っているよ」という気持ちを伝えることが重要です。
このように、子どもの感情を理解し、受け止めることは、不登校から抜け出すための第一歩となります。子どもが「自分の気持ちをわかってもらえた」と感じることで、親子の信頼関係が深まり、少しずつ前向きな行動へとつながっていきます。
第2章:日常生活の中でのコミュニケーションの工夫
不登校の子どもとの「心の距離」を縮めるには、特別な場面での対話だけでなく、日常生活の中での関わり方が大きな影響を与えます。多くの保護者は、子どもとしっかり話そうとして「時間を作って真剣に向き合う」ことを考えがちですが、それが逆にプレッシャーとなり、子どもが話しづらくなってしまうこともあります。不登校の子どもにとっては、「向き合う対話」よりも「自然な会話」が重要なのです。
共通の時間を増やすことの大切さ
不登校の子どもは、学校に行かないことで「親と顔を合わせるのが気まずい」と感じたり、「どうせ叱られるのではないか」と警戒心を抱いていたりすることがあります。そのため、親子の関係を改善するためには、意識的に「同じ空間で過ごす時間」を増やすことが大切です。ただし、「話すこと」を目的にするのではなく、「一緒に何かをする」ことに重点を置くのがポイントです。
例えば、一緒に食事をする時間を増やすことは有効な手段のひとつです。食卓を囲むことは、言葉を交わさなくても「家族としてのつながり」を感じられる大切な時間です。無理に会話をしようとせず、同じ空間で食事をすること自体を大事にするだけでも、子どもに安心感を与えます。また、子どもが自分から話し出したときに、さりげなく相槌を打つことで、「親は自分を受け入れてくれている」という感覚を持たせることができます。

また、子どもの好きなことに親が関心を示すのも、自然なコミュニケーションのきっかけになります。不登校の子どもは、ゲームやアニメ、動画視聴などに没頭していることが多いですが、それを「時間の無駄」などと否定せず、「どんなゲームをしているの?」「このキャラクター、どんなところが好き?」といった形で興味を持って話しかけることで、子どもは「親に認められた」と感じやすくなります。このような日常的な関わりを続けることで、親子の信頼関係が深まり、子どもが自分の気持ちを話しやすくなる土台ができます。
親からの一方的な会話にならない工夫
子どもとの会話では、「親が話す時間を短くし、子どもが話す時間を長くする」ことが理想的です。しかし、不登校の子どもは自分から話し出すことが難しいため、親が主導で会話を進める場面も出てくるでしょう。その際に気をつけるべきなのは、「問い詰めるような話し方をしない」「アドバイスを押しつけない」ことです。
例えば、「学校に行かない理由を教えて」と直接聞いてしまうと、子どもは「正しい答えを言わなければならない」と感じ、余計に口を閉ざしてしまいます。そのため、「最近、家で過ごす時間が増えたけど、何か楽しいことはあった?」といったように、答えやすい話題から入るのが効果的です。まずは子どもがリラックスして話せる環境を作り、徐々に心を開いてもらうことを意識しましょう。
また、親が「こうしたほうがいい」「こうすればうまくいく」とアドバイスをするのも避けたほうがよいでしょう。たとえば、「朝早く起きる習慣をつけたほうがいいよ」と言うと、子どもは「できていない自分はダメなんだ」と感じてしまいます。
代わりに、「朝起きるのがしんどいのは、夜なかなか眠れないのかな?」と、子どもがどう感じているかを尋ねる形にすることで、プレッシャーを与えずに話を深めることができます。
「会話がなくてもOK」という安心感を持たせる
不登校の子どもは、親と話すこと自体に緊張を感じることがあります。特に、長期間学校に行っていない場合、「親と話すと学校の話になってしまうのでは」と警戒し、できるだけ会話を避けようとする子もいます。このような場合、「話さなくてもいい」「会話がなくても大丈夫」という空気を作ることが大切です。
具体的には、子どもがリビングに来たときに、無理に話しかけるのではなく、親が普段通りに過ごしている姿を見せることが有効です。例えば、親が新聞を読んでいたり、料理をしていたりすると、子どもは「何か話さなければならない」というプレッシャーを感じずに済みます。そして、もし子どもが何か話し始めたときには、手を止めてしっかり耳を傾けることで、「親は自分の話をちゃんと聞いてくれる」と感じるようになります。
また、散歩やドライブなど、横並びの状態で過ごす時間を増やすのも良い方法です。面と向かって話すのが苦手な子どもでも、並んで歩いていると自然と会話が生まれやすくなります。「天気がいいね」「この道、前に通ったことある?」といった些細な話題から始めることで、子どもが会話に参加しやすくなるのです。
このように、日常生活の中で自然な形で関わりを持つことが、子どもとの「心の距離」を縮める上で非常に重要です。親が「会話をしなければならない」と意気込むと、子どもは逆に緊張してしまうため、「同じ空間にいること自体が大事」と考え、ゆるやかに関わっていくことが大切です。
第3章:親自身の心のケアとサポートの重要性
不登校の子どもと向き合うことは、親にとっても精神的な負担が大きいものです。多くの保護者が「このままでいいのか」「何か間違ったことをしているのではないか」と悩み続けています。また、周囲の目や親族からの心ない言葉に傷つき、自分を責めてしまうことも少なくありません。しかし、親が不安や焦りを抱えたままだと、それは必ず子どもにも伝わり、状況を悪化させる要因となってしまいます。子どものためにも、まずは親自身が心のケアを意識することが大切です。
親の不安が子どもに与える影響
不登校の子どもは、親の感情を敏感に感じ取ります。特に、小学生の子どもは親の表情や態度の変化を直感的に察知する能力が高いため、親が焦りや不安を抱えていると、それを「自分のせいだ」と受け止めてしまうことがよくあります。
例えば、親が「なんとかして学校に行かせなければ」と思っていると、その緊張感が日常の何気ないやり取りにも表れます。たとえば、「今日はどうするの?」「そろそろ学校のこと考えようか?」といった言葉が、知らず知らずのうちにプレッシャーになってしまうのです。子どもは親を悲しませたくない、怒らせたくないという思いを持っているため、「学校に行かなければ」と焦りながらも動けない状況に追い込まれ、ますます心を閉ざしてしまうことがあります。
また、親自身が落ち込んでいたり、疲れ果てていたりすると、子どもは「自分のせいで親がこんなに苦しんでいる」と感じ、余計に自己肯定感が低下してしまいます。そのため、親が心の安定を保つことは、子どもの回復にも大きく影響するのです。

親自身のメンタルケアの方法
不登校の子どもと向き合うには、親自身が心の余裕を持つことが不可欠です。とはいえ、「ストレスを溜めないようにしよう」と考えても、現実的には難しいものです。そこで、親自身が気持ちを整理し、適切にケアをするための具体的な方法を紹介します。
① 一人で抱え込まない
不登校の問題は、親一人で解決できるものではありません。親だけで何とかしようとすると、どうしても視野が狭くなり、冷静な判断ができなくなってしまいます。信頼できる専門家や、不登校の子どもを持つ親同士のコミュニティなどに相談し、「一人ではない」と感じることが重要です。
② 生活リズムを整える
子どもの不登校が続くと、親自身の生活リズムも乱れがちになります。例えば、夜遅くまでインターネットで不登校に関する情報を調べ続けたり、朝の登校時間に合わせて過度に神経を使ったりすることで、親自身が疲弊してしまうケースも少なくありません。しかし、親が健康的な生活を送ることは、子どもに安心感を与えるためにも重要です。
特に、食事や睡眠の質を意識することが大切です。親が食事をきちんと摂り、規則正しい生活をしていると、子どもも自然とそのリズムに影響を受けます。逆に、親が疲れ果てた様子でいると、子どもも「家の中が落ち着かない」と感じ、余計に部屋にこもってしまうことがあります。
③ 「今できること」に目を向ける
不登校の子どもを持つ親は、「どうすれば学校に戻れるのか」「いつになったら元の生活に戻るのか」と将来のことばかり考えてしまいがちです。しかし、先のことを考えすぎると、不安が増し、焦りが強くなります。そのため、「今できること」に意識を向けることが大切です。
例えば、「今日は子どもと一言でも会話ができた」「一緒にご飯を食べられた」といった小さな積み重ねを大切にすることで、少しずつ前向きな気持ちを持つことができます。「学校に行かせなければならない」というプレッシャーを手放し、「今の子どもを受け入れる」という視点に切り替えることで、親自身の心の負担も軽くなります。
第4章:親子の信頼関係が回復した先にあるもの
不登校からの回復には時間がかかります。その過程で大切なのは、「親子の信頼関係を回復すること」です。子どもが安心して親と話せるようになり、自分の気持ちを素直に表現できるようになれば、少しずつ前向きな行動が増えていきます。
多くの保護者が「子どもを学校に戻したい」と思うのは当然ですが、大切なのは「子どもが自分の力で一歩を踏み出せる状態を作ること」です。そのためには、「親が子どもに安心感を与えられる存在であること」が何よりも重要です。
不登校の子どもは、「自分はダメな人間だ」「どうせ理解してもらえない」と思い込んでしまうことがよくあります。しかし、親が適切に関わることで、子どもは「自分は大丈夫だ」「受け入れてもらえている」と感じることができるようになります。そうした積み重ねが、最終的には学校復帰や社会との関わりを再構築する力へとつながっていくのです。
これまで述べてきたように、不登校の子どもと親の「心の距離」を縮めるためには、焦らず、日常の中で少しずつ信頼関係を築いていくことが大切です。そして、そのためには、親自身が冷静で、穏やかな気持ちでいられることが不可欠です。「子どもが学校に行くこと」だけを目標にするのではなく、「親子の関係を良くすること」を大切にすることで、子どもは安心して前に進むことができるようになります。
最後に、不登校は決して親のせいではありません。そして、どの子どもにも必ず回復のタイミングが訪れます。親が適切に関わり、支えていくことで、そのタイミングを早めることができるのです。本稿が、少しでもその手助けになれば幸いです。
| 要点 | 必要な行動 |
|---|---|
| 子どもの感情を理解する | 子どもが感じている不安やプレッシャーに寄り添い、「なぜ行かないのか」ではなく「今どんな気持ちか」を聞く。共感の言葉をかけ、安心できる環境を作る。 |
| 自然なコミュニケーションを増やす | 向き合う対話より、食事や散歩などを通じた「さりげない会話」を大切にする。子どもの興味に関心を持ち、一緒に過ごす時間を増やす。 |
| 親の不安を子どもに伝えない | 焦りやストレスを子どもに押しつけないようにし、親自身が心の余裕を持つ。生活リズムを整え、相談できる場を確保する。 |
| 今できることに目を向ける | 「学校に行かせる」ことにとらわれず、「今日は会話できた」「一緒に食事できた」といった小さな前進を喜び、積み重ねる。 |
| 子どもが前向きになる環境を作る | 無理に学校を勧めず、子どもが「安心できる場所」で自信を回復できるようサポートする。親子の信頼関係を最優先に考える。 |
【国内最多の登校支援実績】トーコについて
私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。
「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。
それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。
無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。