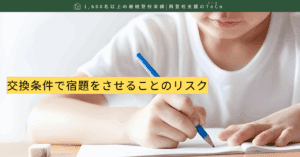子どもに感情をぶつけないための最適な方法
こんにちは。
ToCoの不登校カウンセラー、竹宮です。
子どもに対してイライラしてしまった経験、きっと誰しも一度はあると思います。
特に、子どもが学校に行けない状態が続いていると、親の心もすり減っていきますよね。
「なぜ行かないの?」「ちゃんと話してくれればいいのに」と思いながら、ある日突然、声を荒らげてしまった……そんなことはありませんか?
今日は、「子どもに感情をぶつけないためにはどうしたらいいのか?」というテーマでお話ししてみたいと思います。
一見よくある話題かもしれませんが、世の中で広まっている方法の中には、現実にはうまくいかないものもあります。
だからこそ、今回は「もっと実行しやすくて、実際に効果がある方法」を一緒に考えていきたいのです。
目次
- 「怒りを我慢する」のが正解なのか?
- 「その場を離れる」が一番シンプルで効く
- 離れられないときにできる「見えない距離のとり方」
- 「我慢」だけでは疲れ果ててしまう理由
- 感情をぶつけてしまった後の“回復の仕方”
- まとめ:ぶつけない=無理をしない、ということ
「怒りを我慢する」のが正解なのか?
まず、よくあるアドバイスに「怒りが湧いたらまずは6秒数えましょう」というものがあります。
いわゆる「6秒ルール」と呼ばれる考え方ですね。怒りのピークは最初の数秒間だと言われ、その間をやり過ごせば冷静さが戻るという理屈です。
確かに理にかなっているようにも思えます。
「カッとしたときはとにかく我慢」と聞けば、努力で何とかなるような気がします。
でも、本当にそれでうまくいくでしょうか?
私の元に相談に来られる方の多くは、
「6秒待ったのに、余計にイライラした」
とおっしゃいます。
なぜなら、我慢している間も、子どもは目の前で泣いていたり、ふてくされた態度だったり、あるいは無言で睨んできたり……そうなると、「よけい腹が立ってきた」という状態になってしまうのです。
ここで大切なポイントがあります。
人は「その場にとどまったまま怒りを収める」のがとても難しいということです。
怒りのもとが目の前にある限り、脳が「まだ危険だ」と判断してしまうからです。
その場にいる限り、脳は戦闘モードのまま
これは脳の仕組みによる反応です。
人の脳には、外からの刺激に素早く反応する扁桃体という部位があります。
この部分は、怒りや恐れといった強い感情に深く関係しています。
簡単に言うと、「これは危険かも!」と感じたとき、扁桃体がブザーを鳴らして全身に警戒モードを伝えるわけです。
この仕組みは、私たちの祖先が猛獣に遭遇したときにすぐ逃げたり戦ったりできるように備わったものです。
でも今、目の前にいるのはライオンではなく、自分の子どもです。
それでも、脳はそれを区別できません。
子どもの反抗的な言動や不満そうな態度を「脅威」とみなしてしまうのです。
だから、目の前に子どもがいる状態で怒りを抑えようとすると、かなり無理が生じます。
6秒、10秒、30秒と数えても、怒りが消えるどころか燃え上がってしまう。
この現象、実感がある方も多いのではないでしょうか。
「その場を離れる」が一番シンプルで効く
そこで提案したいのが、
「その場から一度離れる」
という方法です。
物理的に数メートルでもいい。部屋を移動して、キッチンに立つ。トイレに行く。ベランダに出て空を見上げる。
できれば、声も視界も届かないところまで離れられると理想です。
一見、逃げているようにも感じられるかもしれません。
でも、これは感情のコントロールを取り戻すための、いわば「戦略的退避」です。
大人だって、感情を完全にコントロールするのは簡単ではありません。
瞬間的に高まる感情を「自分の中だけで処理しよう」とすると、心の負荷はどんどん蓄積していきます。
離れることで、「脅威」と感じていた対象が視界から消える。
そうすると、脳も少しずつ落ち着いてきます。怒りが2段階、3段階と、レベルダウンしていきます。
私は実際、カウンセリング中にもこの方法を勧めることがあります。
実行された方からは「怒りの強さがまるで違った」「言いすぎる前に落ち着けた」といった声が多く寄せられています。
ただ、現実には「離れられない場面」もありますよね。
車の中、公共の場、あるいは目を離せないタイミング……そんなときはどうすればいいのでしょうか?
離れられないときにできる「見えない距離のとり方」
子育てや介護など、逃げられない場面でどう感情を処理するか。
これは、非常に現実的で、かつ重要なテーマです。
一つのヒントになるのが、「物理的に離れられなくても、意識の焦点をずらす」という方法です。
私たちの脳は、見ているもの・聞こえているもの・考えていることに影響されて、感情が動きます。
つまり、目の前の「子どもそのもの」をずっと見ている限り、怒りのスイッチは入り続けるのです。
意識の焦点をズラすだけでも変わる
たとえば、話をやめて視線をそらす。壁のシミでも何でも構いません。
スマホの画面を開いて、天気予報でもニュース一覧でも見てみる。
この行動には、「今の自分をちょっとずらす」という意味があります。
深呼吸をしながら、頭の中で「今、自分は怒りに夢中になりそうなんだな」と言語化するのも効果的です。
これは心理学で「メタ認知」と呼ばれる考え方で、簡単に言えば「自分を一歩引いて見る力」のことです。
何か特別なスキルが必要なわけではありません。
「一歩引く」という小さな選択をするだけで、気持ちは確実に変わります。
「イメージの中で離れる」小さな工夫
実際にその場を動けないときでも、「頭の中でイメージを切り替える」方法も有効です。
子どもの表情が気になって腹が立ちそうになったときは、目の前の出来事をニュース映像のように見る。
自分を俯瞰して見るような感覚を持つことで、怒りの渦から抜け出す助けになります。
あるいは、「今は自分の中のスイッチが入っているだけ」と言葉にしてみるだけでも、距離ができます。
この“ちょっとした工夫”が積み重なると、怒りをぶつける頻度は驚くほど下がっていきます。
感情を持つことは自然なことです。
でも、それをぶつけずに済む方法があるなら、そちらを選んでいけたら気持ちが少しラクになりますよね。

「我慢」だけでは疲れ果ててしまう理由
よく、「怒らないように深呼吸して耐えてください」と言われることがあります。
確かに、衝動的に怒鳴ってしまうよりはいいかもしれません。
でも、問題はその“耐える”という行動が、自分のエネルギーをどれだけ消耗しているかです。
怒りを感じているとき、私たちの身体はかなりのストレス状態にあります。
心拍数が上がり、筋肉は緊張し、交感神経がフル稼働している状態。
そこで無理に我慢すると、怒りの感情は消えるどころか体内に圧縮されていきます。
結果として、
「その場では耐えたけど、あとでどっと疲れた」
「寝るまでずっとモヤモヤしていた」
そういう経験、ありませんか?
人は“ただ耐える”だけでは、感情の処理が完了しないんです。
怒りがどこにも行き場を失ったまま、体と心に蓄積されていきます。
我慢して我慢して、ある日突然爆発してしまう。
あるいは、言葉にならない疲れとなって自分を責めてしまう。
こうした連鎖は、誰にとってもつらいものです。
感情は「処理する」もの。ためこまない。
じゃあ、怒りはどう扱えばいいのか?
そのカギは「感情を処理する」という考え方にあります。
処理とは、「感じたことを自覚し、それを無理のない形で外に出していくこと」です。
怒ることそのものを悪者にせず、「今、自分はこう感じているんだな」と自分に気づいてあげる。
そして、無理のない範囲で誰かに話す、紙に書く、声に出す……そうした出口を持つことが大事です。
たとえば、
- ノートに「今日はこういうことで腹が立った」と書き出す
- パートナーや信頼できる人に「つい怒りそうになった」と話す
- カウンセリングで「感情の背景」を整理してみる
こうした行動は、“ためこまない習慣”をつくってくれます。
感情がゼロになることはありません。
でも、「怒ってもいい」「でも、ぶつけない選択肢がある」と思えるだけで、心はずいぶん軽くなるものです。
感情をぶつけてしまった後の“回復の仕方”
とはいえ、どんなに気をつけていても、感情をぶつけてしまう瞬間はあります。
イライラが頂点に達し、「もういい加減にして!」と叫んでしまった。
あとで自己嫌悪に陥り、「またやってしまった……」と落ち込む。
そんな日も、ありますよね。
でも、そこで自分を責めすぎないでください。
親だって人間です。
怒ってしまったことよりも、「そのあと、どう対応するか」のほうがずっと大事です。
おすすめなのは、次の3つのステップです:
1. 落ち着いたあとに「自分の感情」を言葉にする
「さっきは、ちょっと怒りすぎちゃった。ごめんね。びっくりさせたと思う」
「本当は心配だった。でも言い方が強くなってしまった」
このように、怒った理由を“感情の背景”として伝えると、子どもは「責められた」ではなく「気持ちを教えてくれた」と受け取りやすくなります。
2. 子どもの反応に期待しすぎない
謝ったからといって、子どもがすぐに優しくなるとは限りません。
反応がなくても、ふてくされていても、それでいいのです。
目的は“自分が感情を整理すること”です。
期待しすぎると、「せっかく謝ったのに!」とまた怒りが湧いてしまいます。
相手のリアクションより、自分の回復を大事にしてください。
3. 小さな信頼の積み重ねを意識する
一度の衝突で親子関係が壊れることは、まずありません。
大事なのは、「その後どう向き合うか」の積み重ねです。
子どもと一緒におやつを食べる、散歩に誘う、何気ない会話をする。
そうした“小さな関わり直し”が、信頼を回復する土台になります。
怒ってしまった日のあとこそ、「関係をつくり直すチャンス」なんです。
まとめ:ぶつけない=無理をしない、ということ
怒りをぶつけないようにするには、「我慢」より「仕組み」が大事です。
- 物理的・心理的に距離を取る
- 感情に気づき、言語化して処理する
- ぶつけたあとも、自分をケアする
この3つの習慣を持つだけで、感情に振り回される頻度は確実に減っていきます。
「怒ってはいけない」と自分にプレッシャーをかける必要はありません。
むしろ、「怒っても大丈夫。でも、ぶつけない工夫ができる」と思えた方が、ずっとラクに生きられるはずです。
私たち大人が感情と向き合う姿は、そのまま子どもにとっての“感情の扱い方”のモデルになります。
完璧を目指さなくても、ちょっとした工夫と回復の力があれば、親子の関係はゆっくりと整っていきます。
【国内最多の登校支援実績】トーコについて
私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。
「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。
それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。
無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。