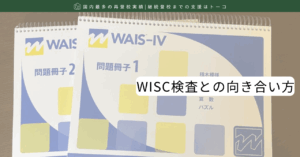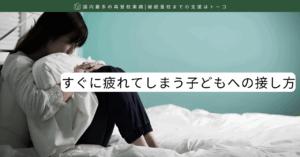子どもとの関係を再構築するためのコミュニケーション術
こんにちは。カウンセラーの竹宮と申します。
今日は「子どもとの関係を再構築するためのコミュニケーション術」についてお話ししたいと思います。
「話を聞いてもくれない」「何を言っても無視される」「このまま親子関係が壊れてしまうのではないか」
不登校の子どもを持つ保護者の方から、こうした声を日々いただきます。
このような状況にあると、「まずは話し合いを」と言われることが多いのですが、実際にはその「話し合い」自体が難しいと感じている方が大半です。
今日はその理由を紐解きながら、「なぜうまく話せないのか」「どうすれば関係を作り直せるのか」を一緒に考えていきたいと思います。
目次
- 話そうとすると避けられる
- 会話の根本は「気持ちよく話してもらうこと」
- 子どもが話してくれないとき、親ができる3つの工夫
- 「話せる空気」をつくることが、最も大切な支援
- うまく話すことより、続けられる関わり方を
- 「話す内容」より「話す姿勢」が関係をつくる
- よくある場面での工夫
- 関係は家族の「間」にできるもの
- コミュニケーションに必要なのは技術より姿勢
- 関連記事
話そうとすると避けられる
よくある誤解:「話すこと=解決すること」
不登校に悩むご家庭では、「とにかく本音を話してほしい」と思うことが多いものです。
「どうして学校に行けないの?」「何があったの?」と問いかけ、子どもの口から真実を引き出したい。
その気持ちはよく分かります。
ですが、このアプローチが子どもにとってプレッシャーになることが少なくありません。
なぜなら、親が「話してほしい」と思えば思うほど、子どもは「話さなければいけない」という圧を感じてしまうからです。
子どもが求めているのは話すことではなく安心できる空気
多くの場合、子どもが本当に望んでいるのは「言葉による解決」ではなく、「気持ちが落ち着くまで待ってくれている」という親の姿勢です。
自分の気持ちがまだ整理できていないとき、人は誰でも話したくないものです。
特に、思春期の子どもにとっては「うまく言葉にできないこと」そのものがストレスになります。
このとき、「じゃあ何も話しかけない方がいいんですね」と極端に振れてしまう保護者の方もいらっしゃいますが、それもまた違います。
必要なのは「話すことを求めない関わり方」です。
会話の根本は「気持ちよく話してもらうこと」
聞く側の姿勢で、子どもの自己開示が決まる
会話は、話し手だけのものではありません。
むしろ、聞く側の姿勢によって内容や雰囲気が大きく変わります。
たとえば、こういう姿勢を意識してみてください。
- 話を最後まで遮らずに聞く
- 相手の目を見て、うなずきながら聞く
- 笑顔を忘れない
これらはどれも、特別なテクニックではありません。
しかし、実際にできているかというと、意外と難しいものです。
日常生活の中で、つい口を挟んだり、顔をしかめたりしていませんか?
その小さな積み重ねが、「話しても無駄」「どうせ怒られる」といった子どもの印象につながってしまうのです。
子どもが話してくれないとき、親ができる3つの工夫
1. 分からないときは、素直に聞き返す
子どもがポツリとつぶやいた言葉。
意味が分からなかったとき、ついスルーしてしまうことはありませんか?
でも、そこにこそ会話の種があります。
「ごめん、ちょっと意味が分からなかったんだけど、もう一回教えてくれる?」
そう聞くことで、子どもは「この人は自分の話をちゃんと理解しようとしてくれている」と感じます。
大人でも同じです。
話を曖昧に受け流されるより、理解しようと努力してくれる相手こそが信頼に繋がります。
2. 嫌だったことは「言葉」に焦点を当てて伝える
子どもに何かを言われて傷ついたとき、そのまま飲み込んでしまっていませんか?
「今は我慢しないと」と思う気持ちは理解できます。
しかし、そのままにしてしまうと、親の中に「わかってもらえない」という感情がたまっていきます。
それがある日、爆発する。よくあるケースです。
だからこそ、嫌だったことはちゃんと伝えるべきです。
ただし「あなたってほんとに失礼ね」ではなく、「その言葉はちょっと悲しかったな」と、人格ではなく言葉にフォーカスするのがポイントです。
これは、非難ではなく共有です。
攻撃しないことで、相手も防衛せずに受け止めやすくなります。
3. 子どもの「沈黙」を責めない
言葉が返ってこない時間。
つらいですよね。
けれど、その沈黙もまた、子どもにとっては「対話」の一部です。
人は、感情を処理するために沈黙を必要とします。
何も言わない=無関心ではありません。
「あえて何も言わない」という選択を、信頼の証と捉えてみてください。
沈黙に耐える力も、親子関係を支える大事な土台になります。
「話せる空気」をつくることが、最も大切な支援
会話が弾まないことを焦らない
「会話ができたら解決に近づく」と思いがちですが、実際はそうとは限りません。
むしろ、「話せる状態になるまでに何が必要か」を考える方が、ずっと効果的です。
そのひとつが「安心できる空気づくり」です。
無理に引き出そうとせず、怒りも不安も受け止めながら、まずは日々の中で穏やかな接点を重ねていく。
それが「この人には話してもいいかもしれない」と思ってもらえる下地になります。
親がカウンセラー役にならないこと
最後に、ひとつ大事な視点を加えておきます。
「子どもに寄り添わなきゃ」と思いすぎるあまり、親がカウンセラー役になってしまうケースがあります。
常に気を配り、気持ちを聞き、感情を察して動く。
これでは、親が疲れてしまいます。
親子関係において必要なのは、無理をして支えることではなく、「一緒に生活する人」として自然に存在し続けることです。
むしろ、親自身が「今日は疲れた」「私も落ち込むことがある」と正直に話す方が、子どもにとっては安心感になります。
完璧な親になることよりも、「安心できる大人でいること」が、長い目で見てずっと大切です。
うまく話すことより、続けられる関わり方を
親の一言が、子どもの意識を決めてしまうこともある
不登校のお子さんと関わる中で、何気なく言った一言が後に影響してしまうケースがあります。
「もう中学生なんだから」
「そんなことで悩んでたら、社会に出てから困るよ」
「周りに迷惑かけないで」
このような言葉は、つい出てしまいやすいものです。
親自身も追い詰められているときほど、こうした言葉が口をついて出やすくなります。
しかし、これらの言葉は、子どもの中に「自分は否定された」という感覚を残しやすいものです。
「自分の状態がいけないのかもしれない」と、さらに心を閉ざしてしまうことにもつながります。
言葉の背景を変えるだけで印象は大きく変わる
同じような意味を伝えるとしても、言い方を変えることで、まったく違う印象になります。
「たしかに今は難しいかもしれないけど、少しずつ考えていけるといいね」
「自分のペースでいいから、できそうなときにやってみようか」
これは決して甘やかしではありません。
子どもの現状を認めつつ、前向きな方向に向かう力を引き出そうとする姿勢です。
「話す内容」より「話す姿勢」が関係をつくる
その場の雰囲気を大切にする
コミュニケーションにおいて大切なのは、言葉そのものよりも、その言葉がどう伝わったかということです。
これは心理学でも「メタ・コミュニケーション(言葉以外の伝達)」として重視されています。
たとえば、こんな違いを考えてみてください。
A.「部屋片づけなさい!」(怒った口調で、背を向けながら)
B.「気が向いたらでいいから、ちょっと片づけてもらえると助かるな」(目を見て、柔らかく)
同じ要望でも、受け手の受け取り方は全く変わります。
子どもは、言葉の意味より「どんな感情で言われたか」を敏感に察知します。
それが積み重なることで、「話しかけられたくない」「反発したくなる」といった反応に結びついていくのです。
無理に親らしくふるまおうとしない
親として、つい「しっかりしなければ」「導かなければ」と思ってしまうことがあります。
けれど、それがプレッシャーになっている場合もあります。
特に不登校のような繊細な状況では、子どもも親の気負いを敏感に感じ取ります。
そして、その緊張が子どもにも伝播してしまう。
もっと肩の力を抜いて、「今の私ができる範囲で関わろう」と思えると、それだけで空気がやわらぎます。
よくある場面での工夫
ケース1:「子どもが突然怒り出す時」
よくあるのが、何気ない一言に突然怒りをぶつけてくるパターンです。
「何か手伝えることある?」と声をかけただけで、「うるさい!」と返される。
傷つきますよね。
ですが、ここで反射的に「なんでそんな言い方するの?」と怒ると、対立が深まります。
こうした場合、まずは「今の言葉は悲しいよ。どうしたの?」と冷静に返してみることをおすすめします。
言い争いではなく、感情を共有する。
それが次の対話への伏線になります。
ケース2:「まったく返事をしてくれない時」
食事に呼んでも、何を言っても返事がない。
無視されているように感じて、イライラする。
このような状況では、言葉のキャッチボールを求めないことが有効です。
「今は言葉が出にくい時期なのかもしれないな」と、こちらの中で受け止めておく。
それでも、挨拶や一言は続けておく。
会話はしていなくても、関係性は維持できます。
たとえば「ごはんできたよ」「お皿ここに置いとくね」だけでも十分です。
その言葉が、後々子どもにとっての安心材料になります。
関係は家族の「間」にできるもの
関係に正解はない
「子どもが不登校になってから、関係が壊れたように感じる」
そんな声をよく聞きます。
でも、親子関係は、変化し続けるものです。
幼いころの接し方と、思春期の今の関わり方が同じである必要はありません。
むしろ、変化に応じて関わり方を「変えてみる」ことが自然です。
これまでのようにはうまくいかなくても、今できる方法でつながっていければ、それで十分です。
子どもと同じ人間として向き合うことが第一歩
「親だから」「育てる立場だから」といった視点から少し離れてみてください。
不登校の子どもも、感情を持つひとりの人間です。
私たちと同じように、自信をなくしたり、不安になったり、誰かに優しくされたり、傷ついたりします。
だからこそ、完璧なアドバイスよりも、温かなまなざしや、素直な「どうした?」の一言が響くことがあります。
コミュニケーションに必要なのは技術より姿勢
最後に、この記事の内容を改めて整理しておきます。
- 会話は「話すこと」より「話してもらうこと」が大切です。
- 聞き方・接し方によって、子どもの心の開き方は大きく変わります。
- 分からないときは素直に聞き返し、嫌だったことは冷静に言葉に焦点を当てて伝えましょう。
- 沈黙もまた、コミュニケーションの一部です。
- 関係を修復するというより、新しい関係を編み直す感覚で向き合うことが大切です。
子どもとの会話は、すぐに変化が見えるものではありません。
けれど、今日あなたが丁寧に頷いたその瞬間から、少しずつ空気は変わっていきます。
その変化を信じて、一歩ずつ、子どもとの時間を紡いでいきましょう。
関連記事
【国内最多の登校支援実績】トーコについて
私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。
「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。
それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。
無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。