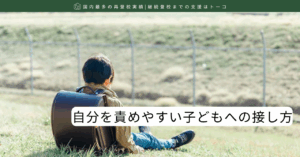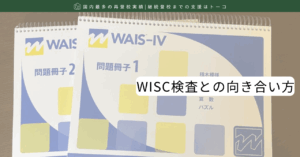過保護は自立の芽を育て「ない」
こんにちは。カウンセラーの竹宮と申します。
不登校の子どもたちに関わる中で、「過保護すぎたのかもしれません」という言葉を保護者の方から聞くことが、少なくありません。
そうしたとき、続けて出てくるのがこの言葉です。
「でも、佐々木正美先生は『過保護は自立の芽を育てる』っておっしゃっていましたよね?」
確かにそうです。
児童精神科医の佐々木正美先生は、「過保護は自立の芽を育て、過干渉は自立の芽を摘む」と語られました。
この言葉は多くの親御さんに希望を与えてきました。
“甘えさせてもいいんだ”というメッセージに救われたという声もよく聞きます。
ですが、ここで立ち止まって考えていただきたいのです。
この「過保護は自立につながる」という考え方は、現在の児童心理学では支持されていません。
実際には、過保護な関わりは、子どもが主体的に生きる力を育む妨げになってしまうことがあるのです。
目次
- なぜ「過保護は良い」と信じられてきたのか?
- 「過保護」と「過干渉」の区別では説明しきれない現実
- 最新の心理学が示す「過保護」のリスク
- 「子どもの甘えを受け入れる」ことと、「自立を阻む」ことは別問題
- 「守る」とは、何を意味するのか?
- 「自立の芽」とは、“自分で選び、責任を持つ”経験
- 親が変われば、子どもの反応も変わる
- 守りすぎないことは、信じることと同じ
- 関連記事
なぜ「過保護は良い」と信じられてきたのか?
親の愛情を肯定するための言葉として広まった
佐々木先生の言葉が広まった背景には、「親の無償の愛情を否定しないでほしい」という強い願いがありました。
「過保護=悪」という見方が主流だった時代に、その反対の立場を示した勇気あるメッセージだったのです。
確かに、親が子どもを大切にしようとする気持ちを「間違い」とされるのは、とても苦しいことです。
佐々木先生の言葉は、その苦しさをやわらげてくれました。
ただし、問題はここからです。
この言葉があまりに広く受け入れられた結果、「過保護はむしろいいことなんだ」と、親の関わりの質を問わない風潮が一部で生まれてしまいました。
その結果、子どもの「自分で考える力」や「失敗から学ぶ力」が、無意識のうちに奪われているケースが出てきているのです。
「過保護」と「過干渉」の区別では説明しきれない現実
よくある説明:「過保護はOK」「過干渉はNG」
現在でも、多くの育児書や専門家がこう説明します。
- 過保護(守る):子どもが困っているときに手を貸す → 良い
- 過干渉(操る):子どもの行動や感情を支配する → 良くない
一見すると、納得しやすい整理です。
しかし実際には、「守ること」と「操ること」を分けるのは、それほど簡単ではありません。
たとえば、
- 朝、子どもが起きられないときに、毎日親が起こす
- 学校に行けない日が続いても、本人に何も言わず好きなことをさせる
- 子どもが不安がる前に、親が先回りして不安要素を取り除いてしまう
これらは「守っている」と言えなくもない行動です。
けれど、こうした関わりが長期間続くと、子どもは「困っても考えなくていい」「どうせ誰かが何とかしてくれる」という学びをしてしまいます。
これは、“守る”ではなく、“学習機会の喪失”です。
子どもの力を信じることなく与えるサポートは「過保護」ではなく「依存の強化」
本当に子どもを守るとは、どういうことでしょうか?
- 子どもが困っているときに、必要な分だけ手を貸す
- できることは自分でやらせ、できないところは一緒に考える
- 支配でも放任でもない、“共同作業”の関係をつくる
これが、本来の“支援”です。
しかし、「過保護は良いこと」という言葉だけが先行すると、
親がすべてを引き受け、子どもが「何もしなくても済む」状態を生み出すことがあります。
それは、支援ではなく依存の固定化です。
最新の心理学が示す「過保護」のリスク
過保護な育ちがもたらす“学習性無力感”
現代の児童心理学では、「過保護すぎる関わり」が子どもに与える影響として、“学習性無力感”という状態が注目されています。
これは、自分の行動が結果を変えられないと学習したときに、人はやがて努力をやめてしまう、という現象です。
たとえば、子どもが何かに挑戦しようとするたびに、親が「それは難しいよ」「やめておいたら?」と止めていたとします。
または、チャレンジする前に親が全部先回りしてしまった場合も同じです。
すると、子どもは「自分でやってもうまくいかない」「何をやってもムダ」と感じるようになります。
結果として、
- 新しいことに挑戦しない
- 自分で考えない
- 他人任せになる
- 自己否定感が強くなる
こういった状態が固定化されてしまいます。
支援が“先取りされすぎる”と、自分でやる力が育たない
最近の研究では、親が過剰に先回りして手を出す関わりが、子どもの実行機能(自己コントロールや計画性)の発達に悪影響を与えることが報告されています。
- 親が毎日スケジュールを管理する
- 宿題をチェックしすぎる
- 問題が起きたときに子どもに解決を考えさせず、すぐに親が動く
これらの行動が長く続くと、子どもは「物事を自分で進める力」を育てるチャンスを失います。
これは、親の意図が愛情であっても変わりません。
結果として、子どもの“自立の芽”は根を張ることなく、土の中で留まり続けてしまうのです。
「子どもの甘えを受け入れる」ことと、「自立を阻む」ことは別問題
甘えさせることは悪ではない。だが、それは“プロセス”であり“結果”ではない
ここで、誤解してほしくないことがあります。
「甘えさせてはいけない」と言っているわけではありません。
むしろ、子どもが「甘えられる」と感じることは、心理的な安心の土台になります。
ただし、甘えは自立のための一時的なプロセスであり、そこに“とどまらせる”ことが目的になってはいけません。
たとえるならば、親の腕の中は充電ステーションのようなものです。
ずっとつなぎっぱなしでは、動けないのです。
必要なときに戻れる場所であることが、重要なのです。
「守る」とは、何を意味するのか?
“やってあげる”ことと、“見届ける”ことの違い
不登校の子どもを前にすると、親は「守ってあげたい」という気持ちが自然と湧きます。
これは、親としての当然の反応ですし、責められるようなことではありません。
しかし、ここでひとつ冷静に見直す必要があります。
「守る」とは、いったい何を指しているのか。
それは、「代わりにやってあげる」ことでしょうか。それとも「失敗しても、見届ける」ことでしょうか。
たとえば、こんな場面を考えてみてください。
- 朝、子どもが学校に行こうと準備をしているが、制服が見つからない。
- 親がすぐに探してあげる。結果、登校には間に合った。
一見すると、「助けてあげた」ように見えます。
けれど実際には、子どもは“探す”という行動をスキップしています。
次の日も同じことが起きたとき、「またママが探してくれる」となる可能性が高まります。
このように、“守るつもり”でやっていることが、実は「学習の機会の剥奪」になってしまっていることがあるのです。
“不安”に対する過保護は、不安を強める
子どもが「学校が怖い」「失敗したら嫌だ」と言ったとき。
親としては、「無理させたくない」「また落ち込ませたくない」と思うのが自然です。
だからこそ、
「じゃあ今日は休んでもいいよ」
「嫌なことはやらなくていいよ」
と言いたくなるものです。
しかし、ここには大きな罠があります。
不安は、避ければ避けるほど強化されるという性質があります。
これは行動療法の基本的な理論です。
怖いことを避ける → 一時的に安心する → だから次も避ける → もっと怖くなる
このループを繰り返すことで、不安は次第に“支配的な感情”になります。
親が過保護に不安から守るほど、子どもは「私は怖いことに立ち向かえない」と学習してしまうのです。
「自立の芽」とは、“自分で選び、責任を持つ”経験
子どもが「選べる」環境を意図的につくる
ここで、あらためて「自立とは何か」を整理します。
自立とは、親から離れることでも、誰にも頼らず生きることでもありません。
それは、自分で選び、自分の選択に責任を持てることです。
言い換えれば、「私はこれでいい」と思える感覚を持てることです。
この力を育むには、親が“選択肢を提示する”ことではなく、
「どうする?」と問う関わりが重要になります。
たとえば、
「学校休むのもいいけど、今日一日どう過ごす?」
「疲れてるように見えるけど、どうしたい?」
このように問いかけていくことで、子どもは「自分で考える」というプロセスに入ります。
子どもが“困ること”は、成長の材料になる
「困らせたくない」「苦しませたくない」――
親として、それを願う気持ちは当然です。
ただ、子どもが困ることそのものが、自己効力感を育てる材料であることを、見落としてはいけません。
自己効力感とは、「私はやればできる」と感じる力のこと。
この感覚は、他人から褒められても育ちません。
- 試してみた
- 少しできた
- またやってみた
- 最終的にできた
この一連の経験の中でしか、育たないのです。
そのためには、子どもが「困っても、自分でなんとかしてみる」経験を重ねられる環境が必要です。
親の先回りや介入が多すぎると、この経験が奪われてしまいます。
親が変われば、子どもの反応も変わる
「あのとき、ああしていれば…」という後悔から抜け出す
ここまでの話を読んで、「私、全部やってしまっていたかも」と落ち込む方もいるかもしれません。
でも、大丈夫です。
子どもは柔軟です。そして、親の変化に非常に敏感です。
あるご家庭では、母親がある日、「今日から、あなたのことは信じて、まずは聞くようにするね」と宣言しました。
それまでは、朝から晩まで、声かけや手助けが絶えなかったと言います。
最初の数日は、子どもも戸惑っていたそうです。
でも、一週間もしないうちに、「今日はこうしたい」と自分から言い出すようになったのです。
親の関わり方が変わることで、子どもが“試しに動いてみる”余白が生まれる。
それが行動につながっていくのです。
子どもに「全部伝わっている」と思わなくていい
親が丁寧に言葉を選んでも、子どもがそれにすぐ反応するとは限りません。
けれど、子どもは見ています。聞いています。感じています。
親が「私はあなたを信じて、あなたのタイミングを待つよ」という姿勢を持つだけで、
子どもはそのメッセージを“体感”します。
伝えることと、伝わることの間には、どうしても“時間差”があります。
でも、伝え続けることで、少しずつ子どもの内側で「自分も動けるかもしれない」という変化が起きてきます。
守りすぎないことは、信じることと同じ
不登校の子どもにとって、家庭は最後の“安心基地”です。
だからこそ、親が「守ってあげたい」と願うのは自然なことです。
けれど、過保護という形での“守り”が行きすぎると、
子どもが「自分の足で立ってみよう」とする機会が失われてしまうことがあります。
「過保護は自立の芽を育てる」という言葉は、多くの親を安心させた言葉でした。
ですが、現代の児童心理学では、その見方は大きく修正されています。
本当に子どもを自立へ導く関わりとは、
- 子どもを信じて見守ること
- 子どもが困ったときに、一緒に考えること
- 子どもの中にある「やってみようかな」の芽を邪魔しないこと
このような積み重ねによって、子どもは少しずつ、自分の道を歩き始めるのです。
親が「守らなきゃ」と頑張りすぎるのではなく、「信じて待つ」という柔らかい在り方が、結果として子どもの根っこを強く育てていきます。
関連記事
子どもにやる気を出させるには、行動ではなく自己認識を動かすこと
【国内最多の登校支援実績】トーコについて
私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。
「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。
それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。
無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。