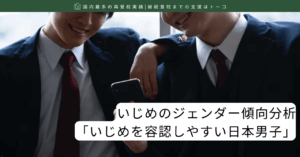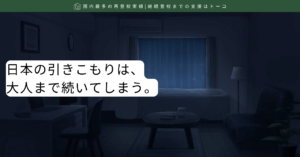希死念慮を抱く子どもにどう接するべきか
こんにちは。カウンセラーの竹宮と申します。
今日は「希死念慮を抱く子どもにどう接するべきか」というテーマについてお話ししたいと思います。
不登校の背景には、単なる学校への行き渋りや人間関係のつまずきだけでなく、時として深い孤独や絶望感が隠れていることがあります。
なかでも、保護者の方が最もショックを受ける言葉のひとつが、「死にたい」という子どものつぶやきではないでしょうか。
これをどう受け止めればいいのか。
甘えているのか、本気なのか。
親としては怖くてたまらないし、どう動いていいのか分からなくなるのも無理はありません。
今日はこのような、言葉にしづらい恐れや葛藤を整理しながら、子どもとどう向き合えばよいのかを、一緒に考えていきたいと思います。
目次
- 希死念慮の言葉にどう向き合えばいいのか
- 甘えか、本心かを見分けるのは難しい
- 「一緒に死のう」と言った母親の覚悟
- 強く責めるのも、何もしないのも、どちらも極端
- 接し方に正解はない。ただ、問い続けることに意味がある
- まとめ:問いを止めないことが、支えになる
- 関連記事
希死念慮の言葉にどう向き合えばいいのか
「死にたい」と言われた時、どうすればいいのか分からない
「死にたいって言うのは、かまってほしいだけなんじゃないかと思ってしまう」
「でも、本当にそうだったらどうしようと思うと怖くてたまらない」
保護者の方から、こうしたご相談を受けることは珍しくありません。
たしかに、「死にたい」という言葉はとても強いものです。
聞いた瞬間に血の気が引くような気持ちになり、「何かすぐに行動を起こさなければ」と焦ってしまうのは自然な反応だと思います。
けれども、そこで“正しい対応”をしようと構えてしまうと、かえって子どもとの距離が遠くなってしまうことがあります。
一番大切なのは、「この子は今、どんな感情を抱えてこの言葉を口にしたのか?」という視点で、その背景を想像しようとする姿勢です。
希死念慮を持つ子どもに多い心理状態
「死にたい」と口にする子どもには、共通するいくつかの心理傾向があります。
- 自分が価値のない存在だと感じている
- 誰にも理解されていないと感じている
- 気持ちを言葉にするのが苦手
- 感情が膨らんだときに、極端な言葉で訴える
- 「死にたい」という言葉が、一種の助けを求める手段になっている
つまり、彼らの内面では「本当に死にたい」気持ちと、「誰かに気づいてほしい」気持ちの両方が同居していることが多いのです。
これは「二次的な希死念慮」とも呼ばれる状態です。
本人が本気で命を絶とうとする段階ではないけれど、絶望の感情が強すぎて、その出口として“死”を選んでしまう。
実際、「死にたい」という言葉の裏には、「もう頑張れない」「苦しい」といった、もっと素直な訴えが潜んでいることが多いのです。
甘えか、本心かを見分けるのは難しい
どちらとも言えない「グレーゾーン」
「これは本気なのか、甘えているのか」と考えてしまうのは、親として当然のことです。
しかし、実際にはこの二択では語れないケースがほとんどです。
希死念慮のある子どもは、感情と行動の一致が難しい状態にあります。
心の中で苦しんでいることを、表面的にどう表現するかが未成熟だからです。
たとえば、
- 元気そうにゲームをしていたかと思えば、突然「死にたい」と言い出す
- 家族とは普通に話しているのに、SNSで「消えたい」とつぶやく
- 何度も「死にたい」と言っては、そのまま眠ってしまう
このような矛盾した言動は、感情の処理能力がまだ発達しきっていない思春期には、むしろ自然な反応とも言えます。
本気じゃないなら、放っておいていいのか?
結論から言うと、「本気じゃないから放っておいていい」という話ではありません。
なぜなら、「死にたい」という言葉を繰り返すことで、本人の中でも“言葉の重み”がどんどん麻痺していくからです。
最初は助けを求めるサインだったはずが、繰り返すうちに本人の中で「これくらい言わないと誰も気づいてくれない」という認識にすり替わっていく。
そして、誰にも響かないことが分かった瞬間、本当に行動に移す可能性もゼロではありません。
ですから、「死にたい」という言葉を真に受けすぎず、かといって軽く受け流しすぎず、真剣に受け止めるけれど、過剰に慌てすぎないというバランスが求められます。
「一緒に死のう」と言った母親の覚悟
私がまだ児童カウンセラーとして現場にいた頃、ある中学2年生の母親からこんな話を聞きました。
その息子さんは、毎日のように「死にたい」とつぶやいていたそうです。
ある日、お母さんは耐えきれなくなり、台所から包丁を持ってきて、こう言いました。
「分かった。ここまで追い詰めたのはお母さんだから、一緒に死のう」
そう言って、泣きながら息子の前に座ったそうです。
息子さんは、驚いた顔で固まりました。
しばらく沈黙が続いた後、彼はこう言いました。
「ごめん、自分のことしか考えてなかった」
それ以降、彼の口から「死にたい」という言葉は出なくなったそうです。
これはもちろん、推奨できる対応ではありません。
ただこの話から伝わってくるのは、「本気で向き合うとはどういうことか」という一つの姿勢です。
「死」を本気で見つめることで、初めて気づけることがある
このエピソードのポイントは、母親が“子どもと同じ目線”で死を見つめたということです。
「死ぬなんて言わないで」と否定するのでもなく、「勝手にしなさい」と突き放すのでもなく、自分自身も巻き込んで正面から受け止めた。
その姿勢が、彼の中で“死”という言葉に初めてリアリティを持たせたのだと思います。
子どもは、「死にたい」と言いながらも、本当に死というものを理解しているわけではありません。
その重さや現実味を知らないまま、「逃げ道」として口にしてしまうことが多いのです。
でも、親が本気でその世界に一歩踏み込んでくると、子どもの中で何かが動きます。
それは恐怖かもしれないし、気づきかもしれません。
いずれにしても、「自分の言葉が、誰かを本気で動かした」という実感は、彼にとって大きな意味を持ったはずです。
強く責めるのも、何もしないのも、どちらも極端
「説得」は効かないが、「無視」もまた危うい
「死にたいなんて言うな!そんなことを言ってはいけない!」
こうした言葉は、親が動揺してしまうからこそ出る反応です。無理もありません。
ただ、ここで少し考えてみてください。
このとき子どもは、自分の苦しみをどうにかして伝えたい気持ちで精一杯なのです。
それに対して「やめなさい」と否定の言葉をかけられると、「また受け入れられなかった」と感じてしまう可能性があります。
逆に、「死にたいって言ってもどうせ何も変わらないし…」と、何も言わずに放っておくとどうなるでしょうか。
子どもは「誰にも届かない」と感じ、さらに孤立感を深めることになります。
否定もしない、放置もしない。
この関わり方を見つけることが、親にとって一番の課題かもしれません。
無力さを受け入れた先にある関わり方
「私にできることなんて、もう何もないんじゃないか」
そんなふうに感じる日もあると思います。
でも、実際のところ、親にできることは少なくないのです。
それは“解決すること”ではなく、“そばにいてくれる人であること”です。
「解決しなきゃ」と焦ってしまうと、会話の主導権が親に偏ります。
しかし、子どもが求めているのは答えではなく、自分の気持ちを整理するための“安心して出せる場”です。
これはカウンセリングの現場でも同じです。
アドバイスや正論が必ずしも心を動かすとは限りません。
むしろ、「ちゃんと聴いてくれる人がいる」と感じることで、少しずつ自分の気持ちに目を向けられるようになっていくのです。
接し方に正解はない。ただ、問い続けることに意味がある
状態は日によって変わる。だからこそ「繰り返し」が大切
希死念慮のある子どもの状態は、常に変化しています。
昨日は笑って話していたのに、今日は布団から出られない。
一見すると一貫性がないように見えるかもしれません。
でも、これは本人にとって気持ちの整理がうまくできていないサインなのです。
この状態を、親が一回で理解しようとするのは難しい。
だからこそ、同じ話を何度もしていいのです。何度も確認していいのです。
「今日はどんな気分?」
「最近よく眠れてる?」
そんな何気ない問いかけの“繰り返し”が、子どもにとっては自分の変化に気づく手がかりになります。
そしてそのうち、「昨日より少し気分がマシだった」「この前よりは眠れたかも」と、自分の状態を自分で表現できるようになっていきます。
自分なりの「確かさ」を持つということ
ここまで読んでくださった方の中には、
「じゃあ、結局どうすればいいの?また、見守りましょうで終わるの?」
と、もどかしく感じる方もいるかもしれません。
たしかに、「正解」を探したくなる気持ちは自然です。
でも、希死念慮のような複雑な状態において、唯一無二の対応策というものは存在しません。
むしろ必要なのは、「我が家の場合はこう接するのが一番納得できる」と思える自分なりの確かさを見つけていくことです。
たとえば、子どもがつぶやいた「死にたい」という言葉に対して、
「そう感じてるんだね。でも私は、あなたが大事だってことだけはずっと変わらない」
と、短くてもいいから、自分の言葉で返していく。
その一言一言が、やがて大きな土台になっていきます。
まとめ:問いを止めないことが、支えになる
希死念慮を抱える子どもに接するのは、とても神経を使います。
言葉一つで状況が悪化するのではないかと怖くなるし、自分の接し方が正しいのかどうか、ずっと迷い続けることになるかもしれません。
けれど、その迷いながら問い続ける姿勢こそが、子どもにとっては何よりの支えになります。
- 否定せず、でも飲み込まずに聴くこと
- 問題を解決しようとせず、今の状態を一緒に考えること
- たった一度の言葉より、日々の小さなやりとりを重ねていくこと
そういった積み重ねが、「この人は自分から離れていかない」と子どもに感じさせます。
そして、もし言葉に詰まったら、思い出してください。
“何を言うか”より、“どう向き合おうとしているか”が大切ということを。
関連記事
【国内最多の登校支援実績】トーコについて
私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,500名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。
「学校の話題になると暴れる」「部屋に閉じこもってスマホばかり見ている」「両親の声かけにまったく返事をしない」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。
それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。
無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。